数日前に映画軍艦島についてFacebookに書いたところハフィントンポストが転載しました。その後キリスト教系のCBS系列と見える「ノーカットニュース」がこれを記事のようにして報道してもいました。(両方とも承認済みです)
その記事を日本語に翻訳して日本の読者向けに報道したところがありましたが、いくつか誤訳があったので直しておきます。
なお、この記事が紹介している非難を私は見てませんが、それはこの文を書く前に私が書いた一連のフェイスブックでのポスティングを読んでないゆえのものも多いかと思われます。私はこれを書く前に鉱夫と言う職業の悲惨さについて書いてます。さらに、この映画が韓国の劇場を構造的に独り占めしていたことを批判しました。
もちろん韓国のネットでは「朴裕河」との名前に悪い印象を持っている人が圧倒的多数なので、私が書いたということだけで警戒の目で見られている傾向はあります。上映館を独り占めしていることに関しては多くの人が批判しているものの、朴裕河の批判となるとどのように受け止めるべきか悩んでしまう傾向が見えるのです。この全てが、訴えられた結果ですが。
しかし少なくともFacebookでは多くの方の支持を得られました。だからこそ転載されたり記事になったりしたのです。韓国の状況を理解していただくため付け加えてみました。
以下、翻訳の修正です。
—————
軍艦島からは「過去の人間が起こしたことに対するつらさ」しか感じられないため
“。。。起こしたことに対する痛みが感じられないため”
その上で「過去の傷への顧慮はなく、すぐに“今日の誇り”として21世紀の大韓民国を描き、満足感を補っている。
“。。。過去の痛みを、深く考えることなくそのまま今日の誇りに置き換えた21世紀大韓民国の代理満足のみがある。”
制作者や出演者の意図とは関係なく、映画の中の『被害者』とはただの観念であり、そのように形式化された被害者は“消耗品”でしかない」と主張した。
“。。。そこでは被害者はただの観念でしかなく、形骸化された「被害者」は消費されるほかない。”
『軍艦島』は日本と朝鮮の対立構造を描いているという点でこれまでの映画と変わらない」と強調した。
“。。。日本と朝鮮を対立構造として描いているという点で、”
Category: 0일본어
[竹内 友章] 朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーの「知識人的あり方」をめぐって 「初期社会文学研究26号」
2016. 6
時空間を越えて「ここより他の場所」を求め、絶えず自分の生まれた場所を相対化し続ける姿勢をとることを、私は「知識人的あり方」と呼びたい。この対極にあるのが、アメリカの歴史学者ジョン ダワーが2015年8月4日付け朝日新聞の取材に応えて語ったナショナリスト的あり方だ。彼は、「グローバル化による格差が緊張と不安定を生み、混乱と不安が広がる。そんな時、他国、他宗教、他集団と比べて、自分が属する国や集まりこそが優れており、絶対に正しいのだという考えは、心の平安をもたらします。」と述べている。
東日本大震災が発生した後に、原発事故によって故郷を追われた多くの人たちの気持ちを私は上手く理解することができなかった。自分の意思ではなく、原発事故によって無理やり強いられたものであることを踏まえても、故郷に強く執着する人たちの思いに寄り添うことができないでいる。自分がどの時代にどの場所に生まれるかを自分で選択できない以上、なぜたまたま自分が生まれた場所にこだわるのかがわからないでいる。自分が生まれた場所を「故郷」と呼ぶ時、その場所に特別な意味づけを見出すことができない。固有名詞の「福島」を語る文脈が、そこで生まれなかつた人々によって相対化されたFUKUSHIMAとなって初めて自分と対置させることができる。
朴裕河が『帝国の慰安嬌』において描きだした慰安婦像を前にして、激しい対立を繰り返してきた韓国の「挺対協」及び日本国内の支持者や現在の韓国政府と、日本政府並びに国内の保守派の論客達は、双方共にかなり戸惑うだろう。「挺対協」及び日本国内の支持者は、やがて彼女の主張に怒りを覚えるだろう。なぜなら彼女の慰安婦に関する記述は、全ての慰安婦は日本軍により強制されたものだという「挺対協」の従来からの主張に対して、実際には慰安婦の徴集に多くの朝鮮人商人が関与していたとしているからである。しかも彼女は、慰安婦たちが単なる性的奴隸に留まらず、兵士のあたかも母や妻のような感情を時には持ちえたことを指摘している。こうした説明は、慰安婦を36年間にわたる日本の朝鮮民族に対する植民地の圧制の象徴として、日本政府への全面的な謝罪を求める「挺対協」が主導してきた反日運動に水差すものとして受け止められた。その結果として、彼女は「挺対協」やその支持者たちから出版差し止めを含む訴訟を受けることになつた。他方で、日本政府や国内の保守系論客達は、最初は彼女があたかも自分たちの側の味方であるかのような錯覚を感じるだろう。なぜなら全く妥協の余地のない「挺対協」に比べて、彼女の説明はより柔軟で日本軍の関与を低減してくれるように見えるからだ。しかし、彼女は日本軍の加害者責任を少しも低減などしていない。実際の慰安婦徴集の現場において日本軍が強制しようがしまいが、直接関与したのが朝鮮人商人であろうがなかろうが、日本兵に性的奉仕を行う慰安婦というあり方自体が、日本による朝鮮の植民地体制を前提に行われたというより大きな歴史的事実をいささかも曖昧にしていない。彼女が問題にしているのは、慰安婦問題を追及する方法において、「挺対協」が採用している考え方が、むしろ問題の本質をゆがめているのではないかという点だ。ソゥルの日本大使館の前にいたいけな少女をかたどった慰安婦像を立て、欧米諸国の議会において反日決議を促す運動を遂行し、日本政府による全面的な謝罪と慰安婦への補償以外の解決策を認めないという「挺対協」の運動のあり方は、日本植民地下における朝鮮人の生き方を「日本人=加害者、朝鮮人=被害者」としてステレオタィプ化し、全ての問題の原因を日本軍=日本による植民地に見出すことで、現在まで続く韓国社会のはらむ様々な課題の解決への道をむしろ正視できなくしているのではないかという指摘が含まれている。端的に言えば、いつまでも反日運動にこだわっていても未来は描けないのではないか、もつと近現代の韓国社会の在り方自体を自分達の問題として捉えなければならないのではないかと述べているように思える。
さて一方でイレーヌ・ネミロフスキーは、ロシア革命により「故郷」を追われフランスに亡命をしたユダヤ系ロシア人の作家である。彼女は、一貫して自らの出自であるユダヤ系ロシア人の視点にこだわりながら、知識人の目で亡命先である二つの大戦間のフランス社会を描いていく。そもそもユダヤ人である彼女にとつて「故郷」は、そのまま素直に同化できる対象ではなかった。自分が生まれる前のどこかの時点で、別の場所から彼女の一族が移動してきた結果として、ロシアは彼女の「故郷」となった。ユダヤ系ロシア人の彼女の家族にとって、「故郷」ははたえずポグロムの恐怖を抱え、たとえ経済的には恵まれた状況にあろうとも緊張を強いられる場所であった。富裕な家庭に生まれた彼女は、ロシアで生まれながらロシア語を母語とせず、幼少時から外国語であるフランス語によって構成されたフランス文化を母体として自らの精神を組み立ててきた。亡命によって、そうした自分自身の文化的母国ともいえるフランスに移動をし、ごく自然にフランス語で小説を書き始めた。彼女にとって「故郷」は、記憶というフィルターを通してフランス語で記述された小説の中に挿入され、あらかじめ抽象化され実体を持たない。亡命ユダヤ系ロシア人として、はるか昔に追い出されたユダヤ民族発祥の地とロシアという二つの「故郷」を喪失していながら、いまそこにあるフランス社会に生きている。
彼女の遺作で代表作でもある『フランス組曲』は、そうしたユダヤとロシアという二つの「故郷」を実体ではなく内面化された意識としてしか持ちえない立場で、ナチスドイツによって占領された第二次世界大戦時のフランスの社会を克明に描いている。戦後、加藤周一らによって日本との比較において高く評価されたレジス夕ンスのフランスではなく、ナチスドイツ並びにその傀儡政権であるヴィシー政権下のフランスに生きる様々な階層の人々の生活を描いている。私自身も昔、ナチス占領下では多くのフランス人がレジスタンスに身を投じ、ドゴール派や共産党といったイデォロギーや政策の違いを超えてナチスやヴィシー政権に対抗して粘り強い戦いを長期に渡り継続したと考えていた。ハリウッドが作り上げた「カサブランカ」のような映画は、そうしたプロトタイプ化したレジスタンス神話を忠実に描いて見せた。しかし実際には、大多数のフランス人はレジスタンスに身を投じるのではなく、ナチス占領下で何らかの妥協をしながら生きる他なかった。中にはナチスやヴイシー政権とうまく折り合いをつけて、上手に金儲けをしたり、出世を図ろうとした人たちもいた。そうした人たちの一部は、よく戦後のドキユメンタリー映像に描かれているような髪の毛を坊主頭にされたナチスのフランス人情婦たちのように、戦後厳しく糾弾された。
ネミロフスキーは、一部の英雄的なレジスタンスの闘士や海外に亡命することのできた少数の恵まれた人々ではなく、ナチス占領下でどこにも逃げることもできず、留まってそこで生きていかなければならなかった貴族、政治家、実業家、商人、農民、労働者、教師、芸術家、学生、主婦といった様々な階層の人々の生態をパリと地方の小都市を舞台に淡々と描いていく。彼女の描写は、そうした人々にとりたてて同情的でもなく批判的でもなく、どこか冷めたい視点で丹念に細部を描く。旧家のブルジョアのしきたりにとらわれ、強権を持つ母親に対してなんら抵抗することのできない夫に嫁いだ妻は、たとえ夫が捕虜としてナチスの収容所にとらわれていようとも、彼への同情を少しも感じることができず、むしろ彼の粗暴さと戦前の浮気を許すことができない。彼女は、自宅に逗留するナチスの将校の繊細な文化的教養や洗練された立ち居振る舞いに次第に惹かれていく。戦前のフランス社会の階級性にどっぷりとつかり、社会の指導者としての意識に凝り固まっている貴族は、ナチス占領下でも何ら変わることなくヴィシー政権の構成員として社会秩序を守ることに汲々とする。階級的に虐げられた女性は、ナチスの兵士の情婦となることでその威を借りて、自分を見下した社会を見返そうとする。こうした生き方を大多数のフランス人がナチス占領下で余儀なくされたことに、私は納得する。数多くの抵抗文学によって描かれたレジスタンスは、むしろごく例外的な状況として理解すべきだと思う。戦時下のフランス社会は、レジスタンスに参加したごく少数の人たちの英雄的な行為ではなく、ナチス占領下でも強固に継続された社会の在り方、枠組み、人々を根深く拘束する様々な伝統的な慣習や偏見によって構成され、それは戦後崩壊することなく今でも継続していることに注視すべきだと思う。先年ノーベル文学賞を受賞したモディアノが執拗に追求しているのも、むしろナチス占領下に浮かび上がったフランス社会の矛盾や欺瞞が、戦後解消されることなく人々を拘束し続けている状況だ。最近頻発したイスラム過激派によるフランス国内でのテロも、フランス社会がグローバル化の進展の中で、多くの人々を不安に陥らせ、その解決の糸口をある者はナショナリズムへ、そしてある者は対抗上異なる宗教であるイスラムに求めようとする動きの中でとらえるべきだ。パリの通りをフランス大統領を先頭に『シャルリは私だ』というスローガンを抱えて行進するさまは、民主主義を奉じるフランス社会が盤石ではなくむしろ大きな危機に直面していることを示しているのではないか。
ただ残酷なのは、多くのフランス人がレジスタンスではなくナチスやヴィシー政権と折り合いをつけながら生き延びようとしたのに対して、ネミロフスキーは生き残ることができなかつたことだ。普通のフランス人には許容されていた生き方が、彼女には与えられなかった。知人や友人たちの必死の努力にもかかわらず、皮肉なことに実体を伴わないロシアとユダヤという彼女の刻印は、彼女をフランス社会から引き離し強制収容所へと送り込んだ。友人の元にかくまわれた子供たちによつて『フランス組曲』の未完原稿は保管され、戦後随分とたってから十年ほど前にようやく出版され、大きな反響を呼び起こした。
『帝国の慰安婦』を読んで、著者の朴裕河はネミロフスキーと同様に「故郷」を喪失している人ではないか、あるいは知識人としての立場を選択した人なのではないかと感じた。彼女がこの著書の中で繰り返し指摘しているのは、慰安婦が日本軍の強制によってのみ生み出され、日本政府による徹底した謝罪と補償なしでは全く解決することはないという「挺対協」並びに現在の韓国政府の主張は、それ自体現在の韓国社会が直面する問題をはぐらかし、解決への道を閉ざすものではないかという問いかけだ。実際には、日本の植民地下の朝鮮においては、大多数の朝鮮人は植民地政府に対して抵抗ではなく何らかの妥協をしながら生きてきた。そこでは植民地政府の日本軍のみが権力者として存在するのではなく、数多くの朝鮮人もまたその権力構造の一翼を担った。慰安婦自体もすベて日本軍の強制によって遂行されたのではなく、そこに数多くの朝鮮人商人が関与していた。ナチスの占領に比べてもはるかに長期に渡った日本による植民地体制下においては、それを受け入れその中で自分の生活を組み立てていかなければならなかったのが大多数の朝鮮人であったはずだ。そしてフランス社会の様々な矛盾や課題がレジスタンスによって解消されず、社会の底に澱のように堆積し、それがグローバル化の浸透の中で新たなナショナリズムやテロリズムの温床となっていったのと同様に、現代韓国社会の抱える課題は過去の日本植民地化の日本政府や日本軍の悪行や現在の日本政府の対応を糾弾するだけではいつまでも解消されない。さらにグローバル化の進展の中で生み出された現代韓国社会のはらむ大きな断層をこそ直視していくべきだと主張しているように思える。
もし彼女と同じことを日本人が主張した場合は、表面上日本の保守系の政治家やメディアが声高に叫んでいることと一見区別が難しくなってしまうだろう、自分たちの責任を回避し、朝鮮民族に大きなダメージを与え続けた自らの歴史に蓋をする者と受け止められかねない危険さを伴う。事実、北朝鮮による「拉致被害者」の運動が本人たちの意図するものとは異なり、日本が戦前朝鮮民族に対してしでかした大きな加害者責任をすっかり忘却させる上で大きく貢献し、完全に保守政治家のナショナリズムの高揚に利用されている状況をみるとその主張の難しさが容易に想像できる。朴裕河が韓国において、「挺対協」や彼らに後押しされた慰安婦によって訴訟され、日本国内の慰安婦問題の解決を目指す運動家たちによっても批判されているのは、そうした困難さを示している。
日本大使館の前に慰安婦の少女の像を建立することは、問題の解決を図るのではなくむしろ遠ざけることにしかならない。自分が属する国や集まりこそが絶対に正しいのだという考えは、恐らく心の平安をもたらすのだろう。そうではなく「故郷」を突き放すこと、そのことによって自らの属する国や集まりから場合によっては敵視され疎外されたとしても、知識人はそうすべきだと私は思う。
2015年6月13日に法政大学で開催された日本社会文学会の如周年記念大会で朴裕河の講演を聞いた。その時の彼女は、決して先入観や多数意見をそのまま受け入れず、絶えず批判精神を持って物事を見極めようとする強靭でしなやかな精神の持ち主のように思えた。朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーという二人の優れた知識人に学ぶ事は多い。厳密な実証も注意深い歴史的考察もされずステレオタィプの言論が跋扈する現代のよぅな時代には、「知識人的あり方」を自分自身の基準として改めて凝視すべきではないかと思ぅ。
<完>
追記
「慰安婦問題」に関しては、日韓両国政府間で一定の合意が成立したものの、韓国国民の一部は、頑なに拒否している状況がある。朴裕河は、韓国検察に名誉毀損で在宅起訴された。
最近都内では『フランス組曲』を元にした同名の映画が封切られた。原作とは全く異なるものだが、比較の為に観てみるのも一考だ。
*ホームページ管理者注:著者は訴えた主体を挺対協と考えていますが、訴えた支援団体は<ナヌム(分ち)の家>という福祉住居施設団体です。
日韓のトゲ 慰安婦問題 山本勇二論説委員が聞く 「東京新聞」
フェイスブックから、2017年5月11日
今回の大統領選挙で安哲秀候補を支持した私に対して、フェイスブックの友人の多くが失望あるいは憤慨したようです。私のことが革新的に見えていたのは、表面的なものに過ぎなかったと思われたようですね。
日本について意見を述べるというだけで、私のことを、日本との「妥協」支持者あるいは担当者だと考えたがっていた人々の「念願」あるいは「呪文」が表面化したと言えるかもしれません。しかし、私にはその現象が、安哲秀は洪準杓と連帯するはずだとしてきた、間違っているだけでなく、悪意に満ちた期待と、とても似ているように見えます。
実際、どこに焦点を置くかによって、革新の基準は異らざるを得ません。私は、私たちの社会の革新、保守という区分が、もはや意味のないものになっていると考えており(最も革新的な男性が最も家父長的でもありますから)、あえて言うなら、私の価値観はむしろ急進(という表現も実は適当ではありませんが)に近いということを長い間の付き合いのフェイスブックの友人たちはご存知でしょう。
それでも、私の志向が、資本と国家の問題をわかっていないことに由来する無邪気なものだという人もいました。疎通が十分でなかったせいでしょうが、そのような断定から、私はフェミニズム論争の頃から考えていた「概念の浅薄化」とでもいうべき状況がもたらした現場を再度発見しました(これについては、いつかまた書きます。今は詳しく書く気力がありません)。
私が葛藤の治癒に関心が高い理由は、憎悪と差別と敵対が、不和と戦争をもたらし、他者の生命を奪う根源にあるものだからです。そして多くの場合反知性主義的な態度が作る偏見と敵対が、いかなる暴力を生み出すのかは、私をめぐって起こったことが十分に説明しています。
私が今回の選挙で悩んだ末に、保守/進歩の既存の構図を打ち破るという安哲秀候補の試みを誰よりも進歩的な試みだと考えた理由も、そこにあります。それは政策ではなく、方向性への支持でした。
そして、失敗はしましたが、その試み自体は、韓国社会に未だ訪れていない、それゆえに「革新的」な価値であると考えます。その到達点は、恐らく統一であり、東アジアの平和でしょう。私の志向性を、単に分裂を「無化」させるものだとか、国家間の政経癒着的な和解とみなそうとする理解は、学問と政治の違いを無化させる大変単純な理解だと言えます。私はいわゆる「政治」に大きな期待はしていないけれど、それでも時に全ての学問を超える価値の実現が可能となるものとして、なおその役割に期待しています。それは、学問的には厳しい批判が可能でも、政治的にはその曖昧さを許すことに繋がります。
今回の選挙では、どんなに革新的な候補であっても、彼らの支持者たちが、口にするのもおぞましい悪態を私に浴びせかけたり、よく知りもせず嘲笑した人々でもあるというアイロニーが、私には存在しました。そのため、私には、代議民主主義を具体化させられる候補自体が存在しませんでした。そのようなアイロニーを抱きながらロウソクデモに参加し、投票に参加したのは、ただ、その多数の隙間のどこかにいたはずの「彼らの中の別の存在」と連帯したかったからです。フェイスブックが私に教えてくれた存在、つまり皆さんです。
選挙は終わりましたが、文在寅大統領を誕生させるための自らの運動を、書きたい小説を書くことに集中したかったからだと述べた作家の言葉を遅ればせながら見つけました。また、新たに始まる文在寅大統領時代を「詩だけを書いて研究にだけ専念できる太平聖代」の始まりだと見做す詩人もいました。
しかし、私にはそのような時間はまだ来ていません。長い苦痛の果てに無罪判決が下されたにもかかわらず、むしろより陰湿な石が私に飛んで来ます。何よりも、私をそのような苦難に陥れ、積極的に加担した人々が保守ではなく、「革新」層だということが、私のジレンマです。彼らと最も近い場所にいた候補が、文在寅候補でありましたが、社会構造に対する問題意識を彼から見出すことができなかったために、私は彼を支持できませんでした。
私の本は、革新の中の欺瞞について問題提起しているだけです。しかし、待っていたのは公開討論ではなく、長い沈黙と、口封じでした。また、同じような欺瞞と暴力を今回の選挙でも、見せ付けられました。
私にとって、文在寅政権が新しい時代になる日は、<革新>層の中に存在する欺瞞と暴力を、革新層みずからが認識する日です。私への嫌悪や抑圧に対する「主流革新層」の沈黙が破れる日です。その日が来ない限り、私にとって文在寅時代も朴槿恵時代と変わりません。
参考までに申し上げれば、私を非難していた人々も、慰安婦問題をもっと知るようになれば、考えが変わると確信しています。もちろん、守らなければならないものがある人には期待していません。
3年近く、裁判の反論のために止むを得ず多くの資料を見ましたが、私の考えを修正する必要を感じませんでした。さらに大きなアイロニーは、私の苦難が、実は本の問題でさえなかったということです。排斥は、知識人の偏見と排斥主義が、告訴は、ロースクールの学生と弁護士の蛮勇さと運動家の策略が作り出したものでした。
このことについてもっと詳しく書かなくてはなりませんが、まだできずにいます。判決後、3ヶ月以上経ちましたが、緊張が解けたのか、気力と体力が回復していないためです。彼らの中からもこの問題を提起する人が出てくることを期待しています。
少しフェイスブックをお休みします。その間、フェイスブックの友達を削除したい方はどうぞなさってください。無罪判決の出た日、「いいね」を押してくださった方が2千数百名いました。その方たちだけが残ってくださったとしても、とても多いのです。
選挙結果について、「パルゲンイ(赤)国家」云々する方については、私から削除させていただきました。
フェイスブックの友人の整理をする余裕がないため、これまで承認を待ってくださった多くの方には、心から申し訳ないと思っています。もう少しで友達承認できるようになると思います。
17年前に最初の日韓関係論を出した時から、私は綱渡りをする心境で書いて来ました。
17年が過ぎた現在、私が立っている空間は、ようやく足がつける程度の面積です。あえてこのような空間に立っているのは、稚気や周りに逆らおうとする情熱があり余っているからではありません。その面積がいつかはもっと広くなるという確信を持っているからであり、その空間が必要な人々がいると思うためです。
狭くて危なっかしく見えるその空間に、共に立ってくださったり、支持してくださる方だけが残ってくだされば嬉しいです。可能なら、私が会いたいと思っていた方々とまた会えると嬉しいです。
(1月に行った「無罪判決を記念する毎月の会合」も継続できず、個人的に会いたい方にも連絡できませんでした。心身の状態があまり良くなかったためです。しかしまたすぐに連絡できるでしょう)
近頃私を非難したツイートを添付しておきます。このすさんだ「言葉」に、改めてやるせない気持ちになります。「和解は加害者が先(許しを請うことから)」だと説教した方が多くいましたが、この言葉もやはり、私の本を理解できていないだけでなく、先に述べた「概念の浅薄化」が生み出した言葉です。
2017・5・11
翻訳: 金良淑
中沢けい, 法理に基づいた「帝国の慰安婦」無罪判決 少女像問題めぐり再び緊張する日韓関係を憂慮
中沢けい
1月25日、ソウル東部地裁は刑事上の名誉毀損で懲役3年を求刑されていた「帝国の慰安婦」の著者朴裕河氏に無罪判決を出した。ハフィントンポスト日本語版は、韓国版から以下の部分を引用している。「被告人が本で開陳した見解については批判と反論が提起されることも予想され、慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れもあるが、あくまでも価値判断を問う問題であり、刑事手続きにおいて法廷が追及する権限や能力を超える」。刑事責任を問う場合は抑制的であるべきだという常識に乗っ取った判決と言えるだろう。
無罪判決に安堵
朴裕河氏が起訴された直後の2015年11月26日に有識者らが「朴裕河氏の起訴に対する抗議声明」を発表、私も賛同人の一人として記者会見に応じた。抗議声明は発表後も新たな賛同人を得ている。最近ではノーム・チョムスキー・マサチューセッツ工科大学名誉教授、ブルース・カミングス・シカゴ大学教授が加わり、賛同人は70名ほどになった。当初からの抗議声明賛同人であった私は今回の判決に安堵を覚えている。
しかし、安堵を覚えることはできても、喜びを感じることができない。その理由は2017年に入り日韓関係が慰安婦問題を巡って再び緊張していることにあるのは言うまでもない。
2015年12月の日韓両政府の慰安婦問題妥結には、その唐突さに当惑せざるを得なかった。しかし、この政治的妥結が慰安婦被害者の救済を進ませ、戦時における女性の人権侵害をどう防ぐかという冷静な議論を深める端緒になってくれることを願わずにはいられなかった。その点は今も考えは変わっていない。
韓国国内にはこの妥結を是とはしない意見があることは承知している。確かにこの妥結はあまりにも唐突で、慰安婦被害者の了解を十分に得ていたとは言えない。妥結後、韓国政府が慰安婦被害者の説得に努めてきたことは、聯合ニュース、朝鮮日報などの日本語版で知ることができた。また、各社の日本語版の報道は妥結に反対する人々が、抗議のために慰安婦被害者の苦難を象徴する少女像を各地に建てていることも報じていた。このようなせめぎあいの中で日本政府から慰安婦救済に当たる財団設立に伴い10億円が支払われたのは2016年8月だ。慰安婦被害者の納得を得るのは極めて難しく忍耐のいる仕事であることは想像できる。
誤解を広く生み出している安倍首相の処置
釜山の日本領事館近くに少女像が新たに設置されたことを理由に、日本政府が韓国政府へ妥結を誠実に履行するように求めたのは2017年に入ってからのことだ。続いてテレビ出演した安倍首相は少女像を「遺憾」と表明、さらには駐韓日本大使などを一時帰国させるという強い処置にでた。1月31日現在、一時帰国した外交官はまだ韓国へ戻っていない。日本政府、いや安倍首相がとったこの処置は、日本国内に少女像の撤去が財団設立資金提供の見返りであったかのような誤解を広く生み出している。また極右保守派の中には「少女像を公道の不正使用で撤去すればよい」などと内政干渉と取られかねないようなことを唱える向きさえある。
本来ならば財団設立資金提供と少女像の撤去は等価ではないことを丁寧に説明しなければならないのが、外交上の約束を交わした日本政府の果たすべき義務だ。二国間の取り決めで負っているはずの義務を果たすことなく、安倍政権は資金提供の見返りに少女像撤去が約束されていたかのような誤解を放置し日韓の対立を生み出している。また外交官を帰国させるという強い措置は、いたずらに問題を肥大化させてしまった。慰安婦被害者の説得にあたっている韓国政府の背中を蹴り上げるような措置だ。妥結は「金を払ったから言うことをきけ」というような雑駁なものではなかったはずだ。
慰安婦を中傷する展示を放置
日韓双方の妥結は双務的であるので、日本政府は国内の慰安婦被害者に対する侮辱を繰り返す勢力に対して、問題理解を求める必要がある。にもかかわらず、日本政府がそうした努力をした形跡を認めることはできない。北海道新聞が報じるところでは、虚偽もしくは誇張された内容で慰安婦被害者を誹謗中傷する慰安婦展が公共施設でくり返し開催されている。慰安婦中傷を材料にヘイトスピーチを繰り返してきたグループによるものだ。声高に「日韓断交」を叫び、ヘイトスピーチを繰り返してきた在特会とも関係するグループであることが分かっている。慰安婦被害者を中傷誹謗、侮辱し、それをそのまま韓国人へのヘイトスピーチに展開させるこれらの人々の行為について、ヘイト対策法が成立しているにもかかわらず日本政府は公共施設の利用を止めようとはしない。もし、それが市民による表現の自由の範疇に入るのだと言うのであれば、少女像の建立も公権力がいたずらに介入できないことは自明である。前者はヘイトスピーチを繰り返すという点で違法行為である。
少女像を「日本に対する嫌がらせ」と捉えることに問題
そもそも少女像を日本に対する嫌がらせと受け止めるところに、政治的妥結の精神を裏切るものが潜んでいる。もし少女像が公道にあることに不都合を感じるのならば、日本の在外公館の敷地を提供し、今後は両国が一致協力して戦時における女性の権利を守るためになにをしなければならないかを追求して行く象徴とすればよい。そういう方法も考えられるのである。
そのほかにもこれを日韓対立の象徴と捉えなければ知恵はでるものだ。そうした前向きな知恵が出ないのは、極右保守派の、慰安婦問題は日本に対する嫌がらせだとして、日韓の対立と見る見方、考え方に縛られすぎているのである。極右保守派は慰安婦問題を国内政治のために利用してきた。左派リベラル攻撃、朝日新聞攻撃などの材料に使ってきた。そして排外主義者たちはこれをヘイトスピーチの材料にしてきた。そこには外交的視点も普遍的問題に対応しようとする視点もない。これらの人々は安倍首相の今回の無謀な措置を歓迎している。しかし、それは日本のごく一部の見方、考え方であることも申し添えておく。もしこのまま誤解を含んだ韓国敵視の雰囲気の放置を続ければ日韓関係が緊張するだけではなく国際社会からも日本は非難を浴びることになるだろう。ここ数年は東京の大学院への韓国人留学生は激減している。すでに影響は出ているのである。
このような雰囲気の中で結審を迎えた朴裕河氏の名誉毀損事件の無罪判決に「慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れ」への言及があることは当然だと言わなければならない。またそのような中でも法理に基づいた無罪判決を出したソウル東部地裁に敬意を表する。朴裕河氏の著作の悪用は著者の責任範囲を超えるものである。悪用されたものについては厳しく批判されてしかるべきであるが、その責任を著者が負う必要はない。残念なことに1月26日、韓国の検察は控訴を決定した。控訴審においても公平な判断を期待したい。
何を守るべきなのか――少女像問題への提言
韓国外交部が釜山の少女像の問題解決に乗り出した模様だ。しかし、少女像の移転要求は、問題の答えではない。
確かに、一時帰国とはいえ、日本大使が帰国後、これほど長く復帰しなかったことはなかったし、そのような意味で、外交部が積極的な行動をとることは、この時点では当然のことではある。しかし、市民のために存在する自治体が市民の意思を超えて行動できるはずがない。何よりも「強制移転」は、これまで以上に事態を悪化させる。
実は私は、釜山の少女像設置に問題で日本政府が大使を帰国させたのは性急だったと思う。日本が怒りを表明すれば少女像が撤去されるだろうと思ったのであれば、日本の韓国理解はまだ十分ではないと言わなければならない。その意味では、日本に対しても言いたいことはあるが、まず韓国の問題について考えてみることにする。
与党はもちろん、野党政治家、マスコミ、国民のほとんどが「日韓の合意は誤りで、少女像はそれに抗議するためのものだから正しい」と考えている。同時に、日韓合意の正当性やウィーン条約を根拠に、撤去すべきだと言う人もいる。
ところが、これほど対立が深いのに、問題の少女像が何を意味するのか、日韓合意とはどんなものだったかについて、原点に戻って考えてみようとする人はほとんどいない。ほとんどの人がただただ反対したり、賛成したりする。そうした思考停止の事態が、片方は「守る」ことに全力を尽くし、もう片方は物理的な力を行使すべきかを考える段階にいたる状況を作った。
この問題を解決するには、何が必要だろうか。いうまでもなく、最初に朝鮮人慰安婦への総体的な理解が必要だ。ところが、慰安婦問題の場合、長い年月をかけてメディアが積極的に報道した結果、すでに「国民の常識」となった具体的な理解が存在する。昨年公開された映画『鬼郷』は、そのような現代韓国の「集団記憶」を描いた映画だ。
ところが、そのような理解は、果たして正しいのだろうか。私は、昨年の公開直後にこの映画を見たが、心境は複雑だった。端的に言えば、その映画に表現された「情緒」は正しく、「事実」は正しくない。
だから、私は感情に共感しながらも、涙を流すことができなかった。一例として、火で焼かれる場面は、ある元慰安婦の絵をモチーフにしたというが、この女性の最初の口述によれば、女性を焼いたのは虐殺のためではなく、病気になって死んだ女性を火葬するためのように見える。また、別の方の手記には、自ら他の慰安婦の女性を火葬しなければならなかった話も出ている。
批判をするなら、このような凄絶な体験をさせた戦争と、軍人・慰安婦の間のヒエラルキー、そしてそのような不平等な関係を作った日本の植民地支配の責任について、まず問わなければならない。批判は、正確でないと受け入れられないものだ。
つまり、慰安婦問題は、朝鮮人慰安婦とはどんな存在だったのか、そしてこの問題が浮上してから四半世紀の間に何があったのか、日本が何をしたか、できなかったのかを正確に知らない限り解決されない。また、初期とは違って国民的な関心事となり、教科書にも登場する問題となったので、国民的な理解と合意が必要になった。
したがってこう提案したい。日韓両政府は、この問題を協議するための協議体を作ってほしい。そして、その議論のために、日本政府は、駐韓大使を直ちに復帰させることが望ましい。協議体は、慰安婦問題について長い関与してきた、しかし対立中の日韓の学者を主要メンバーとし、支援団体と慰安婦の当事者とメディアが傍聴したり、中継したりするようにして、疑問を投げかけ、答えることが可能な形にしなければならない。実際、論点は多くない。そのようにして、両国民の共通の理解を導かなければならない。
慰安婦問題は、両国の国民があまりにもよく知る問題となり、もはや政府間の合意だけでは問題を解決できなくなった。朴槿恵政権が見落としたのはその点である。対立が2000年代以降に本格化したのは、民主化とインターネットの普及の結果であり、市民が力を持つようになった21世紀の世界を反映している。
少女像に関する批判のうち、「当事者を度外視した」という批判がある。私はその認識に共感する。私が会った何人かの元慰安婦は「なぜ解決されないのか」さえ知らなかった。ところが支援団体は、外交部と実に十数回の意見調整をしたという。だとすれば「当事者を度外視」したのは誰だろうか。
このすべての問いが再び必要だ。時間がかかっても。「お金をあげたから終わった」との考えには、まだできていないことへの問いがなく、「金なんかで解決したと思うな」との考えには、困難な合意を成し遂げた「外交」への尊重がない。何よりも「責任とは何をもって負えるのか」への根源的な問いかけがない。
少女像を守ろうとする人々は、少女像が「痛み」を象徴すると言う。確かに少女像自体はそのようにも見ることができる。しかし、他でもない領事館や大使館の前に立つ少女像は、明らかに「抵抗と抗議」を象徴する。実際に少女像の裏側には「崇高な精神」を記念すると書かれている。少女像は本当は「あの」慰安婦の少女ではなく、90年代以降の「運動」と、運動に込められた「粘り強い抗議の精神」を表している。四半世紀続くなか、慰安婦問題には、こうした意識あるいは無意識のトリックが少なからず存在するようになった。
その抗議が正しいとすれば、どれほど正しいのか、なぜ正しいかの国民的な問いかけと確認が必要だ。日本を相手にしたとき、私たちはいまだ対話という姿勢を身につけていない。
少女であれ、抗議の精神であれ、「守る」ことは崇高だ。しかし、思考停止の状態で「守っ」たり、反対したりすることは、最終的には誰のプライドも守らない。
手遅れになる前に、思慮深い行動が必要だ。確執は、相手だけでなく、自分自身も守らない。
朴裕河、無罪判決 インタビュー [中央日報]
朴裕河、無罪判決 インタビュー, 中央日報2017年2月24日(リンク)
[ナム・ジョンホの直撃インタビュー]
学者たちを密室に閉じ込めれば、彼らの間で権力化が起こる
『帝国の慰安婦』、一審で無罪になった朴裕河教授
世の中には、それまでの定説に真っ向から挑戦し、激しい論争を呼んだ本が少なくない。進化論を説いたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』、地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスの『天球の回転について』などがまさにその例だ。これほどの記念碑名著ではないが、日帝植民地史に新しい角度からアプローチした『帝国の慰安婦』もまた大きな論争を引き起こした。本書が出ると、慰安婦ハルモニたちは、自分たちを「自発的売春婦」にして、名誉をひどく失墜させたと、著者の朴裕河世宗大教授(60)に対し民事・刑事訴訟を提起した。朴教授は昨年1月、民事訴訟では敗訴したが、刑事裁判では1年間の攻防の末、先月末、一審で無罪を宣告された。慰安婦動員の真実はどこにあり、学問の自由はどこまで保障されるべきか。これほど大きな反響を呼んだ事件の主人公である朴教授に、今月7日にお会いした。
(写真)
キャプション:「自発的慰安婦」論争を起こした朴裕河教授が去る2月7日、無罪判決を受けたソウル東部地方裁判所前でインタビューに応じた。朴教授は議論の火種となった自著『帝国の慰安婦』について説明した。
Q:無罪判決を受けた感想は。
「ともかくほっとした。判事が合理的に裁判を進めてくれ、名誉毀損の基準にひっかかるところもまったくなかったので、無罪になると思っていた。それでも、実際のところ、はたして判事に独自の判断ができるだろうかという心配がないわけではなかった。メディアをはじめ、さまざまな目に見えない圧力が働いただろうに、判事がそれらを跳ね返してくれて、本当にうれしかった。最終陳述で「韓国社会に正義が生きていることを見せてください」と言ったが、この訴えが受け入れられたわけだ」
Q:今回の判決の要旨は何か。
「メディアでは、「間違った意見であっても保護する価値がある」というのが判決の肝であると報道していたが、これは判決内容のすべてではない。正しくは、「正しい意見だけが保護されるなら、意見の競争は存在しえず、学術的意見が正しいか正しくないかを国家機関が決定しなければならない。これは、裁判所の領域を越えたこと」という内容がつけ加えられている。まったく正しい判断だ」
Q:裁判のプロセスはどのようなものだったか。
「昨年の1月から12月までのちょうど1年間に10回ほどの裁判が開かれた。周りの人はほとんどが否定的な話をしていたが、最終的に勝訴した。これは担当判事が合理的に進めてくれたことが大きかったと思う。準備段階で、判事が自らブリーフィングの資料を作り、プロジェクターに関連の内容を映しながら、「このような名誉毀損の基準に該当するかどうか、検討していく」と説明してくれた。こんなケースはほとんどないと聞いた」
(写真)
キャプション:『.帝国の慰安婦』筆禍事件で起訴された一審で無罪判決を受けた朴裕河教授に、7日、ソウル市チャヤン洞東部地裁で会った。朴教授はこの日のインタビューで「誤解」と述べた。多くの人からおかしな人とみなされて、笑こともできなかった、と語った。
Q:国民参加裁判を申請しなかったのか。
「最初、国民参加裁判をしようと思ったが、途中でやめた。そのころ、『帝国の慰安婦』の批判本がそれなりの出版社から発刊され、一般の人々の私に対する認識が悪くなったと考えた。新任の弁護士からも国民参加裁判をしないほうがいいだろうと言われたし」
Q:日本でも大きな話題になった。日本の反応は。
「ある本を読んで、その内容を伝えるときは、多かれ少なかれ歪曲があるものだ。伝えられる過程で、当事者の意図とずいぶん違ってくる。少し前に毎日新聞も私の本について報道していたが、少女像問題とつなげて書いていた。不本意だった。私自身が何も言及していない政治的なこと自分をつなげられると、まるで私がそのコラムの著者と同じ考えであるかのように見えるのではないか」
Q:最も辛かったことは。
「2013年の夏に本を出したときは、関連する学会と慰安婦支援団体などが、私の主張を検討した後で考えを少し変えてくれるのではないかと期待していた。けれども、そうした反応はまったくなかった。詳しく見れば、今回の事態の底辺には、進歩的知識人たちの間における葛藤が横たわっている。すでに9年前から、ある進歩的メディアに私に対する歪曲された批判が載り始めた。「朴裕河が言う和解とは、被害者を非難するものであり、日本の進歩的知識人たちが支持しているので、徹底的に抵抗すべきだ」という主張だった。韓国のリベラルな層の中に、私への不信を植えつける作業をしていたのだ。起訴後は、私を助けてくれる進歩的知識人までもが右傾化したというふうに攻撃した。私が日本のお金をもらったという文が掲載されたこともあった」
Q:ずいぶん大変だったようだ。
「鬱病に似た症状にずっと悩まされた。今も刺激されると涙が出る(一瞬、朴教授の目が潤み、彼女はしばらく言葉を詰まらせた)」
Q:支持してくれた人も少なくなかったと聞いた。
「私をもっとも擁護してくれたのは、おもに見ず知らずのフェイスブックの友人たちだった。彼らは私の他の本や翻訳書を読んだり、直感的に「そうじゃない」と考えたりした若い起業家など、さまざまな職業の人たちだった。こうしたありがたい存在のおかげで希望を持てた。問題は、考えることをしない圧倒的多数だ。今回のことをきっかけにして韓国社会の多くの問題を見ることができた」
朴教授は、今回無罪判決を受けたとはいえ、彼女の前途は依然として険しい。検察は一審宣告後直ちに控訴し、今後二審さらに最高裁の判決を待つことになる公算が大きい。それでも今回の無罪判決は、ずっしりとした重みがある。判決文に示されたように、学問の自由は広い範囲で保護されなければならないという原則が再確認されたからだ。『帝国の慰安婦』事件が最終的にどう決着がつくか、最後まで予断を許さない。
Q:慰安婦問題に関心を持ったきっかけは。
「私たちの共同体(韓国)では、社会的分裂が大きな問題だ。慰安婦問題に関心を持つようになったのは、子供の頃、いわゆる「ヤンコンジュ(洋公主=西洋のお姫様)」と呼ばれる米軍基地の女性たち関する本を読んだのがきっかけの1つかもしれない。私の最大の願いは、私たちの中の分裂を調和的、平和的に解決することだ。慰安婦問題についての研究も、自分の関心領域の中で葛藤に関わる事案を扱ったものにすぎない」
Q:慰安婦研究における最大の問題点は。
「今回の崔順実(チェ・スンシル)騒動に見られるように、韓国社会では、隠されてきた弊害が次々に表面化している。今回の『帝国の慰安婦』騒動もまた、韓国社会のある弊害が表面化したものと見るべきだ。慰安婦問題は、これまで20数年間にわたって論争になってきたのに、国内にはこれについての専門家とされる人が多くはない。それだけ、この問題についての研究が十分になされていないということだ」
メディアは、学者たちの議論に耳を傾けるべき
正しい判断のためには伝えることも重要だ
家族のために自ら行ったケースもあり
売春婦といって後ろ指をさすことはできない
Q:今回の事態で強く感じたことがあれば。
「メディアがいかに怠慢かを感じた。慰安婦支援団体が私を告発し、「朴教授が慰安婦ハルモニは自発的な売春婦で、被害者ではないと書いた」と主張した。事実ではないのにもかかわらず。けれども、これについて私に直接確認したメディアはほとんどなかった。連絡をしてきたメディアも、まともな記事を書かなかった。今なお私が辛く思っている理由の一つがまさにこれだ。いくら裁判で勝ったとしても、メディアが私のことを悪しざまに言い続ければ、どうやって名誉回復されるだろうか。今なお、私に対して批判的なメディアの態度はまったく変わっていない。判決の後、私の笑っている顔を変なやり方で編集して配信されたこともある」
Q:では何と書いたのか、自発的売春婦もいたはずだと書いたのか。
「違う。自発的売春婦と書いた人を批判するために引用したに過ぎない。もちろん、全体的に見たとき、自発的に行った人がいたということもありうるという点を書かなかったわけではない。慰安婦が戦場に行くことになったプロセスについて、これまでは強制連行という表現が使われてきた。これを根拠に国家が法的責任を負うべきだと要求したのだ。問題は、いったんこのように規定した後、一度も考え直すということをしなかったことだ」
Q:自ら行った慰安婦とは、どのような人なのか。
「自発的に行った人たちの中には、家族のために身を犠牲にしたケースが多かっただろう。私はこの点を強調したい。実は1996年に作成された国連の報告書の中にも売春の話が出てくる。このような包括的な話が、韓国には伝えられないでいる。かつての基準に合うものだけが伝えられてきたのだ。あの時代状況から、自発的な売春だとしても、誰も後ろ指をさすことはできないのは明らかだ。それなのに彼女たちを非難するとすれば、ありのままを見ようとしない態度のためだ。これついては男性たちの責任も大きい。知っているではないか。売春に対する男性たちの偏見がどのようなものかを。売春婦という表現にはすでに差別的な要素が込められている。こうした考え方のせいで慰安婦は少女でなければならないのだ」
Q:「学問の自由」をどのように考えるか。
「もちろん守られるべきだ。ただ、今回の事件は学問の自由ではなく事実関係の問題だと考えている。私を誹謗した学者たちは声明書を通じて、「学問の自由は守られるべきだが、他人の名誉を毀損してまでではない」と言った。それに対して私は名誉毀損をしたのではないと反論したのだ」
Q:では、慰安婦についての議論はどのように行うのが望ましいのか。
「学者間で議論をさせた後、メディアがこれに耳を傾け、きちんと伝えることが必要だ。慰安婦問題をめぐる論争が何なのか、そして誰が、どのようなことを言っているのか、国民が見て、判断できるようにするべきだ。20年前は、慰安婦は強制連行されたことになっていた。けれども長い間の研究が進み、人身売買が中心だったということが明らかになった。これはこの問題に関わっている学者なら誰もが知っている事実だ。それにもかかわらず慰安婦支援団体は、外部に真実を話さないでいる。私はそれを国民動員と述べた」
韓国人たちは自己主張が強すぎる
意見が違うといって退けてしまっては困る
国内の慰安婦研究はきわめて貧弱
資料を集め、研究書をまた出すつもり
Q:韓日問題にどう向き合うべきか。
「歴史をめぐって対立と葛藤は起こりうるが、明らかなファクト(事実)はあるはずだ。ただ、これをどのように見るべきかという観点は異なることがある。同一の事柄について、ある人は肯定的に、ある人は否定的にも見ることもあるが、それでもファクトはきちんと知るべきだ。問題は、韓国人の主張があまりにも硬直しているということだ。最初の主張にこだわれば無理が生じる」
Q:解決方法は。
「学者たちを密室に閉じ込めておくと、その中で権力化が起こる。それが原因で、出てくる声と出てこない声が生じる。もう和解して終わりにしようという意見もあるが、当事者の慰安婦ハルモニを含め、学者、支援団体がお互い話し合ったことにメディアが耳を傾け、それを社会の隅々に伝えるべきだ」
Q:今後の計画は。
「慰安婦問題については、この本以外に何かを書くつもりはなかった。けれども、この本を書いた後、私の主張を誤解して非難する人が依然として多いので、今回の本では使わなかった資料、そして裁判の後で知ったことも合わせて新しい本を出すつもりだ。」
Q:最後に言いたいことは。
「現在、私たちはこんなことをしている場合ではない。韓国は深刻な危機的状況だ。本当に孤立している。日本はもちろん台湾も私たちを嫌っている。米国、中国も好意的ではないのではないか。経済も悪いが政治的孤立が本当に深刻だ。分裂があまりにも激しく、意味のないことにエネルギーを浪費している。私たちは自己主張が強すぎる。良く言えば我が強いということだが、考え方があまりにも硬直しており、反対意見は抹殺し、退けるべきと考えている。これは決して望ましいことではない。ある問題について争うのはいいが、この国では、その過程で消耗するものが多すぎる。何もしていない人間に対し、2年半も精神的、肉体的、さらに金銭的にこんなふうに損害を与えるというのは、あまりにも無意味な消耗だ」
朴裕河教授とは…
ソウル生まれ。高校卒業後、日本に渡って慶応大学卒業後、早稲田大で文学博士号を得た。大江健三郎、柄谷行人など、日本の知識人の作品を翻訳、紹介してきた。民族主義を越えた韓日間の協力と東アジアの歴史的和解のための研究にも携わっている。2007年には日本の朝日新聞が社会科学分野の質の高い作品に授与される「大佛次郎論壇賞」を韓国人として初めて受賞した。現在世宗大日本文学科教授として在職中。
文:ナム・ジョンホ論説委員
写真:チョ・ムンギュ記者
Translated by H.H.
Original Article (in Korean) Link
判決に対するメディアの誤解について
(記事)『帝国の慰安婦』刑事訴訟に勝訴した理由 [HUFFPOST 2017.02.22]
『帝国の慰安婦』刑事訴訟に勝訴した理由
裁判所の判決文である以上、たとえ気に入らなかったとしてもありのままに伝えてこそ、記者として恥ずかしくないのではないですか。
[裁判関連] 『帝国の慰安婦』裁判、判決文(全文)
Translated by H.H.
ソウル東部地方裁判所
第11刑事部
判 決
事 件 2015コハプ329 名誉毀損
被 告 朴○○(57****-2******)、教授
住居 ソウル
登録基準地 ソウル
検 事 クォン・パンムン(起訴、公判)、イ・ユンヒ(公判)
弁 護 人 1.法務法人 ユジン
担当弁護士 キム・ヨンチャン
2.法務法人 エイチス
担当弁護士 ホン・セオク
判 決 宣 告 2017年1月25日
主 文
被告は無罪。
この判決の要旨を公示する。
理 由
公訴事実の要旨
告訴人のイ**、キム**、キム**、ユ**、カン**、チョン**、パク**、キム**、キム**、イ**、イ**は、日本軍慰安婦被害者らで、実際は日本国の売春婦とは異なり、本人たちの意思に反して日本軍によって慰安婦として強制動員され、その監視の下で戦時状況の中国、東南アジア等の地に設置された慰安所に閉じ込められ、最小限の人間らしい生活も保障されないまま、一日に数十人の軍人たちの相手をし、性的快楽の提供を強要された「性奴隷」にほかならず、本質的に売春婦ではなく、日本国と日本軍に愛国的または自矜的に協力したことはなく、日本軍は上記の通り設置された慰安所を設置・運営し、慰安婦を国外に送り出す過程で広範囲に介入する等の行為をした。
それにもかかわらず被告は、2013年8月12日、ソウル麻浦区西橋洞541-28にある「プリワイパリ(根と葉)」出版社から、「日本軍による朝鮮人慰安婦動員の非強制性を強調(日本軍の強制動員または強制連行を否定)し、朝鮮人慰安婦が基本的に売春の枠組みの中にある女性であるとか、自発的に行った売春婦であり、朝鮮人慰安婦が日本帝国の一員として日本国に対する愛国心または自矜心を持って日本人兵士たちを精神的・身体的に慰安する慰安婦として生活しながら、日本軍と同志的な関係にあったことを示し、「朝鮮人慰安婦の苦痛が日本人の娼妓の苦痛と基本的に変わらないという点をまず知る必要がある。」、「「慰安」は、過酷な食物連鎖構造の中で、実際にお金を稼ぐ者は少なかったが、基本的には収入が予想される労働であり、その意味では「強姦的売春」であった。または「売春的強姦」であった。」、「朝鮮人「慰安婦」を呼ぶ「チョーセン・ピー」という言葉には、朝鮮人に対する蔑視が露わである。この軍人たちが彼女たちをこうも簡単に強姦できたのは、彼女たちが「娼婦」だったからでもあるが、何よりも「朝鮮人」だったからである」、「1996年の時点で「慰安婦」とは根本的に「売春」の枠組みの中にあった女性たちであることを知っていたのである。」、「そして、「自発的に行った売春婦」というイメージをわれわれが否定してきたことも、やはりそのような欲望、記憶と無関係ではない。」、「日本人・朝鮮人・台湾人「慰安婦」の場合、「奴隷」的ではあっても基本的には軍人と「同志」的な関係を結んでいた。」、「それは朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係だったからである。」、「ホロコーストには、「朝鮮人慰安婦」が持つ矛盾、すなわち被害者でありながら協力者でもあったという二重の構図はない。」、「そのような精神的な「慰安」者としての役割――自分の存在に対する(やや無理な)矜持が、彼女たちが直面した過酷な生活に耐え抜くことのできる力にもなりえたということは、十分に想像できることである。」、「「朝鮮人慰安婦」は被害者であったが、植民地人としての協力者でもあった。」、「そして少なくとも「強制連行」という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはないという点。」、「「慰安婦」たちを「誘拐」し、「強制連行」したのは、少なくとも朝鮮の地では、そして公的には、日本軍ではなかった。」等、別紙犯罪一覧表に記載したように、虚偽の事実が摘示されている『帝国の慰安婦』という本(以下、「本件書籍」という)を出版し、その後、全国の書店等を通じて配布し、公然と被害者たちの名誉を毀損した。
判断
1.被告と弁護人らの主張
被告と弁護人らは次のように主張し、この事件の公訴事実を争っている。
○別紙犯罪一覧表に記載の各表現は、被告が自らの意見を表明したものに過ぎず、具体的な事実を摘示したものではなく、上の各表現は、検事が上の表の「備考」欄で主張しているような内容でもない。
○被告は、別紙犯罪一覧表に記載の各表現で、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の名称を使用したものであり、上の各表現は集団の構成員すべてを指摘している内容ではく、例外を認める一般的な平均判断に過ぎず、上の集団の構成員である告訴人らが被害者として特定されていたとはいえない。
○被告は、本件書籍において日本軍慰安婦の強制動員を認め、慰安所は強制売春の形態で、慰安婦が「性奴隷」であったことを認めており、日本国の責任を否定する否定論者たちを批判し、日本政府の責任を問おうとする意図で本件書籍を著述した。したがって、被告には名誉毀損の犯意がない。
○被告が本件書籍に叙述した内容は、さまざまな国際報告書と国内委員会の発刊資料等に叙述された内容と同一のもので、虚偽ではなく、被告は慰安婦問題の解決を望む気持ちから既存の国内慰安婦支援団体の運動と日本の否定論者たちを批判するために本件書籍を著述したもので、仮に被告が告訴人らの名誉を毀損する事実を摘示しているとしても、これは真実であり、公共の利益のためのものであるから、違法性が阻却される。
2.事実の摘示に当たるかどうか
カ.検事の主張
検事は、被告が別紙犯罪一覧表に記載の各表現のうち、①番号2~4、7、11~13、15、16、27、30、34に記載の各表現(以下、便宜上番号のみ記す)を通じ、「慰安婦は本質が売春だった」という事実、より具体的には「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、本人または両親の選択によって自発的に行ったので、その本質は売春だった」という事実を摘示しており(以下、「第一主張」という)、②番号1、6~10、13、14、17~19、21~25、28、29、31~33、35に記載の各表現を通じては、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは日本国または日本軍の愛国的または自矜的協力者で、日本軍と同志的関係にあった」という事実を摘示しており(以下、「第二主張」という)、③番号5、16、20、26に記載の各表現を通じては、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がなかった」という事実を摘示している(以下、「第三主張」という)と主張している。
ナ.被告と弁護人らの主張
これについて被告と弁護人らは、①被告が本件書籍で「売春」という単語を使用したのは、日本軍慰安所が「管理売春」の形態で運営されていたという点を説明するためであって、慰安婦たちが「自発的」な売春婦だったという意味で上の単語を使用したのではなく、②被告は朝鮮人日本軍慰安婦たちが植民地人として日本国によって協力と愛国を強要された「軍需品としての同志」だったと叙述したものであって、慰安婦たちが愛国心または自矜心を持って日本軍や日本国に協力したと叙述したのではなく、③被告は本件書籍で帝国主義、植民地支配、資本主義、家父長制等の社会構造的次元での強制性を意味する「構造的強制」という概念を通じて、直接的で物理的な強制連行のみを意味する「狭義の強制動員」と区別される「広義の強制動員」を主張しつつ、そのような広義の強制動員について日本が責任を負うと叙述しただけでなく、狭義の強制動員があったという事実も否定したことはなく、ただそのような狭義の強制動員が「公的に」日本軍によってなされたものではなかったと叙述しただけである、と主張している。
タ.関連法理
1)「事実の摘示」の概念
刑法第307条第2項の名誉毀損罪が成立するためには、問題となった表現が「事実の摘示」に該当しなければならない。ここで「事実の摘示」とは、価値判断や評価を内容とする意見表明に対置される概念で、時間的・空間的に具体的な過去または現在の事実関係に関する報告や陳述で、その表現内容が証拠によって証明可能なものをいう(最高裁2007年10月26日宣告2006ト5924判決等参照)。すなわち、「事実」とは、五感の働きで感知できる程度に現実化され、証拠により証明できる特定人の過去または現在の具体的事件または状態をいうものであり、「意見」は単純な事実と区別される価値判断で、事実関係や人に対して何らかの意識や見解を持ったり、評価したり、判断したり、態度を決定したりする等の、精神的活動の表現を意味する(最高裁2004年2月26日宣告99ト5190判決参照)。
また、摘示された事実は、これによって特定人の社会的価値や評価が侵害される可能性があるという程度にまで具体性を帯びていなければならない。特定人の社会的価値や評価を低下させるに十分な具体的事実の摘示があるというためには、必ずしもそのような具体的事実が直接的に明示されていることが要求されるわけではないが、少なくとも摘示された内容の中の特定の文句によって、そのような事実がただちに類推されうる程度になっていなければならない(最高裁2011年8月18日宣告2011ト6904判決等参照)。他人の社会的評価を侵害する可能性があるという程度にまで具体性がある事実を明示的に摘示した表現行為が名誉棄損になりうるのはもちろんであるが、意見ないし論評を表明する形式の表現行為だとしても、その全体的な趣旨に照らして、意見の根拠になる隠された基礎事実に対する主張が黙示的に含まれているうえに、その事実が他人の社会的評価を侵害しうるならば、名誉棄損に該当しうる(最高裁2015年9月10日宣告2013タ26432判決参照)。
2)事実の摘示に該当するかどうかを判断する方法
ある表現が事実を摘示しているものなのか、意見を表明しているものなのか、意見を表明していると同時に黙示的であれその前提になる事実を摘示しているものなのかを判断するためには、その表現の客観的内容と合わせて、一般読者が普通の注意深さでその文章に接することを前提として、使用された語彙の通常の意味と用法、証明可能性、問題となった言葉が使用された文脈、その表現が行われた社会的情況等、全体的情況を考慮して判断しなければならない(最高裁2011年9月2日宣告2010ト17237判決等参照)。
このように、論争になっている表現の客観的意味は、その言語的文脈およびその表現がなされた周辺の状況によって決定されるものであるため、たとえ表現内容の中の一部の趣旨がはっきりせず、誤解の余地があったり、ここに相手方に対する批判が加えられていたりしたとしても、その表現内容の中のほかの部分とともに全体的・客観的に把握することなく、趣旨のはっきりしない一部の内容だけを取り出して、名誉棄損的事実の摘示と断定してはならず(最高裁2008年5月8日宣告2006タ45275判決等参照)、さらに客観的な表現形式や内容等に照らして見るとき、これを事実の摘示ではなく、単純な意見表明と捉えることができるにもかかわらず、その文章が批判的な観点から作成された等の主観的な事情を考慮して、このような表現行為を名誉棄損に当たるものと断定することは許されない(最高裁2009年4月9日宣告2005タ65494判決参照)。したがって、ある表現が主体と行為を指摘していて、一見、意見または論評を表現すると同時にその前提になる事実を摘示したものと見える場合であっても、その表現の前後の文脈とその表現がなされた当時の状況を総合して見るとき、その表現が比喩的、想像的であり、多義的で、具体的内容、日時、場所、目的、方法等が特定されず、一般的に受け取られる核心的意味を捉えがたく、読者によって異なる見方をする余地がある等で、立場表明という要素が決定的であれば、その表現は事実の摘示と見ることはできず、意見の表明というべきである(最高裁2004年2月26日宣告99ト5190判決参照)。
ラ.第一主張に関する判断(順番2、3、4、7、11~13、15、16、27、30、34に記載の各表現)
1)検事が「摘示された事実」と主張する内容について
検事は、この部分の各表現が「慰安婦は本質が売春だった」という事実、より具体的には「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、本人または両親の選択によって自発的に行ったので、その本質は売春だった」という内容の事実を摘示したと主張している。しかし、いろいろな側面を持つ、ある対象の本質的要素が何であると見るかということは、必然的に主観的な評価が介入せざるをえない価値判断に属するものであり、その判断の当否を問うのならともかく、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。これは、検事がより具体化された形で提示した陳述が、「…なので、その本質は…だった」となっており、推論の文章口調をとっていることを見ても明らかである。したがって、被告が「慰安婦は本質が売春だった」という内容の叙述をしたという検事の主張は、その主張自体が事実の摘示ではなく、意見の表明を問題としているに過ぎない。
ただ、もし検事の主張のように、この部分の各表現が、明示的または黙示的に「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という内容を摘示したものであれば、これは時間的・空間的に特定の事実関係に関するもので、証拠によってその事実の存否を証明することが可能なので、事実の摘示に当たると見る余地がある。以下では、この部分の各表現がはたして検事が主張する上の内容のような事実を摘示したものと見ることができるかどうかを判断する。
2)番号2~4、11、30に記載の各表現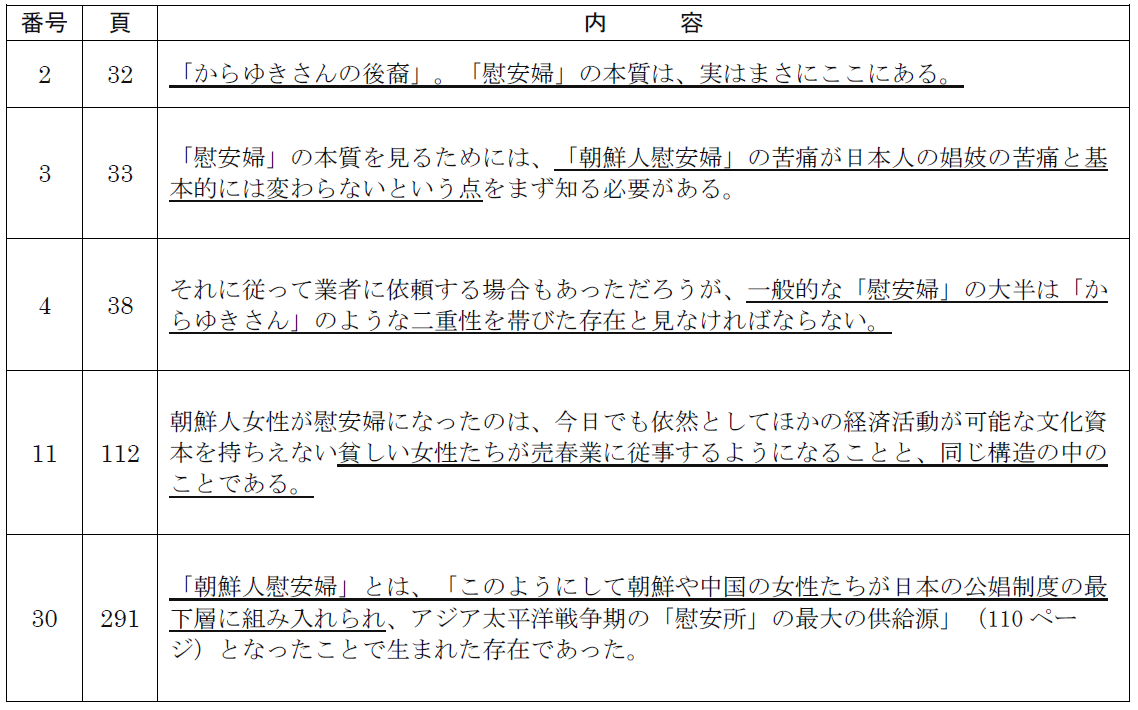
本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見るとき、この部分の各表現は意見の表明に該当するに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を摘示していると見ることはできない。
〇この部分の各表現の客観的な内容は、慰安婦の「本質」が何であるかを説明したり(番号2、3)、一般的な慰安婦の大多数には「二重性」という属性があると述べたり(番号4)、朝鮮人女性が慰安婦になった構造的・制度的次元の原因と起源を説明したりしている(番号11、30)ものである。ある現象の本質や属性が何であるかを明らかにすることは、主観的な評価が必然的に介入せざるをえない価値判断に属し、ある歴史的現象について、その背景になっている社会構造や制度との因果関係を明らかにすることもまた、主観的な分析と評価に伴う推論の性格を持つ。
〇被告は「からゆきさんの後裔」、「「からゆきさん」のような二重性を帯びた存在」、「構造の中のこと」等の抽象的・比喩的表現を使用し、「基本的には変わらない」、「それに従って…場合もあっただろうが、…見なければならない」と述べ、通常、主観的な判断や推測を表すときに使う表現を使用している。このような語彙の通常の用法と意味、文章の全体的な流れと文句のつながり方に照らして見るとき、この部分の各表現を通じて、時間的・空間的に特定可能な具体的事実関係をただちに推論するのは難しい。
〇この部分の各表現の前後の文脈と、本件書籍の全体的内容、すなわち△「日本では近代初期から幼い少女たちを誘拐まがいの方法で連れて行き外国へ売り渡すことが多かったが、その女性たちは韓国、中国をはじめとした外国に作られた公娼へ売られて行き、このような女性たちを故郷の人々が「からゆきさん」と呼んだ」という趣旨の記述(27~28頁)、△人々はからゆきさんを軍人になぞらえ「娘子軍」と呼ぶこともあったが、これは「国家の欲望実現のために動員された者たちが、いつのまにか国家の勢力拡張に役立つ存在として、「国家のための」役割をする者たちと認められるようになって(もちろん動員のための国家のレトリックに過ぎない)生まれた言葉だった。後の慰安婦たちもまた「娘子軍」と呼ばれ、「慰安婦」たちはそのようにして国家と男性による被害者でありながら、国家による「愛国者」の役割を担わなければならなかった者たちでもあった」という叙述(31頁)、△番号2に記載の表現の直後に出てくる「国家間「移動」がより容易になった近代に、経済・政治的勢力を拡張するために他国へ渡った男性たち(軍隊もその一つである)を現地につなぎとめておくために動員された者たちが「からゆきさん」だったのである」という叙述、△番号3に記載の表現の直後に続く、「その中に差別が存在していたのは事実だが、慰安婦の不幸を作ったのは、民族の要因よりもまず、貧しさと男性優越主義的家父長制と国家主義であった。」という叙述、△番号11に記載の表現の直前に出てくる「何よりも、性労働の加害者は女性を「教育」から排除し、経済的自立の機会を与えず、父親や兄がモノのように売ることができた時代、女性の所有権を男性が持っていた時代の、家父長制的国家だった。」という叙述(112頁)、△番号30に記載の表現の前に登場する、「慰安婦は日本の戦時にだけ存在したものではない。それよりずっと前から存在し、今も存在する。今の基地村女性たちもまた現代の「慰安婦」であり、軍隊が存在する所なら「慰安婦」はどこにでも存在した。」という叙述(290頁)、△そのほか「貧しい女性たちの海外移動を助長したのは、家父長制と国家主義だけではなく、何よりもまず自国の勢力を海外へ広げようとした帝国主義だった。」という叙述(278頁)、△「「慰安婦問題」は国家の問題であるだけでなく、より本質的には資本の問題である。…慰安所は表面的には近代の戦争遂行のためだけのものに見えるが、その本質はそのような「帝国主義」と、人間を搾取し利潤をあげようとする資本主義にある。」という叙述(279頁)、△「家父長制と資本主義により支えられてきた近代国民国家体制は、国家勢力を拡張したり維持したりするために軍隊を組織し、故郷を離れ「お国のために」働く彼らを「慰安」すべき女性たちの組織を維持してきた。その意味では、日露戦争の時代の日本人慰安婦も、太平洋戦争の時代の朝鮮人慰安婦も、解放後の韓国に駐屯することになった米軍のための慰安婦も、基本的にはすべで同じく国家(安保または経済)のためという名目で動員された被害者である。」という叙述(287頁)等に照らして見るとき、この部分の各表現で、被告は、日本軍慰安婦被害発生の根本的な原因が国家主義、帝国主義、家父長制、資本主義等の社会構造的側面にあると捉える立場を前提として、日本で「からゆきさん」と呼ばれていた人々と朝鮮人日本軍慰安婦は、どちらも国家の勢力拡張の過程で、社会の最下層にある貧しい女性たちが国家によって動員されたという側面において同一の点があり、今日貧しい女性たちが売春業に従事するようになることと、過去朝鮮人女性たちが日本軍慰安婦になったことには、どちらもこのような社会構造的原因があるという趣旨の主張をしているものと見られるに過ぎず、朝鮮人日本軍慰安婦たちが自発的に慰安婦になったという趣旨の主張をしているものとは見がたい。
〇被告がこの部分の各表現を通じて主張した「朝鮮人女性たちが日本軍慰安婦になったのは、国家主義、帝国主義、家父長制、資本主義等の社会構造が原因になった」という陳述は、時間的・空間的に特定される事実関係に関連するものでないだけでなく、こうした分析と評価は、その当否を問い、賛否の見解を提起することはできても、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。
3)番号7に記載の表現
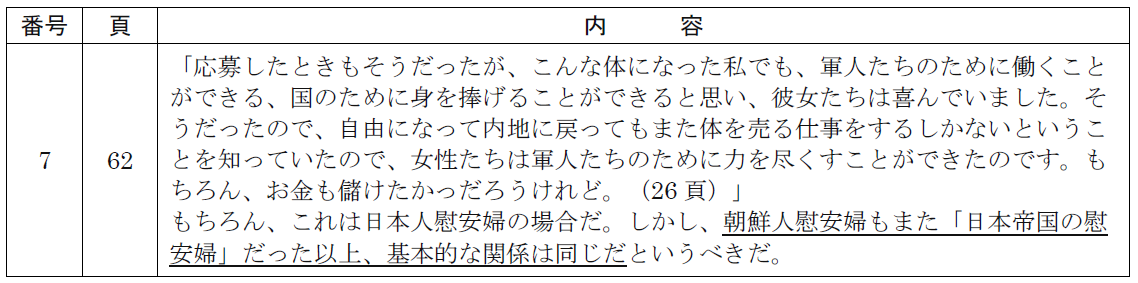 本件弁論と記録によって認められる次のような事情、すなわち、〇この部分の表現は、朝鮮人慰安婦は当時、日本人慰安婦たちが軍人たちのために働くという気持ちで慰安所で働いていたというある日本人業者の証言を引用した後、その証言に付け加えた陳述である点、〇この部分の表現は、被告が「軍人たちが戦争を遂行する間、それに必要ないくつかの補助作業をさせるために動員されたのが慰安婦であった。その意味でも、戦場で強姦の対象になった「敵の女」と慰安婦は、軍との関係において根本的に異なる存在であった。」(57頁)、「「朝鮮人慰安婦」は、そのように中国やインドネシアのような占領地/戦闘地の女性たちと区別される存在であった。植民地になった朝鮮と台湾の慰安婦たちは、どこまでも「準日本人」として帝国の一員であり(もちろん実際には決して「日本人」たりえない差別があった)、軍人たちの戦争遂行を助ける関係であった。それが「朝鮮人慰安婦」の基本的役割であった。」(60頁)、「慰安婦たちは当時「日本人」として動員された。…「朝鮮人慰安婦」とは、そのように日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員された存在でもあった。」(80頁)と叙述して、朝鮮人慰安婦は占領地または敵国の女性とは違う植民地人であり、日本帝国の一員として扱われていたために、日本軍との関係において占領地や敵国の女性と異なっていたことを強調する脈絡において登場する点、〇この部分の表現の直後に続く、「そうでなければ、敗戦前後に慰安婦たちが負傷兵を看護したり、洗濯や裁縫をしたりした背景を理解することはできない。」という叙述を見れば、被告がこの部分の表現で述べている「基本的な関係」とは、慰安婦が日本軍を助ける行為をすることもあったという現象を説明するためのものであることがわかる点、等に照らして見るとき、この部分の表現は「朝鮮人慰安婦も日本帝国の慰安婦であったので、軍人たちとの関係においては、上の証言に出てきた日本人慰安婦と基本的に同じである」という内容であり、下のマ1)項で見る通り、「慰安婦は日本帝国の一員として動員され、戦場で軍人たちを精神的・身体的に慰安する役割を果たすことを要求され、その意味で日本軍とは同志的関係と評価されうる」という意見を表明しているものと見ることができるに過ぎず、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を暗示している内容とは見がたい。
本件弁論と記録によって認められる次のような事情、すなわち、〇この部分の表現は、朝鮮人慰安婦は当時、日本人慰安婦たちが軍人たちのために働くという気持ちで慰安所で働いていたというある日本人業者の証言を引用した後、その証言に付け加えた陳述である点、〇この部分の表現は、被告が「軍人たちが戦争を遂行する間、それに必要ないくつかの補助作業をさせるために動員されたのが慰安婦であった。その意味でも、戦場で強姦の対象になった「敵の女」と慰安婦は、軍との関係において根本的に異なる存在であった。」(57頁)、「「朝鮮人慰安婦」は、そのように中国やインドネシアのような占領地/戦闘地の女性たちと区別される存在であった。植民地になった朝鮮と台湾の慰安婦たちは、どこまでも「準日本人」として帝国の一員であり(もちろん実際には決して「日本人」たりえない差別があった)、軍人たちの戦争遂行を助ける関係であった。それが「朝鮮人慰安婦」の基本的役割であった。」(60頁)、「慰安婦たちは当時「日本人」として動員された。…「朝鮮人慰安婦」とは、そのように日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員された存在でもあった。」(80頁)と叙述して、朝鮮人慰安婦は占領地または敵国の女性とは違う植民地人であり、日本帝国の一員として扱われていたために、日本軍との関係において占領地や敵国の女性と異なっていたことを強調する脈絡において登場する点、〇この部分の表現の直後に続く、「そうでなければ、敗戦前後に慰安婦たちが負傷兵を看護したり、洗濯や裁縫をしたりした背景を理解することはできない。」という叙述を見れば、被告がこの部分の表現で述べている「基本的な関係」とは、慰安婦が日本軍を助ける行為をすることもあったという現象を説明するためのものであることがわかる点、等に照らして見るとき、この部分の表現は「朝鮮人慰安婦も日本帝国の慰安婦であったので、軍人たちとの関係においては、上の証言に出てきた日本人慰安婦と基本的に同じである」という内容であり、下のマ1)項で見る通り、「慰安婦は日本帝国の一員として動員され、戦場で軍人たちを精神的・身体的に慰安する役割を果たすことを要求され、その意味で日本軍とは同志的関係と評価されうる」という意見を表明しているものと見ることができるに過ぎず、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を暗示している内容とは見がたい。
4)番号12に記載の表現
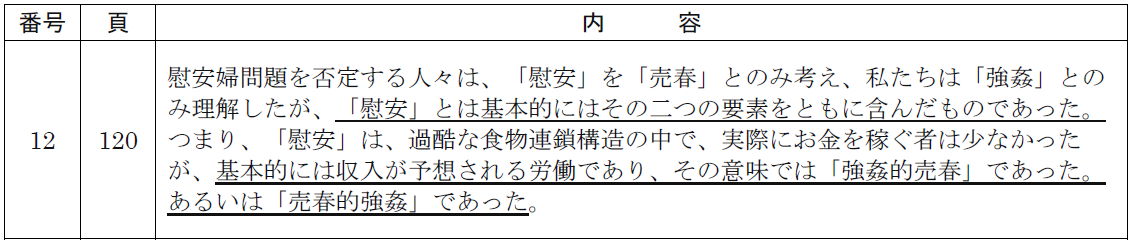
本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を摘示しているものと見ることはできない。
〇この部分の表現の客観的な内容は、「日本軍慰安婦には売春の要素と強姦の要素がともに存在している」というものである。このように、ある歴史的対象について、ある要素ないし属性が存在していると表明することは、主観的な評価が必然的に介入せざるをえない、価値判断に属する。
〇被告はこの部分の表現で、「基本的には」、「要素を含んだもの」、「強姦的売春」、「売春的強姦」、「その意味では」等、抽象的な語彙と比喩的表現を使用しており、その意味を一義的に確定しにくく、一般的に受けとれる核心的意味を捉えるのも難しい。
〇被告は、 △この部分の表現の前の部分(81~86頁)で日本軍が直接的・間接的に慰安所を管理していたが、これを直接運営したのは民間人業者たちまたは抱え主たちであり、これらの抱え主たちが慰安婦たちに性労働を強要していたと記述しつつ、性労働の対価については、「舎監は女性たちの借金の程度によって彼女たちの稼ぎの中から50~60パーセントの上前をはねた。」という米軍報告書の内容と、「お金を払えば主人たちがみな持っていくのよ」、「報酬はもらえず」という慰安婦たちの証言を直接引用しつつ、「慰安婦たちの中にはお金を稼いだ者もいるが、ほとんどはお金をもらえなかったそうだ。」と叙述し、「抱え主たちは幼い少女に無理やり性労働をさせ、労働の対価を搾取」したと書いている。△また、110頁では「日本軍による性暴力は、一回限りの強姦、拉致性(連続的)の性暴力、管理売春の三種類が存在した。「慰安婦」たちの場合、この三つの状況が少しずつ重なる場合もあるが、朝鮮人慰安婦のほとんどは、先に見た通り、三番目の場合が中心であった。」と叙述しているもので、それと同じく朝鮮人慰安婦の場合、ほとんどは「管理売春」に当たると主張しつつも、それもまた「日本軍による性暴力」に当たるという点を明示している。△そしてこの部分の表現より後の246頁では、国連人権委員会のいわゆる「クマラスワミ報告書」を引用しつつ、「そのようなクマラスワミでさえ「慰安婦」の状況を「強要された売春」と認識している。慰安婦たちを三種類――自発的な売春業、食堂や洗濯婦として行ったが「慰安」をさせられた場合、強制連行――に分類する等、「慰安婦」の姿が一つではなかったということも知っていた。1996年の時点で、「慰安婦」とは根本的に「売春」の枠組みの中にあった女性たちであるということを知っていたのだ。」と叙述している。
〇上のような複数の叙述内容を見れば、被告は慰安所の状況を、軍の管理下で抱え主たちが慰安婦たちに無理やり性労働をさせ、その対価は抱え主たちが搾取する「強要された売春」と認識しつつ、その形態(「枠組み」)が売春、すなわち性売買業だったことを指摘しているものと理解され、この部分の表現にも、このような前後の叙述とつながる「実際にお金を稼いだ者は少なかったが、基本的に収入が予想される労働であり、その意味では」という言い方が登場する点を考慮すれば、この部分の表現において被告が「売春の要素がある」と述べたことは、検事が主張するように、慰安婦が自発的に性売買に従事したことを意味するものというよりは、被告が主張するように、日本軍慰安所は管理売春の形態で運営されていたことを意味するものと見る余地が大きい。
5)番号13、15、27に記載の各表現
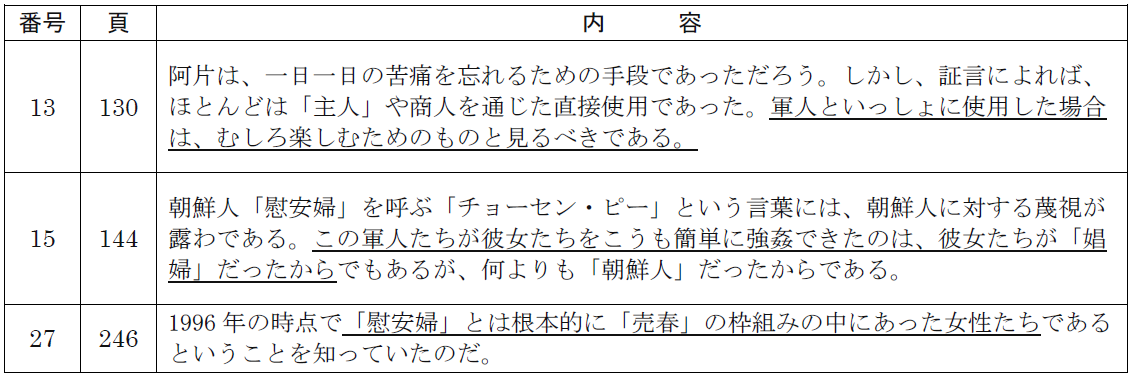
カ)関連法理
意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている場合、それとともに摘示された基礎事実そのものによって名誉棄損が成立しうることは別の議論として(最高裁2009年4月9日宣告2005タ65494判決等参照)、そのような基礎事実を根拠にして表明した意見部分は、いわゆる「純粋意見」であって、事実の摘示に当たると見ることはできず、名誉棄損は成立しえない(最高裁2001年1月19日宣告2000タ10208判決、最高裁2007月10月26日宣告2006ト5924判決等参照)。
ナ)具体的判断
番号13に記載の表現の場合、〇その前の部分で「慰安所で阿片の注射を打たれた慰安婦もおり、慰安所の運営者である「主人」が慰安婦に阿片注射を打ってやることもあった」という内容の証言、「私も一回打ってみたけれど、世の中が私のものになるの、こんなに気持ちいいなんて。…軍人たちがこっそり打ってくれたんだけど、いっしょに阿片を打って、アレをすればすごくいいんだって言いながら、女にも打ってやり、自分たちにも打って、そんなふうにしたのよ」という証言等、実際の慰安婦たちの証言をそのまま直接引用し後に登場する点、〇被告はこの部分の表現で、「証言によれば…であった。」、「…のものと見るべきである。」等、通常、推論と評価を意味する語彙と文句を使用している点、等に照らして見るとき、この部分の表現は、上のような内容の証言に表れた現象を根拠として、被告が「ほとんどの場合、慰安婦たちに阿片を直接無理やり注射したのは主人や商人たちであって、日本軍人ではなく、慰安婦が軍人といっしょに阿片を使用した場合は楽しむために使用したものだ」と、そのような現象に対する自分なりの分析と評価を提示しているもので、たとえそのような分析と評価に誤謬があるとしても、どこまでも意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、事実の摘示と見ることはできない。
また、番号15に記載の表現は、被告が、作家田村泰次郎が書いた「蝗(いなご)」という小説を紹介しつつ、その小説の中の朝鮮人慰安婦たちが日本軍によって列車で移送される途中、日本軍人たちが彼女たちを「チョーセン・ピー」と呼び、無理やり引きずり下ろして強姦する場面を描写した部分をそのまま引用した後に登場するもので、「チョーセン・ピーという言葉には…露わである。」、「この軍人たちが…強姦できたのは…だったからである。」として、その小説の中で使用された用語や登場人物たちを直接指し示しつつ、通常の用法上、主観的な推論と判断を表す語彙と文句を使用したものであり、この部分の表現は、被告が当該小説の中の場面に描写された日本軍人が、その描写されたものと同じ行為をするようになった理由について、自分なりの意見を提示している内容である。したがって、この部分の表現もまた、意見を表明しつつその意見のもとになる基礎資料まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、事実の摘示と見ることはできない。
番号27に記載の表現の場合も、先にラ4)項で見た通り、〇その直前の部分で1996年に出た国連人権委員会のいわゆる「クマラスワミ報告書」でも、日本軍慰安婦の状況を「強要された売春」と叙述しており、日本軍慰安婦の類型を単一のものとして捉えておらず、自発的な売春業、食堂や洗濯婦として行ったのに慰安婦になった場合、強制的に連行された場合の三つに分類したと述べ、クマラスワミ報告書の内容を紹介した後に登場する点、〇「根本的に」、「売春の枠組み」等抽象的で比喩的な語彙を使用した点、等に照らして見るとき、被告がクマラスワミ報告書の特定内容を根拠にして、それに関する自らの評価と分析を提示しているもので、意見を表明しつつその意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たる。したがって、被告がここで開陳した意見そのものが妥当であるかどうかは別問題として、被告がこの部分の表現を通じて事実を摘示したものと見ることはできない。
6)番号16、34に記載の各表現
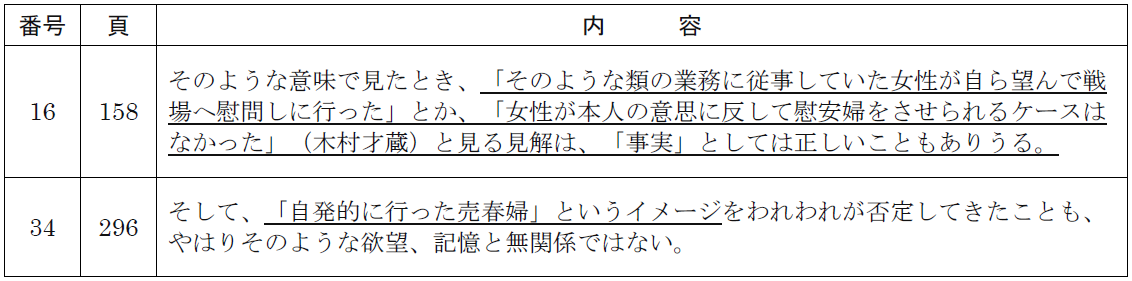
番号16に記載の表現は、「日本人の否定の心理と植民地認識」という表題の章で、被告が日本軍慰安婦問題を否定する日本の否定論者たちの見方に対する批判的な意見を開陳している文脈の中に登場する。上の表現で被告は、「そのような類の業務に従事していた女性が自ら望んで戦場へ慰問しに行った。」、「女性が本人の意思に反して慰安婦をさせられるケースはなかった」という、日本の否定論者木村才蔵の見解を直接引用した後、このような見解が「「事実」としては正しいこともありうる。」と述べ、その文章構造や語彙の通常の用法上、ほかの人の見解を別途明らかにした後、これについての自身の評価を叙述している意見表明の形式をとっている。そして番号34に記載の表現もまた、「イメージを否定してきたこと」、「欲望、記憶と無関係ではない。」という比喩的・抽象的な表現を使用しており、その文言自体からは、時間的・空間的に特定される具体的は事実関係を陳述しているのはどうか、はっきりしない。
しかし、被告は番号16に記載の表現の直前の段落で、「慰安婦の強制連行は、戦場で、朝鮮人女性ではなく敵国女性たちを対象にしてなされたものと見られる」という内容の叙述をしているが、これは証拠によってその存否の証明が可能な事実関係に該当する陳述であり、被告が引用した木村才蔵の主張の内容も「日本軍慰安婦は自らの意思にしたがって慰安婦になった、本人の意思に反して日本軍慰婦になった人はいない」というもので、証拠によってその存否の証明が可能な事実関係に当たる。また、被告もやはり「「事実」としては正しいこともありうる。」と述べ、このような木村才蔵の見解を事実関係の側面からは認めることができることを明示的に明らかにしており、直後に続く文章でも「明らかに彼女たちの中には、貧しさの中で「白いご飯」を夢見たり、女が勉強することを極端に嫌悪していた家父長社会から逃れ、一個の独立した主体たろうとしたりする者たちも多かった。」と述べて、時間的・空間的に特定可能な事実関係に関する陳述を付け加えている。このような点を総合的に考慮すれば、この部分の表現は、たとえ意見表明の形式をとっているとしても、そのような意見の前提になる具体的事実として「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見なければならない。それゆえ、この部分の表現は事実の摘示に該当する。
また、番号34に記載の表現は、被告が、これまで解放後の韓国社会では韓国民族を「完璧な被害者」としてのみ見ようとしており、日本の植民地支配に対する抵抗と闘争の記憶のみを持とうとしていたと主張しつつ、そのような態度を批判する脈絡(294~298頁)に登場するもので、被告はこの部分の表現の前の部分で、「「朝鮮人慰安婦」を、「日本軍」が直接「強制的に連れて行った」存在で、彼女たちを「監禁」したのも日本軍で、すべての軍人は暴悪で、すべての慰安婦は「純真な幼い少女」としてのみ見なすということは、そうした姿に見えないもう一つの慰安婦(いわゆる「売春婦」を含む)たちを排除することでもある。それはわれわれの、被害者像を薄めたくないという、被害者としての欲望がなせるわざであるが、表面的な姿が「完璧な被害者」として見えないからといって、彼女たちもまた被害者であり、犠牲者であった。」(295頁)と述べ、いわゆる「売春婦」を含む別の慰安婦たちの存在を認めるべきだという趣旨で叙述している。このような前後の文脈と合わせ、先に見た番号16に記載の表現の内容まで総合的に考慮すれば、この部分の表現は結局、「われわれは、韓国民族を被害者としてのみ見ようとする欲望と、日本の植民地支配に対する抵抗と闘争の記憶のゆえに、日本軍慰安婦の中には自発的に慰安婦になった人もいるにもかかわらず、「自発的な売春婦」というイメージを否定してきた。」という内容と見られ、したがって被告は、この部分の表現を通じても、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を、その表現の前提として暗示していると見なければならない。それゆえ、この部分の表現も事実の摘示に該当する。
ただ、その摘示された事実の具体的な内容に関して見ると、〇被告は番号16に記載の表現で、「正しいこともありうる。」と述べ、留保的な表現を使用している一方、その直後の文章で「彼女たちの中には…者たちも多かった。」と述べて、日本軍慰安婦の中の一部に関する陳述であることを明確にしている点、〇番号34に記載の表現の場合にも、上で見た「そのような姿に見えない別の慰安婦(いわゆる「売春婦」を含む)たち」という叙述に見られるように、その脈絡上、いろいろな姿の慰安婦の中の一部を指すものであることがわかる点、〇さらに被告は、本件書籍全体に渡って「日本軍慰安婦たちは多様な姿で存在し、ある一つの姿だけで全体を説明することはできない」という趣旨の叙述を繰り返し〔たとえば、「「慰安婦」は実際決して一つで説明しうる存在ではない。それにもかかわらずこれまでわれわれは「慰安婦」に関して一つのイメージだけを思い浮かべてきた。」(6頁)、「「慰安婦」たちが慰安婦になるまでの情況は、このように一つではなかった。」(54頁)、「「慰安婦」の状況――「慰安所」に行くまでの状況と慰安所での状況が一つではなかったように、「日本軍」もまた一つではなかった。」(70頁)等〕述べている点、等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現が、「すべての朝鮮人慰安婦たちが自発的に慰安婦になった」という事実を、黙示的にであれ摘示していると見ることはできず、ただ「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実、すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦の中の一部は、自発的な意思にしたがって慰安婦になった」という事実を摘示しているものと認めることができるに過ぎない。
マ.第二主張に関する判断(番号1、6~10、13、14、17~19、21~25、28、29、31~33、35に記載の各表現)
1)番号1、6~10に記載の各表現
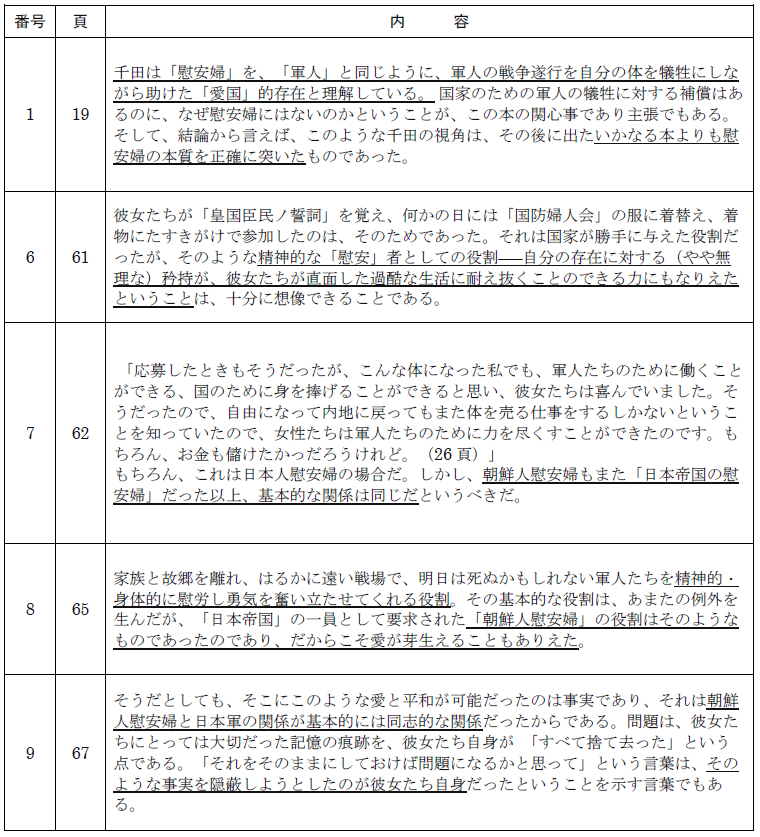
本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にであれ、「朝鮮人日本軍慰安婦たちが、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。
〇番号1に記載の表現は、千田夏光が書いた『声なき女性8万人の告発、従軍慰安婦』という本に表れている認識と主張を紹介した後、そのような千田夏光の見方について「慰安婦の本質を正確に突いたもの」と叙述している内容で、その表現の文言口調上、千田夏光の本に関する被告の主観的な論評に当たる。被告はこの部分の表現で千田夏光の見方を受け入れ、肯定的に評価しているので、結果的に自身の紹介した千田夏光の見方と同じ内容の表現、すなわち「慰安婦の本質は、軍人と同じように戦争遂行を自らの体を犠牲にして助けた「愛国」した存在だ。」という表現をとったものと見ることができ、上のような表現もまた時間的・空間的に特定できる事実関係に関する陳述ではないだけでなく、さまざまな側面を持ったある対象の本質的要素を何と見るかということは、典型的に主観的な価値判断の領域に属するもので、証拠によってその存否を証明することは不可能である。
〇番号6から10までに記載の各表現は、慰安婦の生活をしている間に看護員の役割をしたこともあり、着物を着て演芸会をし、軍事訓練を受けることもあったという証言、軍人たちと故郷の話をしたこともあったという証言、日本人慰安婦たちが「私も国のために身を捧げることができる」と思ったという日本人業者の証言、軍人たちを労ってやったこともあり、軍人たちから「愛している」、「結婚しよう」と言われたこともあるという慰安婦の証言、戦争が終わった後日本に来て、戦争犯罪人を収容する所に行くことになったという慰安婦の証言、等を直接引用した後に登場するもので、使用された語彙の通常の用法と意味その文章口調上、そのような証言に表れた現象をもとにして、それと同じ現象が発生しえた原因についての、自分なりの分析や推測を提示している内容である。これは被告が意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている、いわゆる「純粋意見」に当たり、被告が根拠として摘示した基礎事実の存否、そこから被告が主張している意見を導き出すことが妥当かどうかは別問題として、上のラ5)項で見たのと同じ理由で、この部分の各表現を事実の摘示と見ることはできない。
〇先に見た通り、被告は本件書籍において、日本軍慰安婦被害発生の根本的原因は国家主義と帝国主義、家父長制と資本主義等の社会構造的側面にあるという基本的立場をとりながら、当時朝鮮は日本の植民地であったために、植民地人として日本帝国主義の一員となり日本の戦争遂行のための役割を担った朝鮮人慰安婦たちは、日本軍と戦争をした敵国の女性たちと、日本軍に対する関係において違いがあったという点を強調している。とはいえ、被告はこのような朝鮮人慰安婦の戦争遂行のための役割担当について、「それは国家が勝手に与えた役割」(番号6)、「「日本帝国」の一員として要求された「朝鮮人慰安婦」の役割」(番号8)、「彼女たちに与えられた公的な役割」(137頁)と表現している一方、朝鮮人慰安婦については、「日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員され存在」(80頁)、「過酷な性労働を強要された「被害者」」(番号10)、「日本の「植民地」になった「半島」出身「日本」女性――「帝国治下の国民」の資格で軍人に対する性の提供を要求された存在」(111頁)と規定し、そのような戦争遂行の役割は日本帝国によって一方的に与えられたという趣旨で叙述している。また、慰安婦たちの「矜持」や「愛国」に関しても、「自己存在に対する(多少無理な)矜持」(番号6)というように、留保的・制限的表現を使用したり、慰安婦が「自身を売るために積極的に」行動した場合があったとしても、「その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生きるために自らに与えたトリック(ごまかし)だったということもありうる。」(160頁)と叙述したり、「目の前に与えられた「嘘の愛国」と「慰安」に没頭することは、彼女たちにとっては一つの選択でもありえたという事実を無視することはできない。」(62頁)、彼女たちの性の提供は、基本的には日本帝国に対する「愛国」の意味を帯びていた。もちろんそれは、男性と国家の女性搾取を隠蔽するレトリックに過ぎなかったが、…」(137頁)と叙述し、「自らに与えたトリック(ごまかし)」、「嘘の愛国」、「搾取を隠蔽するレトリック」等と表現している。このような本件書籍の全体的な内容を考慮すれば、この部分の各表現は、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在で、そのような意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」と、被告が自分なりに社会構造的次元の分析と評価を提示したり、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた、軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持っていたこともありうる」と、主観的な推測を提示したりしている内容に見えるに過ぎず、朝鮮人日本軍慰安婦たちが、実際に日本国に対して、自矜心と愛国心を持って、日本軍に協力したという事実を、明示的または黙示的に摘示したとは認めがたい。
2)番号13に記載の表現
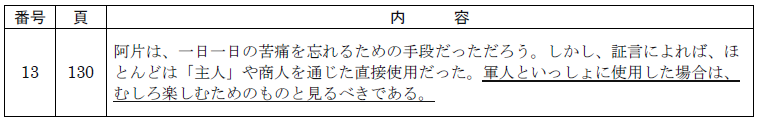
上のラ5)項で見た通り、この部分の表現は慰安授たちの証言を直接引用した後、それについて論評を記述したもので、意見を表明しつつその意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、具体的な事実を摘示していると見ることはできない。
3)番号14、19、21ないし25、28、29、31、32、33、35に記載の各表現
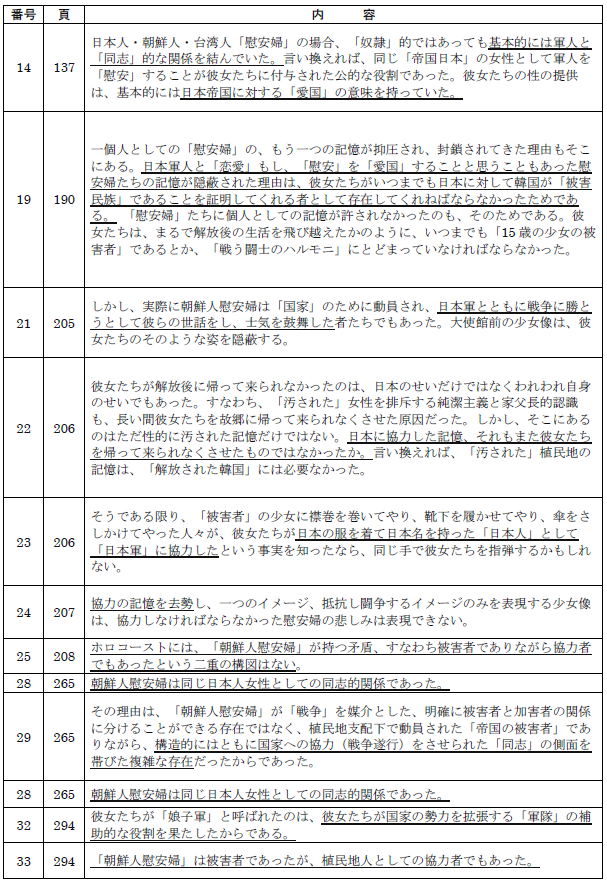
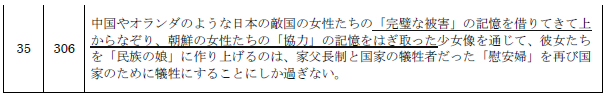 本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は、上のマ1)項で見たものと同じく、慰安婦たちの複数の証言をもとにして、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」という、被告の自分なりの分析と評価を提示したものの延長線で、同一の分析と評価を繰り返し叙述したもので、意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示しているものと見ることはできない。
本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は、上のマ1)項で見たものと同じく、慰安婦たちの複数の証言をもとにして、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」という、被告の自分なりの分析と評価を提示したものの延長線で、同一の分析と評価を繰り返し叙述したもので、意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示しているものと見ることはできない。
〇この部分の各表現は「基本的には」、「同志的な関係」、「意味を帯びていた。」、「構造的には」、「「同志」の側面を帯びた複雑な存在」、「「準軍人」のような存在」、「被害者でありながら協力者という二重の構図」、「植民地人としての協力者」のように、時間的・空間的に特定される事実関係をたやすく推論しにくい抽象的・比喩的語彙を使用し、通常、ある対象に対する価値判断と評価を表すときに使用する文章口調をとっている。
〇上のマ1)項で見たものと同じく、被告は本件書籍において帝国主義と国家主義等の社会構造的側面が日本軍慰安婦被害の根本原因になったという基本的立場を前提にして、植民地人だった朝鮮人女性は敵国の女性と異なり、日本軍人と同じように日本帝国の戦争遂行のために動員され、戦争遂行のための役割を担ったと分析している。しかし、先に見た通り、本件書籍で被告は、国家により慰安婦たちにこのような役割が一方的に与えられたものと叙述しており、「愛国心」や「自矜心」もまた本物ではないという趣旨で叙述している。このような趣旨は、この部分の各表現の文言とその前後の文脈、特に、△番号14に記載の表現にすぐに続けて、「もちろんそれは、男性と国家の女性搾取を隠蔽するレトリックに過ぎなかったが、「日本」軍人だけを慰安婦の加害者と特殊化することは、そのような部分を見えなくさせる。」(137頁)という叙述が出てくる点、△番号21、22、23に記載の各表現の後には、「「朝鮮人慰安婦」とは、朝鮮人日本軍と同じように、抵抗したが屈服し協力した植民地の悲しみと屈辱を一身に経験した存在である。「日本」が主体になった戦争に「引っ張られて」行っただけでなく、軍が行くあらゆる所に「引っ張り」回されなければならなかった「奴隷」であることは明らかだが、同時に性を提供し、看護し、戦場に出る兵士に向かって「生きて帰って」と言った、同志でもあった。…言い換えれば、朝鮮人日本軍と同じように「植民地の矛盾」を最も凄絶に生き抜いた存在であった。」(207頁)と述べ、朝鮮人慰安婦たちが植民地支配に抵抗したが屈服し協力せざるをえなかったという趣旨で叙述し、同じような趣旨で、番号24に記載の表現でも、「協力しなければならなかった「慰安婦」の悲しみ」に言及している点、△番号28、29に記載の各表現は、慰安婦たちはその出身国によってそれぞれ直面した状況が違い、特に朝鮮人女性は植民地人だったという点で、戦争の相手である敵国女性や占領地の女性と異なると主張している部分(264~265頁)に登場する点、△番号33に記載の表現の直後に続けて、「それは彼女たちが望もうが望むまいが、朝鮮が植民地になった瞬間から取り払うことのできなくなった矛盾であった。」という叙述が出てくる点、等を通じても表れている。
4)番号17、18に記載の各表現
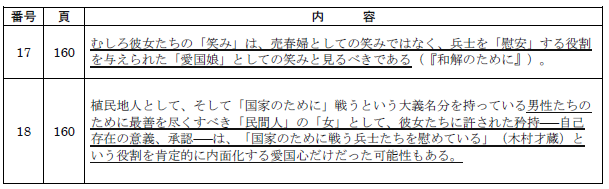 この部分の各表現は、〇「日本軍慰安婦たちが兵士たちに近づいて積極的な姿を見せ、明るく楽しげな姿を見せることもあった」という皮相的観察を根拠に、日本軍慰安婦が性奴隷だったことを否定する日本の否定論者の見解を紹介した後、被告がこれについて反駁する文脈の中で登場する点、○被告が「見るべきだ」、「に過ぎなかった可能性もある」と述べ、通常の意味と用法上、主観的な価値判断と評価や推測を表す語彙を使用している点、〇先に見たような、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈、特にこの部分の各表現のすぐ前に登場する、「抱え主たちの徹底した監視の中で、自らの意思では引き返す道がないということを知った慰安婦たちが(もちろんその中には契約期間の満了によって帰った者たちもいる)、時間が経過し、最初に着いたときの当惑と悲しみと怒りが消え、「自身を売るために積極的に」行動するようになったとしても、おかしなことではない。その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生き抜くために自らに与えられたトリック(ごまかし)だった可能性がある。」という叙述内容等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現は、前に出てくる番号6に記載の表現で、慰安婦の証言をもとにして、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持つこともありうる」と主観的な推測を提示したことの延長線で、それと同一の推測ないし評価を繰り返して叙述したものと見るべきである。したがって、この部分の各表現は、意見の表明に当たり、黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持ち、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。
この部分の各表現は、〇「日本軍慰安婦たちが兵士たちに近づいて積極的な姿を見せ、明るく楽しげな姿を見せることもあった」という皮相的観察を根拠に、日本軍慰安婦が性奴隷だったことを否定する日本の否定論者の見解を紹介した後、被告がこれについて反駁する文脈の中で登場する点、○被告が「見るべきだ」、「に過ぎなかった可能性もある」と述べ、通常の意味と用法上、主観的な価値判断と評価や推測を表す語彙を使用している点、〇先に見たような、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈、特にこの部分の各表現のすぐ前に登場する、「抱え主たちの徹底した監視の中で、自らの意思では引き返す道がないということを知った慰安婦たちが(もちろんその中には契約期間の満了によって帰った者たちもいる)、時間が経過し、最初に着いたときの当惑と悲しみと怒りが消え、「自身を売るために積極的に」行動するようになったとしても、おかしなことではない。その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生き抜くために自らに与えられたトリック(ごまかし)だった可能性がある。」という叙述内容等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現は、前に出てくる番号6に記載の表現で、慰安婦の証言をもとにして、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持つこともありうる」と主観的な推測を提示したことの延長線で、それと同一の推測ないし評価を繰り返して叙述したものと見るべきである。したがって、この部分の各表現は、意見の表明に当たり、黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持ち、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。
バ.第三主張に関する判断(番号5、16、20、26記載の各表現)
1)番号5、20、26に記載の各表現
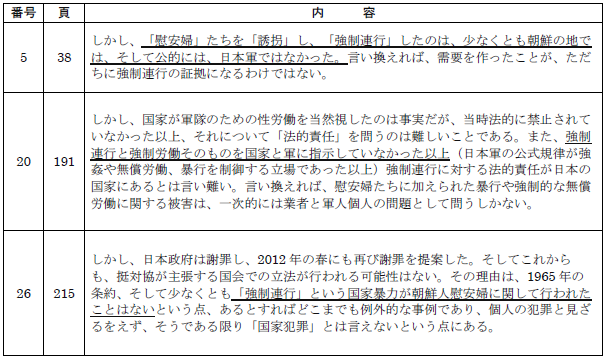 この部分の各表現は、使用されている語彙の通常の意味と用法、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を総合的に見るとき、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という内容を明示している。このような内容は、時間的・空間的に特定される事実関係で、証拠によってその存否の証明が可能である。したがって、この部分の表現は、事実の摘示に当たる。
この部分の各表現は、使用されている語彙の通常の意味と用法、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を総合的に見るとき、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という内容を明示している。このような内容は、時間的・空間的に特定される事実関係で、証拠によってその存否の証明が可能である。したがって、この部分の表現は、事実の摘示に当たる。
ただ、その摘示された事実の具体的な内容に関して見ると、〇「公的には」(番号5)、「公式規律」(番号20)、「あるとすればどこまでも例外的な事例であり、個人の犯罪と見ざるをえず、そうである限り「国家犯罪」とは言えない。」(番号26)という表現を使用した点、〇番号5に記載の表現のすぐ前の文章に「もちろん軍人や憲兵により連れて行かれた事例もないわけではなかったと見られ、個別的に強姦された事例も少なくなかった。」という叙述が登場する点、〇そのほかに、本件書籍のほかの部分でも、「強制連行があったとすれば、国家政策によるものではなく、国家政策のように見せかけて連れて行った、一般人が行なった行為と見るべきである。」(48~49頁)、「軍が物理的に行使した「強制連行」を文字通り「強制」「連行」と考えれば、その意味での「強制連行」が朝鮮人を対象に行われた事例は多くないように見える。…植民地で無差別的「強制連行」はなかったものと見られるが、それはどこまでもそのような行為を「有法化しても問題にならない、非日常的空間ではなかったために過ぎない。」(152頁)等、軍人による物理的強制連行があったという事実は一部認めながらも、法令や指示等国家政策によってなされたことはなかったという内容の叙述がある点を考慮すれば、被告がこの部分の各表現を通じて、日本軍が朝鮮人日本軍慰安婦を強制的に連行した事実が「まったく」ないという事実を摘示したものと見ることは難しく、上で見た通り、日本国または日本軍が「公式的な政策を通じて」朝鮮人女性たちを「物理的に」強制連行して慰安婦にしたことはないという事実を摘示したものと認められるに過ぎない。
2)番号16に記載の表現
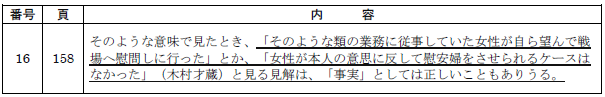 この部分の表現は先に見たものと同じく、たとえ文言そのものは意見を表明する形をとっているとしても、前後の文脈に照らして見れば、そのような意見の前提になる具体的事実として、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、日本国または日本軍によって強制動員または強制連行されたのではなく、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見ることができる。しかし、先に見た通り、この部分の表現に使用されている語彙と前後の文脈、本件書籍の全体的な内容に照らして見るとき、被告がこの部分の表現を通じて、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がまったくなかった」という事実、すなわち「すべての朝鮮人日本軍慰安婦たちは、自発的に慰安婦になった」という事実まで暗示しているものと見るのは難しい。
この部分の表現は先に見たものと同じく、たとえ文言そのものは意見を表明する形をとっているとしても、前後の文脈に照らして見れば、そのような意見の前提になる具体的事実として、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、日本国または日本軍によって強制動員または強制連行されたのではなく、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見ることができる。しかし、先に見た通り、この部分の表現に使用されている語彙と前後の文脈、本件書籍の全体的な内容に照らして見るとき、被告がこの部分の表現を通じて、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がまったくなかった」という事実、すなわち「すべての朝鮮人日本軍慰安婦たちは、自発的に慰安婦になった」という事実まで暗示しているものと見るのは難しい。
サ.小結論
結局、被告は本件書籍に記載された番号16、34記載の各表現を通じ、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示し、番号5、20、26に記載の各表現を通じて、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という事実を摘示したと認めることができる。しかし、残りの番号に記載の各表現の場合は、被告が自身の意見を表明したものであるに過ぎず、具体的な事実を摘示したものと見ることはできず、ほかにその点を認める証拠がない。
3.名誉棄損的事実の摘示に当たるかどうか
カ.関連法理
ある表現が事実の摘示に当たるとしても、その摘示された事実が特定人の社会的価値や評価を低下させる内容でなければ、名誉棄損罪は成立しない(最高裁2007年6月15日宣告2004ト4573判決等参照)。
ナ.判断
告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちが持っている、被害者としての社会的価値や評価の核心は、彼女たちが自身の意思に反して日本軍慰安所で性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要されたということにある。彼女たちが直接的な暴行・脅迫によって強制的に連行され慰安婦になったか、さもなければ学校に行かせてやるとか、就職させてやる等の欺瞞・誘惑によって慰安婦になったかは、彼女たちの慰安婦被害者としての社会的価値や評価にいかなる影響も及ぼさず(わが国の刑法は第287ないし第296条の2で暴行・脅迫を要件とする略取罪と欺瞞・誘拐を要件とする誘引罪に関して、原則的に同等の法的評価をしている)、そのような強制連行または欺瞞・誘惑行為を行なった主体が日本軍人であるか、さもなければ民間人の抱え主や業者だったかもまた、彼女たちの社会的価値や評価に影響を及ぼしえない。さらに、日本国や日本軍が強制連行の方法で慰安婦を動員することを公式的な政策として指示したか、さもなければただ個別の軍人の個人的逸脱行為として強制連行が発生したかも、同じように慰安婦被害者としての社会的価値や評価に影響を及ぼさない。
先に見た通り、番号5、20、26に記載の各表現で摘示された内容は、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」というものである。被告は本件書籍の複数の個所で、たとえ「例外的は事例」に過ぎない「個人的次元の犯罪」と捉えていたとしても、日本軍人によって物理的に強制連行され、日本軍慰安婦になった人もいるという事実を認め、たとえ行為の直接的な主体はほとんどの場合日本軍人ではなく、民間人の仲介業者や抱え主たちだったことを強調しているとしても、慰安婦の募集過程で、工場に就職させてやる等の嘘によって女性たちをおびき出した後、売り渡すという詐欺的手法と、人身売買があったという点、および慰安婦たちが慰安所で監視を受け、暴行等過酷な行為を受けたという点も複数の証言を直接引用しつつ叙述している。このような本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を考慮すれば、番号5、20、26に記載の各表現は、「公式的な政策」があるかどうかに焦点を合わせて、「朝鮮人女性たちを強制的に連行し、慰安婦にしたことが、日本国や日本軍の公式的な政策ではなかった」と叙述する内容で、日本軍慰安婦被害者たちの社会的価値や評価を侵害する内容ということはできない。
しかし、番号16、34に記載の各表現は、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人もいる」という内容で、これは直接的な暴行・脅迫によって強制的に連行され、慰安婦になった人または慰安婦になるということを知らずに欺瞞・誘惑の方法で誘引され、慰安婦になった人々については、その社会的価値や評価を低下させる表現に当たる。もちろん日本軍慰安婦被害者の被害者としての地位は、当初慰安婦になる過程での強制性、すなわち自発的慰安婦になったか、さもなければ意思に反して慰安婦になったかだけにかかっているのではない。たとえ最初に慰安婦になる過程で、自発的に募集に応じて慰安所へ行くことになった人だとしても、慰安所内で移動の自由や性的意思決定の自由を奪われたまま性的虐待を受けたならば、同じように日本軍慰安婦被害者に該当するという点は、疑問の余地がない[被告も本件書籍で「戦場の「慰安婦」たちが「もともと売春婦」だったのかどうかは、その点で重要ではない。」(148頁)と、同じ趣旨の指摘をしている]。しかし、韓国社会で日本軍慰安婦たちがどのような経緯で動員され、慰安婦になったかという問題は、従来日本の否定論者たちが直接的な暴行・脅迫による物理的強制連行の有無を重点的に問題視してきたために、重要な問題として取り上げられ、議論がなされてきた。その意味で、もしある慰安婦被害者が自発的な意思で慰安婦になったという事実が知られれば、これはその慰安婦被害者の社会的価値と評価を低下させると見るべきである。
タ.小結論
結局、番号5、20、26に記載の各表現は、日本軍慰安婦被害者たちの社会的価値や評価を低下させる内容ではなく、名誉棄損的事実の摘示ということはできず、そのほかにその点を認める証拠がなく、番号16、34記載の各表現は、彼女たちの社会的価値と評価を低下させうる名誉棄損的事実の摘示に該当する。
4.被害者が特定できるかどうか
カ.関連法理
刑法上、名誉棄損罪を処罰するのは、人の社会的価値に対する評価である外部的名誉という個人的法益を保護するためのもので(最高裁2016年12月27日宣告2014ト15290判決参照)、名誉棄損罪はある特定の人または人格を保有する団体に対して、名誉を毀損することで成立するものであるため、その被害者は特定されていなければならず、「ソウル市民」や「京畿道民」のような漠然とした表現によっては、原則的に名誉棄損罪は成立しえない(最高裁2000年10月10日宣告99ト5407判決参照)。
特定の人や団体を指し示すことなく、集合的名称を使用して名誉棄損的事実を摘示した、いわゆる「集団表示による名誉棄損」は、名誉棄損の内容がその集団に属している特定人に対するものであると解釈しにくく、集団表示による非難が個別構成員に至ると非難の程度が薄まり、構成員個々人の社会的評価に影響を及ぼすほどに至らない場合には、構成員個々人に対する冒涜が成立しないと見るのが原則であり、その非難の程度が薄まらず、構成員個々人の社会的評価を低下させるだけのものと評価される場合は、例外的に構成員個々人に対する名誉棄損が成立しうる。一方、構成員個々人に対するものとみなされるほどに構成員の数が少ないとか、当時の周囲の情況等から見て集団内の個別構成員を指し示すものとみなされうるときは、集団内の個別構成員が被害者として特定されると見るべきであり、その具体的な基準としては、集団の大きさ、集団の性格、集団内での被害者の地位等を挙げることができる(最高裁2014年3月27日宣告2011ト15631判決参照)。
ナ.判断
先に見た通り、被告は番号16、34に記載の各表現を通じて、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という名誉棄損的事実を摘示したと認められる。これは特定人を指し示さないまま、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の名称だけを示した表現で、次のような理由で、上の集団に属する特定の人々である告訴人らを指し示すものと見るのは難しく、集団内の個別構成員である告訴人たちに至っては、非難の程度が薄まり、告訴人個々人の社会的評価に影響を及ぼす程度にまで至っていないと判断される。
〇被告がこの部分各表現を通じて指し示した集団は、歴史的に存在した「朝鮮人日本軍慰安婦」全体である。被告は、たとえ「「慰安婦」が存在した国家は日本、台湾、韓国、フィリピン、インドネシア、オランダの6か国およびその地域である。…「オランダ」女性、インドネシア女性と、朝鮮人女性は、日本軍との基本的な関係が異なる。」(264~265頁)という表現からわかるように、本件書籍において「慰安婦」という用語を朝鮮人女性に限定しておらず、出身国に関係のない日本軍慰安婦全体を指す意味で使用することもあったが、番号16に記載の表現は、その直前の部分で「慰安婦の強制連行は戦場でのみ行われ、インドネシアでの強制連行は朝鮮人女性とは異なる事例である」という内容を叙述した後に登場し、番号34に記載の表現の場合、被告が「解放後の韓国では朝鮮人慰安婦に対する、一方の側面だけを記憶しようとしている」と主張しつつ、これを批判する脈絡で登場するという点から、前後の文脈上、日本軍慰安婦のうち出身国が朝鮮人だった人、すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦」を指していることは明白である。この部分の各表現に使用されている語彙、前後の文脈、本件書籍の全体的な内容等をすべて考慮しても、被告がこの部分の各表現を通じて、歴史的に存在した「朝鮮人日本人慰安婦」のうち特定の範囲の一部の集団、特に告訴人らが属した集団である「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業等に関する法律(以下「慰安婦被害者法」という)によって日本軍慰安婦被害者として登録した人々」や、「上のように登録した人々のうち現在生存している人々」という下位集団を指し示しているものと見る根拠はない。
〇歴史的に存在した日本軍慰安婦の全体の規模は、資料の限界によって、正確に把握することはできないが、研究者によって、多く見れば40万人から、少なく見れば3万人まで、多様な推算値を提示している。そしてこのような日本軍慰安婦全体の中で、朝鮮人が占める比率もまた正確に把握することはできないが、研究者たちは50%以上、多く見積もれば80%ほどと推算している。このような推算に従えば、歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦の規模は、いくら少なく見積もっても1万5000人以上であり、多く見れば32万人に達するもので、被告が「朝鮮人日本軍慰安婦」全体について述べたこの部分の各表現が、慰安婦個々人に対する社会的評価に影響を及ぼしうると見るには、「朝鮮人日本軍慰安婦」集団の構成員数が非常に多い。
〇このような朝鮮人日本軍慰安婦全体の中で、慰安婦被害者法による被害者登録および支援作業が開始されて以来、本人が日本軍慰安婦だったことを自ら明らかにし、被害者として登録した人は230人余りに過ぎず、当時の状況について証言した人々は、その中でも一部である。結局、朝鮮人日本軍慰安婦全体が直面した具体的な状況がどうであったかに関して、現在までに知られている資料は非常に限定的で、確保された資料を見ても、それぞれの慰安婦が直面した具体的な状況はすべてが同一ではない。このように、現在までに知られている情報が制限的である点、および集団の規模が非常に大きい点まで考慮すれば、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団は、その性格が均質的であったり、境界がはっきりしていたりすると見るのは難しい。
〇上のラ6)項で見た通り、この部分の各表現は、「すべての朝鮮人日本軍慰安婦は自発的な意思にしたがって慰安婦になった」という内容ではなく、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という内容と見るべきである。すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団全体に対する陳述ではなく、その集団の中の一部だけを指し示して述べた陳述で、例外を認める平均的判断に当たる。したがって、この部分の各表現に名誉棄損的内容が含まれているとしても、それによって「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の構成員たち全体の社会的評価が低められたと見ることはできない。
〇告訴人らは、自ら慰安婦被害者であることを明らかにし、慰安婦被害者法第3条によって生活安定支援対象者として登録した約230人余りの人々の一部であり、告訴人たちの中の一部は実名と顔を公開して日本に対して日本軍慰安婦被害者に対する賠償を要求する活動の先頭に立ってきた。したがって彼らは「朝鮮人日本軍慰安婦」という全体集団の中で、相対的により広く知られている著名な人々ということができる。しかし、本件書籍全体を通して表現されている被告の核心的な主張は、本件書籍で最も目立つ部分である表紙に記載されている、「実はかつての「強制的に連れて行かれた少女」も、今の闘志も、「慰安婦」のすべてではない。「慰安婦」のすべての姿を見ることなしには、問題は永遠に解決されない。」という文句からもわかる通り、「日本軍慰安婦たちは、慰安婦になった経緯や慰安所での経験がきわめて多様な姿で存在していたもので、今までわれわれはその中の一つの姿、すなわち10代の少女時代に日本軍人によって直接強制的に連行され慰安婦になった人の姿だけを知っていたが、それと異なる姿の慰安婦もいたという点も知る必要がある」というものである。そのような基本的な立場を前提に、被告は本件書籍で、従来広く知られていたものとは異なる日本軍慰安婦の姿に注目して叙述しており、そのようにしつつ従来からわれわれが知っていた慰安婦の姿が「すべてではない」、または「例外的な場合だった」と述べているに過ぎず、そのような姿の慰安婦は嘘だとか、実際に存在しなかったと主張しているわけではない。その代表的な例として、日本軍慰安婦問題に関する被告の基本理解が要約されている219頁2~14行で、被告は「「朝鮮人慰安婦」は基本的に「同じ日本人」になり、軍人たちの欲求を受け入れる形で、朝鮮人を含む日本軍を「慰安」するために動員された者たちであった。われわれの前にいる被害者たちは、そのような一般的な「慰安」のシステマチックな加害に加え、個人的な暴力と強姦等の加害をより多く経験した事例である。」と述べ、「われわれの前にいる被害者たち」、すなわち従来われわれに広く知られていた慰安婦被害者たちを慰安婦被害者たち全体の中の一部として表現している。このような本件書籍の全体的は内容を考慮すれば、普通の注意深さでこの部分の各表現に接する一般読者としては、その表現に表れた「自発的な意思にしたがって慰安婦になった一部の慰安婦たち」について、朝鮮人日本軍慰安婦たちの中で自ら慰安婦被害者であることを明らかにしつつ、日本に対する賠償を要求する等の積極的な活動をしてきた告訴人らを指すものと認識するよりも、これまで慰安婦被害を受けたことを明らかにすることができず、世の中に名乗り出なかった残りの被害者たちを指す内容と認識する余地が大きい。
タ.小結論
したがって、この部分の各表現の対象者として告訴人らが具体的に特定されていると見ることはできないので、上の各表現によって告訴人らの社会的評価が侵害されたと見ることはできず、ほかに上のような点を認定する証拠がない。
5.名誉棄損の故意の有無
カ.関連法理
表現の自由と名誉保護の間の限界を設定するときは、問題になる表現の内容が私的関係に関するものであるか、公的関係に関するものであるかによって違いがあることに留意しなければならない。すなわち、当該表現による被害者が公的な存在であるか、私的な存在であるか、その表現が公的な関心事に関するものであるか、純粋な私的な領域に属する事案であるか、その表現が公共性、社会性を備えた事案に関するもので、世論形成や公開討論に寄与するものであるか、そうでないか等を吟味し、公的関心事と指摘な領域に属する事案の間には、審査基準に違いをつけなければならない。当該表現が私的な領域に属する事案に関するものであれば、表現の自由より名誉の保護という人格権を優先することができるが、公共的・社会的意味を持った事案に関するものであれば、その評価を異にすべきであり、表現の自由に対する制限が緩和されなければならず、したがって、その表現による名誉棄損の故意を認めるのに際しても、より厳格に審査しなければならない(最高裁2011年9月2日宣告2010ト17237判決、最高裁2016年5月24日宣告2013タ34013判決等参照)。
また、学問の自由には、言論・出版の方法で学問的研究の結果を発表する自由が含まれるものであるため、結局、研究結果を発表する行為は表現の自由の保護対象になると同時に、学問の自由の保護対象にもなり、ほかの一般的な言論・出版に比べて高度の憲法上の保障を受ける。また、学問の研究は既存の思想と価値について疑問を提起し、批判を加えることで、これを改善したり、新しいものを創出しようとしたりする努力であるので、その研究の資料が、社会で現在受け入れられている既存の思想および価値体系と相反したり抵触したりしても、容認されなければならない(最高裁2007年5月31日宣告2004ト254判決等参照)。したがって、名誉棄損かどうかが問題になっている表現が、学問的研究結果の発表に当たる場合は、このような理由からも、そのような表現に対する制限が緩和され、名誉棄損の故意を認めるのに際しても、より慎重でなければならない。
ナ.判断
上で見た通り、本件の各表現は、すべて告訴人らの社会的評価を侵害する名誉棄損的事実の摘示に該当しないだけでなく、たとえ本件の各表現によって、告訴人ら個々人の社会的評価が間接的であれ低められうると見られるとしても、本件の記録によって知ることができる次のような事情に照らして見れば、被告に告訴人ら個々人の名誉を毀損するという点に対する認識があったと認めるのは難しく、ほかに被告に名誉棄損の犯意を認めるだけの証拠がない。
○被告は、本件書籍の序文で、その執筆目的を明らかにしているが、そのおおよその趣旨は次の通りである。すなわち、被告はまず、慰安婦問題が20年以上にわたって解決されておらず、むしろ慰安婦問題に対する韓国と日本両国国民の認識の違いの乖離はもっと大きくなりつつあり、両国間の葛藤と対立もまたより悪化している状況を批判的に指摘している。被告は、そのような状況の最大の理由は「実際には「慰安婦」は決して一つで説明できる存在ではないにもかかわらず、われわれ(国民)たちの「慰安婦」についての理解が不十分であり、取捨選択された情報だけから作られた一つのイメージと記憶だけを作ってきたため」という主張をしつつ、それによる結果として、日本国民の間に韓国に対する嫌悪または無関心の感情が徐々に高まってきた状況、その原因として韓国国民の慰安婦問題に対する認識が、慰安婦支援団体や少数の研究者たちによって左右されている状況等を記述した後、韓日両国の葛藤と対立を克服して相互信頼と平和に至るために、本件書籍を著述することになったと明らかにしている。上の序文に表れている被告の状況認識や原因診断が妥当で適切であるかどうかについては議論の余地があるが、そのような序文の内容と本件書籍の全体的は内容を見れば、被告が本件書籍を著述した主要な動機が「韓日両国の相互信頼構築を通じた和解」という公共の利益のための目的に発したという点を否定するのは難しく、その意図が朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちの社会的評価を低下させようとするものであったと見ることはできない。
〇朝鮮人日本軍慰安婦問題は、韓国と日本の学界と市民社会において、研究と議論が続いている事案で、朝鮮人慰安婦の募集・移送・慰安所での生活等に関する実態、日本軍の慰安所設置・運営・管理等に関する責任、朝鮮人日本軍慰安婦動員に関する植民地期朝鮮の社会経済的要因等、被告が本件書籍で扱ったテーマは、韓国社会全体で国民たちが知るべき公共性・社会性を持っているものとして、公的関心事に当たると見るべきであり、別紙犯罪一覧表に記載の各表現を見ても、これを朝鮮人日本軍慰安婦被害者個々人たちの純粋に私的な領域に関する事案と見ることはできない。したがって、上のように公的関心事に関する内容を含む本件書籍について、それによる名誉棄損罪が成立するかどうかを審査するのにおいては、私的な領域の事案に関する場合と異なり、活発な公開討論と世論形成のために幅広い表現の自由を保障する必要がある。
〇本件書籍は、被告が朝鮮人日本軍慰安婦について新しい史料を提示したり、これまで学界に知られていなかった歴史的事実を発掘して紹介したりする本ではなく、学界ではすでに知られていた既存の史料と先行研究結果を土台にして、韓国社会の主流の見方と異なる立場から、主に一般市民に向けて被告自身の主張を開陳している学術的性格の大衆書である。一部、専門歴史研究者たちは、本件書籍について「被告が史料を取捨選択して分析する方法に誤りがある」であるとか、「被告が展開している推論に性急な一般化や過度の飛躍等の論理的誤謬がある」という批判等を提起している。しかし、そのような批判の内容と本件記録をともに見ても、被告が既存の史料に対する自分なりの評価と解釈に基づいて論争の余地の大きい主張を提起するという程度を越えて、新しい史料を捏造したり、既存の史料の内容そのものを歪曲したりする等の方法で、虚偽の歴史的事実をでっち上げようという意図を持っていたとまで見るのは難しい。また朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちについては、韓国の学界と市民社会において、すでにある程度歴史的評価が確立されつつある状態にあるもので、本件書籍で不明瞭な概念や抽象的で模糊とした表現、前後で矛盾していると見られる叙述等が多数発見される点、提示された史料や文学作品等の根拠と、それに基づいて提起された被告の主張の内容の間の論理的なつながり等に照らして見るとき、被告が本件書籍で主張した内容だけで、朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちに対する既存の社会的評価に有意味な程度の否定的な影響を及ぼすのは難しいと見られる。
〇本件書籍で被告が開陳したさまざまな見解については、多様な批判と反論が提起されうる。日本軍慰安婦被害について、日本に法的な責任を問うことはできないという被告の主張について批判することもできるだろうし、日本軍慰安婦被害に対する日本の責任を帝国主義や家父長制、資本主義等の一般的な社会構造の次元のものに還元すれば、この問題に固有の側面を看過し、結局、責任を薄めることになるという反論を展開することもできるだろう。たとえ被告の著述意図に悪意がないとしても、本件書籍の論旨は、結局、慰安婦問題否定論者たちに悪用されてしまうだろうと、その副作用を指摘することもできるだろう。しかし、これはどこまでも互いに異なる価値判断と評価の間の当否を問う問題で、それに関する判断は刑事訴訟手続きにおいて裁判所が遂行できる能力と権限の範囲を越えている。学問的表現の自由は、正しい意見だけでなく誤った意見も保護する。正しい意見だけが保護されるなら、意見の競争は存在できないだろうし、その場合、学術的意見の正誤を決定する主体は、結局、国家機関になるだろう。被告の見解に対する当否の判断は、学問の場で専門家たちが、さらに社会的公開討論の場ですべての市民が、互いに自由に意見を交換して、相互検証と論駁を重ねるやり方でなされるべきであり、またそうすることで最もよく達成されうる。実際に、被告が本件書籍を発刊した後、国内外の学界の専門家たちをはじめとした多くの人々が、上のようなさまざまな観点から被告の主張を批判する意見を開陳し、その結果として、本件書籍の主張を批判する内容を含む本(『Q&A「慰安婦」問題と植民地支配の責任』、『帝国の弁護人朴裕河に問う――帝国の嘘と「慰安婦」の真実』、『誰のための「和解」か――〈帝国の慰安婦〉の反歴史性』等)が出版された。これを見ても、韓国社会の公開討論の場は、被告が本件書籍で開陳した主張について、合理的な検証と論駁を行うことで、朝鮮人日本軍慰安婦問題について歴史的真実を明らかにし、適正な意見の歩み寄りに到達できる十分な能力があると見られる。
6.結論
結局、本件公訴事実のうち、番号5、20、26に記載の各表現と、番号16、34に記載の各表現を除いた残りの番号に記載の各表現は、すべて意見の表明に該当するに過ぎず、具体的事実の摘示と見ることはできず、番号5、20、26に記載の各表現は、事実の摘示には該当するが、告訴人らの名誉を侵害する内容と見ることはできず、番号16、34に記載の各表現は、名誉棄損的事実の摘示に該当するが、集団の名称だけを示したもので、上の各表現の対象者としてその集団の個別構成員である告訴人らが具体的に特定されていると見ることはできない。また、本件公訴事実に記載の各表現に関して、被告に名誉棄損の故意も認められない。
したがって、本件公訴事実は、犯罪の証明がない場合に当たるため、刑事訴訟法第325条後段によって無罪を宣告し、刑法第58条第2項にしたがってこの判決の要旨を公示する。
裁判長 判事 イ・サンユン
判事 イ・ジヘ
判事 キム・ウンジェ
犯罪一覧表
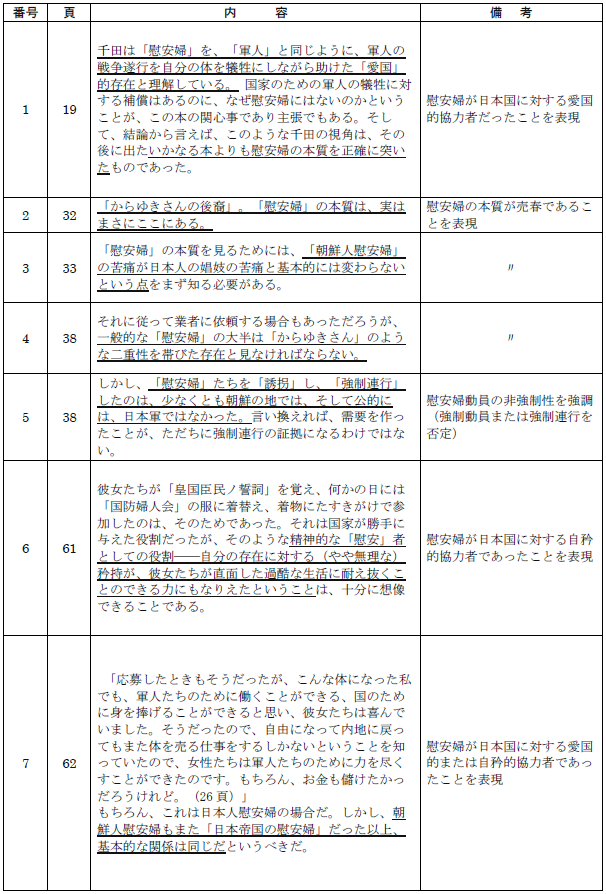
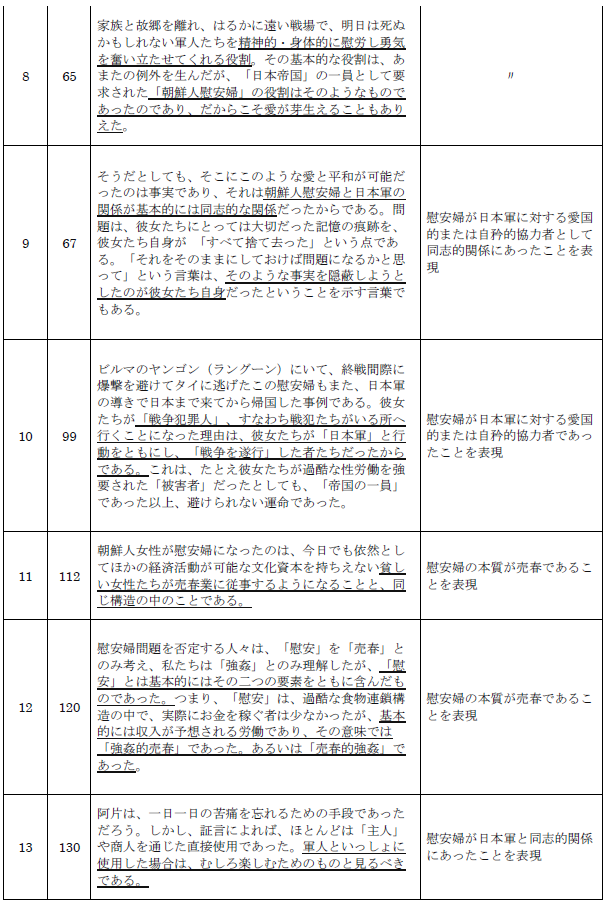
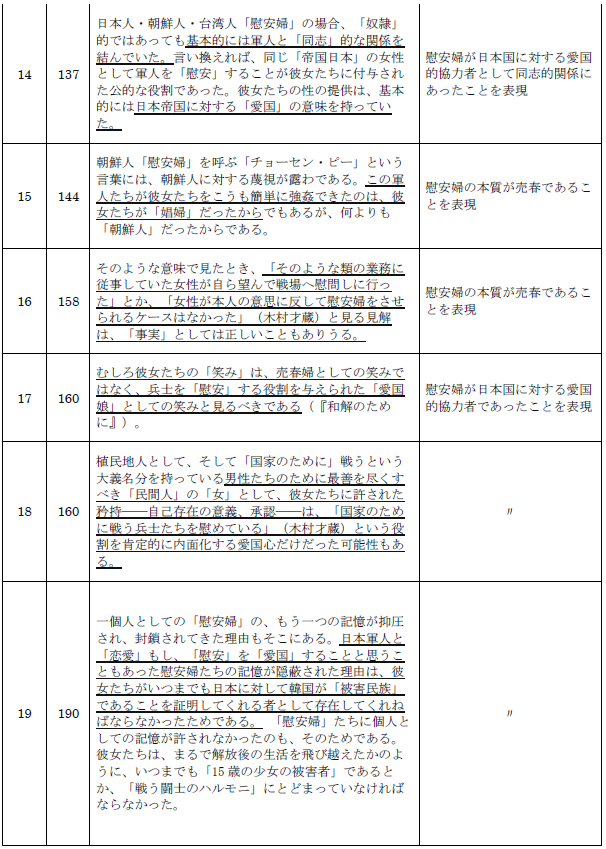
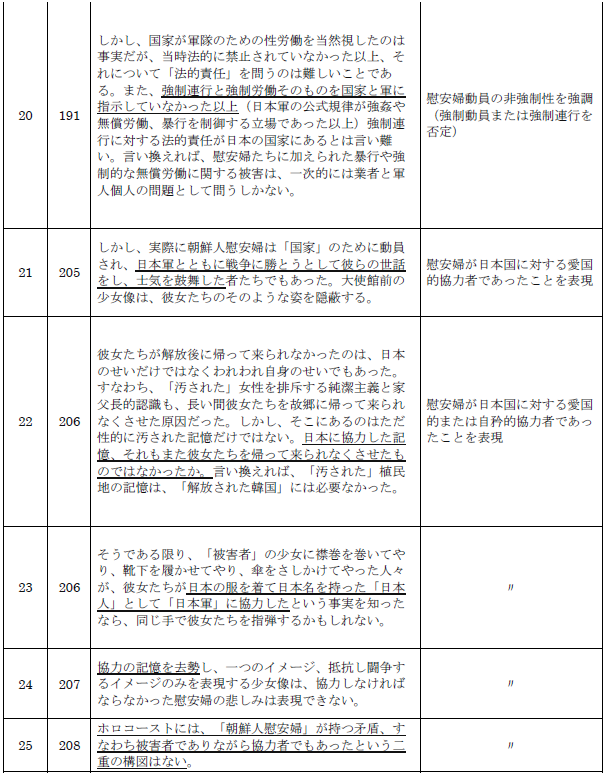
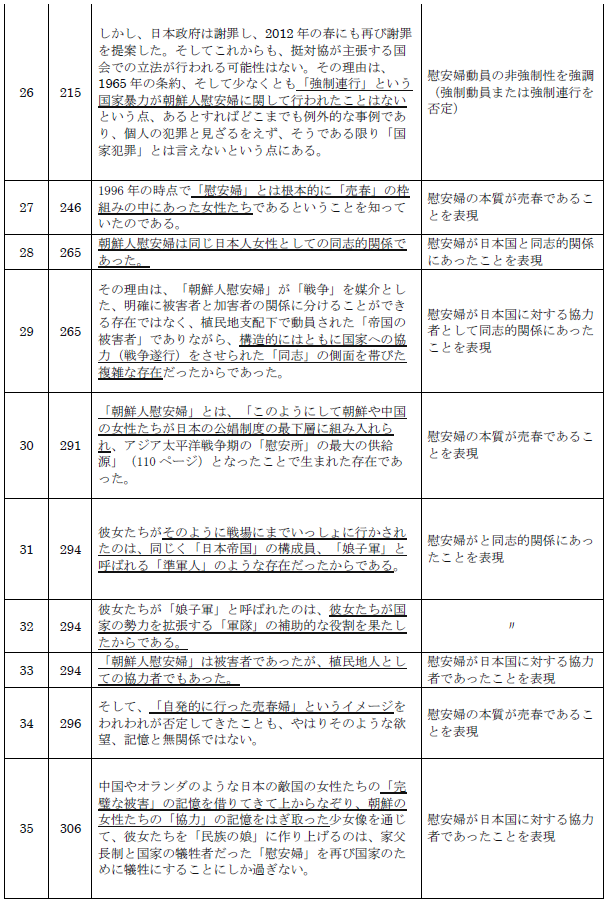
原口由夫, 「鄭栄桓-忘却のための和解 :『帝国の慰安婦』と日本の責任」批判
〔鄭栄桓『忘却のための「和解」』について〕
本書には、確かに朴裕河氏が言うように、数多くの「誤読」「曲解」がある。私が気づいたそのいくつかを提示したいが、全体の3分の2ほど読んだところで読むのを止めてしまった。何ものをも証明せず、ひたすら恣意的な読み替えで『帝国の慰安婦』を批判する本書に、これ以上読み続ける意味が見出せなくなったからである。したがって、本投稿は中途半端なものとなってしまったが、自分自身の備忘ということもあり、投稿することにした。
【略記号等】
1)最初のページ番号は、本書のページ番号。
2)≫で始まる部分は、本書掲載の、鄭氏による『帝国の慰安婦』の引用。
3)(帝、P.135)の「帝」は『帝国の慰安婦』を、(忘、P.46)の「忘」は『忘却のための「和解」』を指す。
4)>で始まる部分は、本書の地の文(鄭氏の文)。
5)――で始まる部分は、私の文(コメント)。
6)「Soh」は、Sara Soh “The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan, 2008.
7)[ ]内は私の補注。
P.17 ≫当時すでに挺身隊に行くと慰安婦になるという誤解があったから(中略)場合によっては当時のユン教授もそのようなうわさを聞いていたのかもしれない。また、実際に挺身隊に行ったあと、慰安婦になるケースもあったから、そのうわさが必ずしも嘘だったわけではない。
おそらく、このような混同が生じたのは、実際のケーズに基づくものではなく、そのような「うわさ」自体によるのだろう。(中略)植民地特有の恐怖がそのよう嘘を誘発した可能性が高いのである。(帝、P.135)
>この短い記述のなかには、(a)噂は「誤解」である、(b)噂は「必ずしも嘘だったわけではない」、(c)噂は「植民地特有の恐怖」が誘発した「嘘」である、という一見矛盾する三つの主張が併存している。このため内容への賛否以前に、著者の「噂」についての認識を理解することができないのである。
――この簡単な記述が鄭氏は理解できないのであろうか。鄭氏自ら「一見矛盾する」と言っている通り、「一見」であって実はそうではない。それが分かっていながらこのように(a)(b)(c)などとことさらに分けるのはなぜなのか(分けてみせている、と言うべきだろう)。内容は、挺身隊に行けば慰安婦になるという噂は「誤解」であり、真実ではないという意味で「嘘」であるが、中には実際に挺身隊に行ったあと慰安婦になったケースもあった。誰でも理解できることである。「一般」と「特殊」の違いにすぎない。恣意的に「矛盾する三つの主張」と分析し、曲解しているのである。
P.24-25 ≫「慰安婦」とはいったい誰のことだろうか。韓国にとって慰安婦とはまずは<日本軍に強制連行された朝鮮人の無垢な少女たち>である。しかし慰安婦に対する謝罪と補償をめぐる問題-いわゆる「慰安婦問題」をなかったものとする否定者たちは、<慰安婦とは自分から軍について歩いた、ただの売春婦>と考えている。そしてこの二十年間、日韓の人々はその両方をの記憶をめぐって激しく対立してきた。(帝、P23)
>朴裕河が提示する二項対立は奇妙である。対立の一方が「韓国」であるのに対し、「売春婦」と考える側は「日本」ではなく「否定者」とされる。「二十年間、日韓の人々」が「激しく対立してきた」というのならば、「否定者」を除いた「日本」もまた対立の内部にいるはずである。にもかかわらず二項対立はその存在を曖昧なものにする。この奇妙さに気づくかどうかが、本書の評価の分岐点となる。
――ここでも鄭氏は朴氏の文を「二項対立」と解釈し、この「奇妙さ」に気づくかどうかが本書の評価の分岐点になるとし、「二項対立の恣意性」とも述べているが、この解釈こそが恣意的である。朴氏は韓国で一般化している記憶-強制連行された無垢な少女-(20万人と付け加えてもよい)と日本の一部の極端な否定者-「自発的売春婦」派-を対置しているだけである。鄭氏はこの解釈の後、強制性と軍の関与の問題に若干議論を展開し、否定者が論点を強制性の問題に移しているのであるから朴氏の主張は「否定者の争点の設定を受けいれることを意味する」としているが、大きな間違いである。強制性を問題としているのは否定者だけではない。その強制性の問題も含めて、日韓の対立があるということだ。鄭氏は強制性の問題を否定者の見解とすることで、この問題を矮小化し、朴氏が提起した問題を争点とせず、朴氏の著作の「二項対立」という自らが設定した論理に問題をすり替えることで、この問題からの争点ずらしを図っているのである。実際に、本書には資料に基づいた強制性についての議論は展開されていない。鄭氏はP.28で「もちろん日本軍「慰安婦」制度全体をながめれば、軍による直接的・暴力的な強制連行も存在したことが明らかになっており」としているが、「全体」と一応書いてはあるが、直接的・暴力的な例があるのはフィリピン、インドネシアなどについてであり、朝鮮については確認されていないのである。朝鮮における強制性の問題が大きな疑問となっている現在、それを争点化させないために、あえて強制性の問題を否定者の争点とし、自ら設定した「二項対立」の図式の中に埋め込んでしまっているのである。そもそも、『帝国の慰安婦』を問題とするのであれば、何を置いても、強制性、自発性を問題とすべきであるはずなのに、本書は朴氏の「奇妙な」、「恣意」的な論理の解説に終始しているのである。
P.31 >慰安所設置は兵士の強姦防止に何ら役立たなかったと指摘されている
――不十分な研究成果の理解である。集団的強姦は減少しているという指摘がある(Soh, P.142)。また慰安所設置の目的は性病の予防でもあった。
P.32 ≫そういう意味では、慰安婦たちを連れていった(「強制連行」との言葉が、公権力による物理的力の行使を意味する限り、少なくとも朝鮮人慰安婦問題においては、軍の方針としては成立しない)ことの「法的」責任は、直接には業者たちに問われるべきである。それも、あきらかな「だまし」や誘拐の場合に限る。需要を生み出した日本という国家の行為は、批判はできても「法的責任」を問うのは難しいことになるのである。(帝、P.46)
>結局のところ日本国家の法的責任は否定されるのである。
――否定しているのではない。「「法的責任」を問うのは難しい」としているだけである。ここにも恣意的な読み替えがある。
P.32 >一方で朴は「軍属扱いされた業者」が女性たちを連れていったことを認めている。軍属とは日本の陸海軍に勤務した軍人以外の構成員の総称であるから、当然ながら「軍属扱いされた業者」による徴集は、軍による直接的な連行への関与を示す証拠となる。右のような業者=軍属との規定が自説と矛盾することに気づいていないようである。
――これを証拠とするのは初耳である。大体「軍属扱いされた」と朴氏が述べているように、業者は「軍属」ではない。「朝鮮人慰安所管理人の日記」にもあるように、軍属ではない朝鮮人管理人は軍属にのみ許された場所への出入りを断られている。
P.34 >だが、吉見の指摘を支持するならば…..軍が女性の徴集を命じなければ、人身売買も起きようはずがなく、その責任を軍もまた負うべきであることは当然であろう。にもかかわらず朴は、徴集の命令は「物理的な強制連行を想像させる」から「繊細な規定」が必要であるとして、日本軍の関与の事実に関する議論をイメージの問題にすりかえる。
――この章で鄭氏は軍の関与問題について朴氏を批判しているが、永井論文の指摘も含めて軍による慰安所設置と関与(兵站部への帰属、消耗品の給与等)は明らかな事実である。ただすべての慰安所がそうではなかったことは、慰安婦問題を少しでも齧った人間なら周知の事実のはずだ。そのことを朴氏は言っているにすぎないのである。また、吉見氏の指摘を持ち出しているが、さすが吉見氏は鄭氏の言うような、軍による「徴集」、「徴集の命令」などとは言っていない。吉見氏は次のように述べている。「もうひとつは、派遣軍からの要請を受けて、日本の内地部隊や台湾軍・朝鮮軍が業者を選定し、その業者が慰安婦を集めるやり方である」(吉見義明「従軍慰安婦」岩波新書、P42)。その通りである。「研究の成果をまったくふまえていない謬論」とは鄭氏に返されるべき言葉であろう。「まったく」ではないかもしれないが。
P.35-36 ≫軍が慰安婦募集過程でだましなどの違法な行為を取り締まろうとした….このような権力の存在こそが、軍の<管理>事実や主体的な関与を示すものであろう。つまり、たとえ軍が募集に直接関わっていないとしても、そのことが即、軍の関与がなかったことになるわけではないのである。不法で強引な募集を「取り締まった」ことこそが、この問題に対する軍の認知と権力と主体性を示す。
つまり、だましであれ拉致であれ、国から遠く離れた地域に持続的な需要を作り、業者たちが、ともかくも強制的な手段を使っても女性たちを連れていきさえすれば、商売になると考えるようなシステムを維持したこと自体が問題なのである。(帝、P.224-225)
>・・・・日本軍の役割は業者の「不法で強引な募集を「取り締まった」こと」にあるという理解は、朴がそれでも認めていた業者の不法行為を「黙認」した責任、という主張すらも覆す。「黙認」とは、文字通り黙って認めることを意味する。当然ながら、日本軍が業者の違法行為を取り締まったのならば、これを「黙認」したとの主張は成り立たなくなる。業者が軍の目を盗んで違法行為を行ったとすれば、「黙認」とはいえないからだ。朴裕河が「よい関与」論を採用した結果、「黙認」責任すら否定されてしまうのである。
――ここにも「奇妙な」言い替え、鄭氏の言葉を返すと「トリック」がある。「日本軍の役割は業者の不法で強引な募集を取り締まることにある」などとは朴氏は言っていない。そういう事実があったことが軍の主体的な関与があったことを示していると指摘しているにすぎないのである。理解力が足りないのか、恣意的に解釈して言い替えをしているのである。そこから「黙認」責任論との矛盾、「「黙認」責任すら」の否定に結論付けるのだが、暴論というしかない。これは恣意的に朴氏を貶めるための「謬論」である。
P.40-41 >本書は日本軍「慰安婦」制度が軍による「性奴隷制」であることを認めないが、その際の「性奴隷」説批判も….特異な用語法で行われる。….「奴隷」概念を改変したうえで言明される「「奴隷」だった」という主張は、事実上「奴隷ではなかった」と言っているに等しい。
――ここでは鄭氏が引用している朴氏の文章は挙げないが、それは、慰安婦が「性奴隷」であるかどうかは議論の分かれるところであり、朴氏が「性奴隷」という表現を拒否しようとそれは議論の問題であり、それを批判すればそれですむことなのである。しかるに鄭氏はその批判において、ここでもまた、朴氏の言説の言い替え、曲解を行い、朴氏の主張を「改変」しているのである。朴氏が身体的な拘束を伴った「奴隷」概念と、構造的に強制される存在としての「奴隷状態」を区別して論じているのを、概念の「改変」として、その結論を転倒させている。さらに根拠もなく「国際法学の議論や挺対協の主張を正確に理解せず批判する」とか、「「性奴隷制」概念を「性奴隷」イメージの問題にすりかえ….「慰安婦」の「すべてを表現」していないと的はずれな非難を行うのである」と、朴氏の議論が様々な「慰安婦」証言に基づく実態解明を前提に行われているにもかかわらず、その議論には入らず、概念理解が間違っていると切り捨てることで、鄭氏自身の言葉を使えば「論点のすりかえ」を行っているのは鄭氏自身である。慰安婦・慰安所の多様性についてや性奴隷制概念の政治的側面に関するSarah Sohの研究も参照すれば、鄭氏自身こそ政治的な言説を展開していることを知るであろう。研究者として実態に迫れば、「強制」や「性奴隷」の概念が単純ではないことを知るのである。
P.44 >まず、朴裕河の事実認識には数多くの誤りがある。朴は米国の戦時情報局心理作戦班作成の「日本人捕虜尋問報告書」第49号にある、ビルマ・ミッチナで捕虜となった朝鮮人「慰安婦」20人の記録を根拠に、平均年齢が「25歳」だと主張する。….しかも捕虜時の平均年齢も23.15歳であって「25歳」ではない。また、朴裕河は被害者たちの証言から「「少女慰安婦」の存在が必ずしも一般的ケースではなかった」(帝、P.64)と主張するが、証言した朝鮮人被害者たちの大多数は徴集時の年齢が20歳以下であり….
――ここでは朴氏の原文がなぜか省略されているが、原文は「….尋問を受けた朝鮮人慰安婦たちの「平均年齢は25歳」だった(「Japanese Prisoners of War Interrogation Report No.49」、船橋洋一 2004から再引用)。そしてある元朝鮮人日本兵も慰安婦たちが「20、21歳」だった自分たちよりも年上で、「お姉さん」と呼んでいたと語る(『海南島へ連行された朝鮮人性奴隷に対する真相調査』…2011、P.69・72・120)。」である。
どこが事実認識の誤りなのであろうか。貶めるための誇張である。言うまでもなく、この25歳という数字は証言記録に書かれている「average Korean girl…is about twenty-five years old」から来ているに過ぎない。つまり計算による正確な平均年齢なのではなく、証言記録者の印象なのである。そして実際の年齢も、同報告書の付録のリストにある記録番号順に記せば、21、28、26、21、27、25、19、25、21、22、26、27、21、21、31、20、20、21、20、21、であり、記録者が「about 25」としたのもうなづける(大体、平均値は鄭氏も書いているが、23.15であるから、「about 25」と大差はない。事実誤認ではない)。しかも、「徴集」時(1942年。尋問時は1944年)の年齢は、19、26、24、9、25、23、17、23、19、20、24、25、19、19、29、18、18、19、18、19、であるから、「徴集」時の年齢が20歳以下の人数は、20人中12人である。これを鄭氏は「大多数」としているが間違いであり、これこそが事実誤認であり、欺瞞である。さらに「名乗り出た被害者たち52人のうち、徴集時の年齢が20歳以下だったものは46名にのぼる」とか、「鄭鎮星によれば、1993年12月時点で韓国政府に申告した元「慰安婦」被害者175人のうち、「徴集」時年齢が20歳以下だった者は156人であった」と表まで付けて示しているが、戦後50年前後の時点で生き残っている人が若くして「徴集」されている人が多いのは当たり前である。高年齢者ほど鬼籍に入っているからである。つまり、鄭氏が挙げた52名と175名の年齢は、「徴集」されたのが20万人であろうと3万人であろうと、いずれにしても、50年以上前の「徴集」時の慰安婦全体の年齢については未成年がいたという事実以外は何も語ってはいないのである。1944年の20名の記録では不十分と言うなら、最近タイで発見された終戦直後の数百名の慰安婦の記録を精査すれば、より多くの知見を得ることができるであろう。ちなみに、私が、KBSで放送されたテレビ画面に映る25人の年齢を平均してみたところ、それは26.8歳であった。
以上の慰安婦の年齢問題に続けて、鄭氏は上野千鶴子の慰安婦パラダイムを紹介し、朴氏が「少なからぬ影響」(忘、P.46)を受けているとするのみならず、「『帝国の慰安婦』がその基本的なモチーフを上野論文から借用していることがわかる」(忘、P.47)、「上野千鶴子のレトリックを本書が借用している」(忘、P.47)とまで述べているが全く無意味な指摘であるのは、内在的な批判にはなっていないからである。
P.57 ≫そこで考えられるのは、親たちが娘たちの行く先が、単なる「挺身隊」ではないと考えていた可能性である。その形が<自発>だろうが<強制>だろうが、娘たちを待っているのが「慰安婦」の仕事と考えての悲しみであったかもしれない。そこには、娘たち自身の悲しい<嘘>――性に関わる仕事ではないと自分と親に納得させるために、内容が分かっていながら「挺身隊」に行くと話すような――があったかもしれないし、娘を貧しさゆえに売った親たちの<嘘>が介在していたかもしれない。多くの売春女性や強姦された女性たちが、その事実を公には言えなかった差別的な社会構造こそが、挺身隊と慰安婦の混同を引き起こし、いまだにひきずっている根本的な原因とも考えられる。(帝、P.62)、
>衝撃的な解釈である。もし朴のいうように親たちが「挺身隊」を「慰安婦」と理解していたとするならば、その最大の要因は日本軍や業者が挺身隊の名目で朝鮮人「慰安婦」を集めた事実があったからであろう。それが、当事者女性やその親たちの<嘘>の責任にされる。
――「衝撃的な解釈である」。本書P.17ですでに扱われた箇所に出てきているように、「挺身隊に行ったあと、慰安婦になるケースもあった」という<噂>がその要因であることは著者である鄭氏は承知のはずである。しかも、「当事者女性やその親たちの<嘘>の責任に」などされてはいない。日本軍や業者を免責していると言いたいのだろうが、全く文脈からずれた読み替えである。さらに鄭氏は続けて言う。
>そもそも、朴のいうように、自発的に行った女性も娘を売った親もみんな「挺身隊」に行くと嘘をついていたならば、なぜ親たちは挺身隊動員を「慰安婦」への徴集だと考えることができたのか、まったく説明がつかない。
――この理解からは「説明がつかない」。理解できないのか(そんなはずはない)、理解できないふりをしているのか、先行するP.17の著者の言葉とすれば「説明がつかない」。
P.59 ≫おそらく、このような混同を生み出したのはまずは業者の嘘によるものだったはずだ。「挺身隊に行く」と偽って、実際には「慰安婦」にするために戦場に送るような嘘である。それは自分の利益のためのみならず、軍が要望する圧倒的な数に応えるためにも、「挺身隊」という装置が必要だったのだろう。合法的な挺身隊の存在が、不法なだましや誘拐を助長したとも言える。そこに介在した嘘は、慰安婦になる運命の女性たち自身や周りの人々、そしてその家族をその構造に入りやすくする、無意識のうちに共謀した<嘘>でもあった。そこで行われている最後の段階でも民族的蹂躙を正視しないためにも必要だった、<民族の嘘>だったのかもしれない。
つまり、彼女たちのみならず、彼女たちを守れなかった植民地の人々すべてが、<慰安婦でなく挺身隊>との<嘘>に、意識的あるいは無意識的のうちに加担した結果でもあったのである。そして、そのような嘘を必要とする事態こそが、「植民地支配」というものであった。(帝、P.62)
>・・・・周到に日本軍の嘘のみを排除したうえで、<民族の嘘>なる驚くべき言葉が作られるに至る・・・・
この「共謀した<嘘>」なる言説が破綻していることは、上の引用だけからでも明らかである。女性や親たちが嘘をついていたとするならば、業者は嘘をついていないことになる。業者が連れていく目的を伝えていなければ、親や女性たちは嘘などつきようがない。結局朴のいう「共謀した<嘘>」「民族の<嘘>」論は、日本軍だけでなく業者すら免責し、末端の民衆たちに責任を転嫁する言説なのである。この<民族の嘘>なる言説は日本の植民地支配下を生きざるをえなかった朝鮮民衆の経験を不当に貶めるものといわざるをえない。
――鄭氏は理解できないのではなく「結局」以下に続く結論に持っていくために朴氏の言説を改変しているのである。「女性や親たちが嘘をついていたとするならば、業者は嘘をついていないことになる。」とはどういう理解なのか。曲解である。業者がつく嘘を嘘と思いながら内心を納得させる親や女性の自分自身や互いへの嘘という構造が植民地支配の桎梏もとであったのであり、その構造的な<嘘>を朴氏は「民族の<嘘>」と呼んでいるのである。日本軍や業者を免罪しているわけではないことは明らかである。
P.63 >2 千田夏光『従軍慰安婦』の誤読による「愛国」の彫琢
――「彫琢」というのは「宝石などをきざみ磨くこと。そこから、詩文の字句に磨きをかけること」(広辞苑)ということらしいから理解不能な見出しである。「・・・の誤読による、「愛国」意識の恣意的造作」とでもいうことであろうか。後に登場する「簒奪」といい、大げさな言葉である。しかも、誤用である。
P.63 >・・・・朴は・・・・千田が「慰安婦」について取材するきっかけとなった写真にふれ・・・・和服姿の朝鮮人「慰安婦」とそれを「蔑みの目」でみる中国人の写真を想像[させる記述をしているが]、・・・・能川が明らかにしたように、そのような写真は存在しない。
――存在している。現に本書のP.63の写真がそれである。渡河する二人の女性の写真と混同しているわけではない。鄭氏自身が理解していないだけのことである。
P.64 >実際『従軍』[千田夏光『従軍慰安婦』]をどれだけ探しても、朝鮮人「慰安婦」の本質が「愛国」的存在だったとの主張は見つからない。驚くべきことに、「どの研究よりも」「本質を正確に突いた」と称えるにもかかわらず、千田がどこでそう指摘したかも記されていない。
――ここでも朴氏の言説を巧妙に言い替えている。朴氏が「慰安婦」一般について述べているにも拘らず(「千田は慰安婦を、兵士と同じように、戦争遂行を自分の身体を犠牲しながら助けた<愛国>的存在と理解している」(帝、P.25))、「朝鮮人「慰安婦」」と限定することで、「どれだけ探しても」それは「見つからない」と言うのである。さらに「千田がどこでそう指摘したかも記されていない」としているが、それを「朝鮮人「慰安婦」」という文言に限定する限りは存在しないだけのことである。
P.66 >そもそも、日本人女性たちの「お国の為に働ける」という証言にしても、戦争遂行を助ける「愛国」的存在という解釈にはおさまりきらない側面がある。女性たちがこのように考えたのは、いずれも募集の際や「戦場に着いた当初」である。斉藤の証言はむしろ後方では「共同便所」扱いされる現実があったことを物語っている。
――この文の前に鄭氏が引用している千田の文は朴氏も引用(帝、P.73)しているにも拘らず、そのことは全く指摘されていない。それは、P.64で「千田がどこでそう指摘したかも記されていない」と朴氏の論拠を批判した手前、そう指摘するのを避けたのかもしれないが、それはともかく、誤読である。まるで「当初」は「お国の為に働ける」と思っていたが、後にはそうでないことが分かった、と言っているのだが、引用されている斉藤キリの証言は「第一線」と「後方」の扱いの違いを述べているだけのことなのである。真面目に書いているのなら誤読であるが、朴氏の「愛国」的存在論を否定するための嘘と言うことができる。
P.66 >朴裕河は証言以前に、千田の「声」を理解していないのである。
――「千田の「声」を理解していない」ということを示すために朴氏の言説の改変が行われているのである。
P.66-69 >この解釈の問題点は明らかである。朝鮮人についての証言でないにもかかわらず、<朝鮮人「慰安婦」=日本人「慰安婦」>という図式に従って、ただちに朝鮮人もそうであったろうと推測する。・・・・朴は検証すべき仮説をあたかも証明された命題であるかのように用いて個々の事例を演繹的に解釈する誤りを犯すのである。「女性たちの声にひたすら耳を澄ませる」こととは程遠い。
――鄭氏は朴氏が数多く挙げている「証言集」(挺対協編)からの引用(帝、P.80-88)を全く無視して千田からの引用のみを取り上げ、朴氏の論拠を「不可解」「飛躍」「誤謬」と断じているが(忘、P.68)、「証言集」 「女性たちの声にひたすら耳を澄ませる」朴氏の姿勢を無視して、自らの命題に結論付けるための恣意的な論法である。
P.72 >朴裕河の解釈には明らかに無理がある。「同族」という言葉や「同志意識」は「春江」や「梅千」のものではなく、「私」「おれ」の言葉だからだ。もしこれらの小説から読み取れるものがあるとすれば、それは「慰安婦と自分を同一視」する「私」「おれ」の姿である。
――これも詭弁である。「同族」という言葉が登場するのはまず兵士の言葉としてであるから、そのような意識は慰安婦たちにはないと言うのである。慰安婦が軍人を自分と同一視した、「春江」の言葉はここで全く消されることになる。「同族」という言葉が使われた意味を無視して、言葉としての「同族」だけを取り上げるからである。その結果、慰安婦が軍人を自分と同一視したことはなかったことになるのである。恣意的な論法である。
P.78 >2 証言の簒奪
――「簒奪」とは「帝位を奪い取ること」(広辞苑)らしいから、これも意味不明の見出しである。大げさな言葉を使っているが誤用である。一例しか挙げていないが、「証言の略取」とでも言いたいのであろうか。
P.80 > ・・・・重要な個所なので引用しよう(【 】部は朴裕河が引用した箇所である)。
「私は口が上手じゃなかったからうまくも言えないし、私は思った通りにしか言えない人間だから。【日本人に抑圧はされたよ。たくさんね。しかし、それも私の運命だから。私が間違った世の中に生まれたのも私の運命。私をそのように扱った日本人を悪いとは言わない。】同じ韓国人だけど韓国人が主人になってからどれほど私を殴ったかわからない。客をとらないからって。股が痛くて死にそうなんだ。たくさん涙も出てくる。ご飯も食べられない。夜は軍人が来ないから自分の世界だと思えて大丈夫なんだけど、夜が明けると軍人が来ると思うと、ただそのまま地獄に入るような気がする。地獄で生きているみたいだ。軍人たちが怖くて。(中略[ママ])いま思うとなんであんな目にあったのかと思う。私は犬も同じだ。・・・・アイグ、日本の軍人のことを考えると本当に恨めしい。恨めしいのは恨めしいけど、あの軍人たちもみんな死んだはずだよ」。
P.80 >「苦痛を作った相手」とは、自分を銃台で殴り続けた軍人をさすが、黄さんの力点は「運命」にあり、許しではない。「悪いとは言わない」とはあるが、「許す」とは一言も語っていない。
――「「苦痛を作った相手」とは、自分を銃台で殴り続けた軍人をさす」とあるが、それだけではないであろう。だからこそ「運命」という言葉が登場するのである。また鄭氏は言外の意味というものを全く認めないらしい。それはともかく、朴氏自身の言葉を正確に引用しておこう。朴氏は証言を引用した後、「自分の身に降りかかった苦痛を作った相手を糾弾するのではなく、「運命」ということばで許すかのような彼女の言葉は、葛藤を和解へと導くひとつの道筋を示している」と述べている。「許すかのような彼女の言葉は」「ひとつの道筋を示している」としているのである。どこが「簒奪」なのであろうか。私もこの黄さんの言葉に感動する者の一人だが、そこから感じ取れるものは、やはり「運命」という言葉で「許すかのような」彼女の広く深い心なのである。朴裕河氏はその心の声を聞き取り、そこから新しい道筋を見出そうとしているとしか思えないのである。
Original Link 2016年8月21日
[裁判関連] 『帝国の慰安婦』裁判、判決文(要約)
報道資料2017.1.25
ソウル東部地方裁判所 2015コハプ329 名誉棄損事件判決
[第11刑事部(部長判事イ・サンユン)、2017.1.25宣告]
1.当事者
被告 朴裕河(世宗大学校教授)
2.事件の経緯
―被告は、2013年7月17日に『帝国の慰安婦』(以下、本件書籍)を執筆し、2013年8月12日に出版した。
―上の書籍は日本軍慰安婦問題を扱っており、その本文に「「慰安」は過酷な食物連鎖構造の中で実際にお金を稼いだ者は少なかったが、基本的には収入が予想される労働であり、その意味では「強姦的売春」だった。または「売春的強姦だった」、「そして「自発的に行(い)った売春婦」というイメージをわれわれが否定してきたこともまた、そうした欲望、記憶と無関係ではない」、「日本人・朝鮮人・台湾人「慰安婦」の場合、「奴隷」的とはいえ、基本的に軍人と「同志」的な関係を結んでいた」、「「朝鮮人慰安婦」は被害者だったが植民地人としての協力者でもあった」、「「慰安婦」たちを「誘拐」し「強制連行」したのは、少なくとも朝鮮の地においては、そして公的には、日本軍ではなかった」などの表現が記載されている。
―日帝によって強制的に動員され性的虐待を受け慰安婦生活を強要された被害者たちで、「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業などに関する法律(以下、慰安婦被害者法)」に従い登録された人々のうち11名は、被告が本件書籍を通じて彼らの名誉を毀損したとして告訴した。
―検事は、「被告は本件書籍の中の35か所の表現を通じ、(1)「慰安婦は本質が売春だった」という虚偽事実、(2)「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、日本または日本軍の愛国的または矜恃をもった協力者で、日本軍と同志的関係にあった」という虚偽事実、(3)「日本ないし日本軍による慰安婦強制動員または強制連行はなかった」という虚偽事実を摘示したことにより、告訴人らの名誉を毀損した」という趣旨で、被告を虚偽事実摘示による名誉棄損罪で起訴し、懲役3年を求刑した。
3.裁判所の判断
カ.結論:無罪
―検事が起訴した本件書籍の35か所の表現のうち30か所の表現は、被告が主観的な意見を表明したものにすぎず、具体的な事実を摘示したものと見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。
―被告は、本件書籍のうち3か所の表現を通じ、「朝鮮人女性たちを強制的に連行し慰安婦にすることは、日本ないし日本軍の公式的な政策ではなかった」という事実を摘示したものと認められる。しかし、これは告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちの名誉を毀損する表現と見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。
―被告は、残りの2か所の表現を通じ、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示したことが認められ、これは日本軍慰安婦被害者の名誉を毀損しうる表現に該当する。しかし、被告は個々の人を特定せず、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団を記しただけで、被告の上の表現によって集団の個別構成員である告訴人らの名誉まで毀損したと見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。
―たとえ本件書籍のそれぞれの表現によって告訴人ら個々人の名誉が毀損されたと見ることができたとしても、被告に名誉を毀損するという故意があったとはいえない。
ナ.具体的な理由
1) 30か所:事実の摘示に該当しない
●名誉棄損罪が成立するためには、問題とされる表現が「具体的な事実の摘示」、すなわち時間的・空間的に具体的な事実関係についての陳述で、その内容が証拠によって証明可能なものでなければならない。これは「意見の表明」、すなわち事実関係についての主観的な評価や価値判断に該当する表現とは区別される。
●30か所の表現は、すべてその意味を一義的に確定しがたい抽象的・比喩的な表現を使っており、相当数は慰安婦たちの証言などの資料をそのまま引用して記述した後、それに関して被告人なりの分析と評価を示している内容である。
●上の表現の前後の文脈および本件書籍の全体的な内容を見れば、被告は「日本軍慰安婦被害の根本的な原因は、帝国主義、国家主義、資本主義、家父長制などの社会構造的側面にある」という基本的な観点を採りつつ、「朝鮮人日本軍慰安婦は国家の勢力拡張の過程で社会の最下階層である貧しい女性たちが国家によって動員されたものであり、そうした側面において、過去の日本人慰安婦や今日の貧しい女性たちが売春業に従事させられるのと同じ側面がある」、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時植民支配下で日本帝国の一員として扱われていたために、敵国女性とは異なり、日本の帝国主義戦争遂行のための役割を国家によって付与され、動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係だった」などの抽象的・構造的次元の分析と評価を提示しているものと見られる。このような分析と評価は、それが妥当かどうかを問いただすことはできても、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。
●被告は「売春」という用語を使いつつも、慰安所内で慰安婦たちが暴行など過酷な行為を受け、性労働を強要され、その代価は抱え主たちが搾取したと叙述している。このような文脈に照らせば、被告が「売春」という表現を「自発的な売春」という意味で使ったものと見るのは難しく、ただ当時の日本軍慰安所が「管理売春」、すなわち日本軍が管理する売春業の形態をとっていたという意味で使ったと見る余地が大きい。
2) 3か所:事実の摘示に該当するが、名誉棄損的な事実の摘示ではない
●3か所の表現は、「日本や日本軍が法令や指示などの公式的な政策を通じて朝鮮人女性たちを物理的に強制連行し日本軍慰安婦にした事実はない」という事実を摘示していると見ることができる。ここで被告が焦点を合わせているのは、「公式的な政策を通じて」という部分である。被告は日本軍人または民間業者による慰安婦強制連行が一部あったということは認めているが、これは国家次元の公式政策を通じてなされたものではなく、個人的な逸脱行為と見ている。
●告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちがもつ被害者としての社会的評価の核心は、彼らが自身の意思に反して日本軍慰安所で慰安婦としての生活を強要されたということにある。彼らが物理的な強制連行によって慰安婦になったのか、さもなければ詐欺・誘惑に騙されて慰安婦になったのか、そうした強制連行や詐欺・誘惑をおこなった人が日本軍人だったのか、さもなければ民間人の抱え主や業者だったのか、さらに日本もしくは日本軍が強制連行を公式的な政策として指示したのか、さもなければ個人的逸脱行為として強制連行が発生したのかは、慰安婦被害者たちの被害者としての社会的評価に影響を及ぼすとはいえない。
3) 2か所:名誉棄損的な事実の摘示に該当するが、集団の個別構成員である告訴人ら個々人の名誉が毀損されたとはいえない。
●被告は2か所の表現で、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示した。
●日本軍慰安婦被害者としての地位は、最初に慰安婦になった当時、自発的に行(い)ったのか、さもなければ意思に反して行ったのか、ということだけにかかっているのではない。最初は自発的に慰安婦になったとしても、慰安所内で性的意思決定の自由を剥奪されたまま性的虐待を受けたとしたら、同じように日本軍慰安婦被害者に該当する。しかし、従来、日本の慰安婦問題否定論者が、最初に慰安婦になる過程で直接的・物理的な強制連行があったのかどうかを重要視してきたため、韓国社会では、日本軍慰安婦たちがどのような経緯で動員され慰安婦になったかが重要問題として取り上げられ、議論されてきた。したがって、ある慰安婦被害者が自発的意思で慰安婦になったという事実が知られれば、これはその慰安婦被害者の社会的評価を低下させうると見なければならない。したがって、上の2か所の表現において摘示された事実は、名誉棄損的な事実に該当する。
●しかし、被告は上の2か所において、告訴人らを特定して表現したのではなく、「慰安婦」という集団だけを指し示して表現した。刑法上、名誉棄損罪は特定の人の個人的名誉を保護するためのものなので、被害者が特定されていなければならない。「ソウル市民」、「京畿道民」のような漠然とした集団表示では個々の被害者が特定されず、原則的に名誉棄損罪は成立しない。例外的に、集団の名称だけを記したのに、周囲の情況などから見て集団内の個別構成員を指し示しているものと見ることができたり、集団に対する非難が個別構成員にいたるまで薄まらず、構成員個々人の社会的評価を低下させるほどであると評価されるときは、集団表示だけでも名誉棄損罪が成立しうる。
●以下の理由から、集団構成員である告訴人ら個々人の名誉が毀損されたと見ることは難しい。
―上の2か所の表現の文脈と本の全体的な内容上、被告は「歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦全体」を指し示したものであり、そのうちの一部下位集団もしくは特定の人を指し示したものと見る根拠がない。
―歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦の正確な数字はわからないが、学者たちの推算値によれば、少なくとも1万5000人以上、多く見積もれば32万人に達する。個別構成員にいたるまで非難が薄まらず、構成員個々人の社会的評価にまで影響を及ぼし得ると見るには、集団の構成員数が多すぎる。
―「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の性格が均質的であるとか、その境界がはっきりとしていると見ることも難しい。
―上の2か所の表現は「すべての朝鮮人日本軍慰安婦が自発的な意思で慰安婦になった」ということではなく、「朝鮮人日本軍慰安婦の中に一部自発的な意思で慰安婦になった人がいる」というものであり、構成員全体を指す陳述ではなく、例外を認める陳述である。
―告訴人らは公開的に慰安婦問題に関する活動をしており、日本軍慰安婦被害者全体の中でも広く知られている人々ということができるが、本件書籍の核心的な主張は、「日本軍慰安婦たちは、慰安婦になった経緯、慰安所での経験が、みな多様な姿で存在しており、今までわれわれは、そのうちの一つの姿、すなわち10代の少女時代に日本軍人によって直接強制的に連行され、慰安婦になった人の姿だけを知っていたが、それとは異なる姿の慰安婦もいたという点も知る必要がある」というものである。したがって、一般読者としては、被告がいう「自発的な意思によって慰安婦になった一部の慰安婦たち」が、われわれに広く知られている告訴人らを指すのではなく、これまで世の中に知られていなかったほかの慰安婦被害者たちを指しているものと認識する余地が大きい。
4) 名誉毀損の故意を認めることはできない
●本件書籍の全体的な内容を見れば、被告の主要な執筆動機は「韓日両国の相互信頼構築を通じた和解」という公共の利益のための目的から発したものであり、朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちの社会的評価を低下させようという目的があったと見ることはできない。
●本件書籍で扱った朝鮮人日本軍慰安婦問題は、韓国国民が知るべき公共性・社会性を持つもので、公的関心事に該当する。このような公的関心事に関する表現については、私的領域の事柄に関する表現とは異なり、活発な公開討論と世論形成のために、表現の自由を幅広く保障すべきである。
●本件書籍は、新しい資料を提示したり、これまで学界に知られていなかった歴史的事実を発掘して紹介している本ではなく、学界ではすでに知られていた既存の資料と研究結果をもとにして、韓国社会で主流をなす見方とは異なる立場から、主に一般市民に向けて、被告の主張を開陳する学術的性格の大衆書である。被告が本件書籍において、既存資料についての自分なりの評価と解釈に基づいて論争の余地の大きい主張を提起するという程度を越えて、新しい資料を捏造したり、既存資料の内容自体を歪曲するというようなやり方で、虚偽の歴史的事実を作り出そうという意図を持っていたとまで見ることは難しい。
翻訳: H.H.
オリジナルのブログのリンク
『帝国の慰安婦』無罪、慰安婦ハルモニ側と朴裕河教授のインタビュ-(京郷新聞2017年1月28日)
『帝国の慰安婦』無罪、慰安婦ハルモニ側と朴裕河教授のインタビュ-
「判決にショックを受けた。『帝国の慰安婦』は悪意ある本」(慰安婦ハルモニ側のヤン・スンボン弁護士)
「名判決だ。私の本をきちんと読めば誤解は起こらないはず」(朴裕河世宗大教授)
著書『帝国の慰安婦』で日本軍慰安婦被害者たちの名誉を毀損した疑いで裁判を起こされた朴裕河世宗大日本語日本文学科教授(60)が25日、一審で無罪を宣告された。ソウル東部地方裁判所(裁判長イ・サンユン部長判事)は、朴教授に対し、「学問の自由は憲法上保障された基本権であり、学術表現は正しいものだけでなく、間違ったものも保護しなければならない」と無罪を宣告した。
イ・オクソンハルモニ(91)ら、慰安婦被害者11人は2013年8月に出版された『帝国の慰安婦』について、2014年6月、朴教授を、出版物による名誉毀損罪で告訴した。検察は、2015年11月、『帝国の慰安婦』において、日本軍慰安婦が「売春」であり、被害者は、日本帝国と「同志関係」にあったと表現したとして、名誉毀損の疑いで朴教授を起訴した。
『帝国の慰安婦』には、さまざまな争点がある。慰安婦問題をめぐる歴史的記憶の闘争、外交問題、普遍的人権、そして学問と表現の自由…。このため、『帝国の慰安婦』は、これまで学界、法曹界、市民社会で熱い議論の的になっていた。
この日の判決について、慰安婦被害者側のヤン・スンボン弁護士と朴教授の考えを聞いた。検察は26日、控訴した。
慰安婦ハルモニ側のヤン・スンボン弁護士、「裁判所が本を正しく理解していない」
-一審判決についてどう評価するか。
「不当な判決だ。2015年2月に出版差し止めの仮処分申請が一部認められ、本の内容の一部が削除された。昨年1月には、本の内容がハルモニの人格権を侵害しているという理由で、民事訴訟で慰謝料の支払い命令が出た。民事訴訟のように、刑事訴訟でも同様の結果が出てくると思っていた。本をじっくり読み、どんな意図を持って書いたのかを考えれば、このような判決は出なかっただろう。裁判所が本を正しく理解しなかったようだ。裁判所は、朴教授が客観性を持って熱心に研究したと考えたようだが、でたらめだ。
-朴教授は、自分の本をきちんと読めば誤解は起こらないはずと言っている。
「本を何度も読んだ。私も初めて読んだとき、「何の問題があるんだろう」と思った。本に「言い逃れ」の表現が多い。たとえば、「同志的関係」とか「自発的売春婦」という表現をしても、「日本に責任がないわけではない」という表現をつけておく。本の内容が行ったり来たりして、最初は何を言っているのか正確にはつかめなかった。しかし、何度も読めば、客観的な研究といえないことがわかる。朴教授は慰安婦の被害を日本の「戦争犯罪」と見ていない。朴教授は慰安婦問題が貧しい社会、男性中心の社会、国家中心の社会では、いつでも存在しているのだから、日本の戦争犯罪は、特別なケースではないと見ている」
-朴教授の主張のどこがいちばん問題か。
「慰安婦は、日本に「法的責任」を問うことのできない「自発的売春」というふうに言いくるめている。日本政府の論理と同じだ。朴教授は、「賠償」ではなく「補償」を主張している。日本帝国と慰安婦は「同志的関係」にあり、日本の軍人のように、慰安婦たちも国(日本帝国)により犠牲になったので、補償してやろうという立場だ。非常に悪意がある。ところが、裁判所は、朴教授が慰安婦問題を解決するために、善意を持っていると見ていることにショックを受けた。実は私は裁判所が無罪を宣告するとしても叱責しつつのものだろうと思っていた。ところが擁護するので、大きなショックを受けた」
-学問的な批判の領域であって、刑事罰の対象ではないという反論も強い。
「当然、表現の自由は重要だ。しかし、刑法の表現の自由と相容れない個人の人格権と名誉権もある。表現の自由も、無制限の自由ではなく、限界がある。朴教授の表現がその限界を超えたかどうかが問題だ。限界を超えて、ハルモニの人格権を毀損した。私は朴教授が表現の自由を十分に享受していると思う」
-今後、どのような予定か。
「民事裁判では、事実摘示による名誉毀損が認められたが、刑事裁判では違う見方がされた。私がいちばん驚いたのは、問題の表現35個所のうち30個所を単なる意見表明と見なしたことだ。十分に客観的な証拠から引き出せる事実摘示なのに意見表明と判断されびっくりした。民事裁判の結果と、あまりにもかけ離れた判断なので、控訴審では、この点をもう一度冷静に争わなければならない」
-被害者のハルモニたちの反応はどうか。
「ハルモニたちはひどくショックを受けている。怒り、不満がさめられない様子だ。民事訴訟ではなく、刑事訴訟なので、検察と被告の戦いであり、われわれがとりうる行動は意見書を提出することくらいだ。反論の資料を集めて意見書を出すつもりだ。朴教授は、慰安婦が日本政府の戦争犯罪被害者だと考えていないが、私は見方が違う。日本軍慰安婦は日本政府の戦争犯罪だ。これを否定する『帝国の慰安婦』の意図は本当に悪いと思う」
朴裕河世宗大日本語日本文学科朴裕河教授、「本をきちんと読めば何の問題もないはず」
-判決についてどう評価するか。
「名判決だった。裁判所が正義をもって勇気ある判決を下した。本の一節を一つ一つ取り上げていた、合理的に判断すれば、何も問題がないと思う。民事裁判で下された慰謝料支払い命令も、中止を申請し認められた。刑事裁判で、十分に無罪を得られると思っていた。最近の「崔順実ゲート」は、韓国社会のさまざまな問題が明るみに出され、正されていく過程であり、今回の判決もそうした過程の一環として受けとめたい。今後も、葛藤を分析し、代案を提示することにより、韓半島と東アジアの平和に貢献したいと思う。今回の判決は、韓国社会の重要な転換点だと思う」
- 『帝国の慰安婦』を書いた目的は何か。
「戦争犯罪としてのみ見られていた慰安婦問題の原因を、帝国主義に見出した本だ。慰安婦は、国家が強要した売春であり、強要した愛国だった。本を読んで慰安婦被害者たちの悲しみを正しく知ることになり、謝罪の心を持つようになったという日本人が多かった。韓日関係の場合、支配者だった日本に大きな責任があるのは明らかだが、すべての関係は、自分自身を振り返る自省的な態度がなければ、常に平行線を辿るほかない。主に日本帝国の責任を問い、植民地朝鮮の問題についても少し言及しただけなのに、とんでもなく歪められ、あまりにも多くの誤解や非難を受けた。私は被害者のハルモニたちの抑圧された声を代弁しただけだ」
-裁判の過程についてどう思うか。
「私を非難する声と力があまりにも大きかった。慰安婦支援団体は、自分たちの考えを国民の常識として作り上げてきた。私が戦った相手は、被害者のハルモニではなく、私の本を自分の見方で読み、伝えた人々だったということを、最も強く言いたい。証拠も裁判所に提出した。裁判を経験し、慰安婦問題についてさらに勉強し、本に書いたことにいっそう強い確信を持つようになった。私を批判する人々に、公開討論会を何度も要請したが、応答がない」
-慰安婦被害者のハルモニたちが裁判の結果について怒っている。
「私を刑事告訴した被害者のハルモニは11人で、その中の2人だけが裁判所にもいらっしゃった。ところが支援団体は、すべての被害者ハルモニが私を非難しているかのように歪曲している。しかし、ハルモニの中には、私の意見と同じように考えている方もおられた。告訴したハルモニも、私の主張を正確にお知りになったら誤解が解けると思う。昨年12月20日の結審公判で行った最終陳述も、ハルモニたちに聞かせようという思いで書いた。しかし、支援団体がハルモニを連れて出ていってしまったので、最終陳述を聞かせることができなかった」
-裁判所が無罪の根拠として「学問と表現の自由」の領域であることを挙げた。
「マスコミの報道を見ると「間違った表現であっても許されなければならない」という趣旨のようだ。しかし、私は依然として間違った内容があるとは思っていない。問題になった「自発的売春」という表現は、慰安婦強制動員否定論者がそのように言ったことを批判した文脈で出てくる。私は一度も「表現の自由」という理屈で本を擁護したことはない。心を開き、きちんと読めば何の問題もない本だ。問題を正しく見てこそ、責任もきちんと問うことができ、謝罪もしてもらえる」
-慰安婦問題について、また本を出すつもりか。
「歴史的事実について『帝国の慰安婦』に書かなかったことを書くべきだと思っている。平和を志向しているかのように見える韓日知識人の考え方が、なぜ不和と暴力を呼んでしまうのか考えたい。冷戦後の韓日の不和は続き、私をとんでもない暴力で追いつめた。すでに書き始めており、できるだけ早く出せればと思う。おそらく書名は「暴力の構造」もしくは「歴史への向き合う方」になるだろう」
翻訳: H.H.
オリジナルのブログのリンク
(社説) 『帝国の慰安婦』著者・朴裕河氏に対する無罪判決を歓迎する [中央日報 2017.01.27]
社説,『帝国の慰安婦』著者・朴裕河氏に対する無罪判決を歓迎する (韓経)
[裁判関連]『帝国の慰安婦』刑事訴訟 最終陳述
Huffington Post link (1)
Huffington Post link (2)
2016年12月20日、1年間続いた刑事裁判の結審があった。以下はその日、法廷で読んだ最終陳述の全文である。私は準備公判が進行中だった5月に反論証拠資料として1000枚余りの資料を提出している。慰安婦に関して知ることのできる証言、手記、記事などである。慰安婦問題全体が理解しやすいように、時代順、そして当事者、周辺人物、学者順ににした(資料が出てきた時期が遅かったとしても、同時代の人々の発言や彼らが見た光景順に並べて提出した。リンク資料参照、刑事訴訟 公判記2)。そしてその後、『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』が、慰安婦を名誉毀損する本ではないことを証明する他の様々な資料を「参考資料」として提出した。本文で「証拠資料」「参考資料」と記述しているものは、そのように区別した2種類の資料のことである。但し、参考資料の中にも証拠資料以上に重要なものもある。例えば、元慰安婦の方との電話録音記録や映像である。
参考資料は結審までに160以上提出し、この手記を書きながら新しく言及した資料を「追加資料」とした。本文と一緒に裁判所に提出する予定である。リンクなど、まだ不備のところがあるのを承知で公開しておく。
検察はこの日、私に懲役3年を求刑した。「歴史的事実を意図的に歪曲した点、反省していない点、被害者たちの名誉を著しく毀損した点を考慮しなければならない」と述べながらのことである。
この言葉を聞いて気がついたが、検察は私の「反省」を引き出そうとしたようだ。私は刑事の全ての審問に対して反論できたが、反省の態度を示さなかったことに不満があったかもしれない。
確かに、検察と関係者は、起訴の前に調停を勧めつつ「謝罪」「韓国語削除版の廃刊」「日本語版の削除」を要求した。私を非難してきたある教授も、原告側に告訴の取り下げの仲介の役を引き受け「日本語版の廃刊」を要求してきた。そして、私が最後まで応じられないと言ったのは、日本語版の削除・絶版のみである。
しかし彼らは私に何を要求したかは言わず、私が調停で謝罪を要求したと言って、あたかも私が元慰安婦の方に謝罪を要求したかのように非難した。私が要請したのは、私の本を歪曲して告訴して全国民の非難を浴びるように仕向けた周辺の人たちの謝罪である。元慰安婦の方々を非難したり、何かを要求したりしたことは私には一度もない。
私が絶望するのは、求刑そのものではない。私が提出し説明したすべての反論資料を見ておきながら、見ていないかのように厳罰に処してほしいと言ってしまえる検事の良心の欠如、あるいは硬直に対してである。もちろんその背後にあるものは、元慰安婦の方々ではなく周辺の人々である。
この求刑は、歪曲と無知の所産である論理を検事に提供して、おうむのように代弁させた一部”知識人”たちが作ったものである。
———-
尊敬する裁判長、
形事裁判が始まってからもう一年になろうとしています。その間、私にも発言権を与えていただき、私の説明に耳を傾けつつ公正に進めて下さったことに対して、まず、深く感謝申し上げます。
1.故意性(犯意)があったという主張に関して――『帝国の慰安婦』を書くまで
まず、私が『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』を書くようになった経緯に対して話します。
1)私は25年前、留学が終わる頃に東京に証言をしに来られた元慰安婦の方々のためにボランティアで通訳をしたことがあります。そして白いチマチョゴリを着て泣き叫ぶ元慰安婦の方の証言を聞きながら涙した経験があります。この時から慰安婦問題はこの25年間、私の頭の中から消え去ったことはありませんでした。
帰国後は、慰安婦問題を巡っての支援活動のあり方に矛盾を感じ、また活動に加わる特別な機会もなかったため、長い間見守るだけでしたが、10年前に慰安婦問題に関する初めての本を書くまでに、水曜デモに参加したり、「ナヌムの家」を訪ねて慰安婦の方々と話をしたりしたこともあります。
2)その後2004年に、ナショナリズムを超えて日韓問題を議論する日韓有識者のグループを作ることになるのですが、私がこのグループを作るようになった最も重要な契機も、実は慰安婦問題にありました。新しい歴史教科書採択に反対する会の代表でもあった小森陽一・東京大学教授と意気投合してこの会を作りましたが、わたしが誰にも先にこの会に参加してほしいとお願いした方が、日本を代表するフェミニスト学者の上野千鶴子教授だったのも、そのためでした。
そして翌年、同じように長年、慰安婦問題解決のために先頭に立って活動してこられた和田春樹教授と上野教授をソウルに招いてシンポジウムを開きました。この時私は、この方々の話に対するコメントを、慰安婦支援団体の韓国挺身隊問題対策協議会の事務局長だった尹美香氏にお願いしました。挺身隊問題対策協議会が、和田教授が中心となって活動していたアジア女性基金を非難してきたため、両者の接点を見いだそうとしたからです(この時の内容は『東アジア歴史認識のメタヒストリー』という本に収録されています)。しかしこの時、尹美香氏はこれまでと同じ主張を繰り返すのみで、結局接点を探すことはできませんでした。
3)実は私はシンポジウムの少し前の秋に『和解のために-教科書・慰安婦・靖国・独島』という本を出版していました(慰安婦問題関連は第二章。参考資料98.)。挺身隊問題対策協議会の活動の問題点や、それまで知られていなかった、世間に知られているものとは異なる元慰安婦の方々の声をより多くの人々に知ってもらい、この問題をみんなで改めて考えてみないといけないと思ってのことでした。
私がこの本で強調したことは,「対立する問題を解決するためには、まず、その問題に関する正確な情報が必要。支援団体がマスコミと国民に出す情報が必ずしも正確でもなく一貫性がないので、まず正確に知ろう。そのあと議論し直したい」ということでした。
そして韓国社会は私の本をとこれといった拒否反応なしに受け入れてくれました。いくつかのメディアに書評が載り、翌年には文化観光部が選ぶ優秀教養図書に指定されたりもしました(参考資料86,87)。
4)翌年『和解のために』が日本語に翻訳されてから、日本での発言機会も多くなりました。そのたびに私は、慰安婦問題解決に日本がもう一度向き合うべきだと言いました。1995年に設立された日本のアジア女性基金は、2003年までにいくつかの国の元慰安婦の方々に日本の首相からの手紙を添えた「償い金」を渡し、医療福祉の支援をしてから、2007年に解散していました。その後、慰安婦問題への日本の関心が急激に冷めたように感じたためです。
例えば2010年、日韓併合100周年になった年に、その年にすべきことがいろいろ議論されましたが、日本政府はいうまでもなく韓国政府さえも慰安婦問題に言及しませんでした。そこで私は日本のメディアに向けてその年に「日本がすべきもっとも重要なことは慰安婦問題の解決」と書きました(参考資料59.)。
5)そして、翌年の2011年冬、やはり日本のメディアに慰安婦問題について論じた、日本の保守層と政府と支援団体に向けての文を連載し始めました(WEBRONZA 2011/12~2012/6)。2年後に韓国で先に出版された『帝国の慰安婦』には、この時連載した内容も韓国語に翻訳され収録されています。
つまり、『帝国の慰安婦』は、慰安婦問題に無関心だった日本に向けて、慰安婦問題を思い起こしてもらい、解決に乗り出すべきだと促すために書き始めた本です。しかし日本のみならず韓国でもこの問題を考え直すことが急務だと思い、結局先に出したのは韓国語版です。まさにそのために、当初は日韓両国で同時に出したかったのです。慰安婦問題解決のために長年尽力してきた日本の和田春樹教授が、私が起訴されたあと「日本で慰安婦問題を喚起させる機能がある」と言及されたことは、私の努力が無駄ではなかったということを証明します(記事)。
6)まだこの文章を連載中だった2012年春、今度は日本で、私が2005年に試みたように、この問題の解決にともに関心を持っていながら方法において意見が異なる人々を呼んで接点を探ろうとするシンポジウムがありました。私も和田教授と一緒に招待され、和田教授と似た立場から意見を述べました(参考資料162)。
このシンポジウムのタイトルが「慰安婦問題解決のために」で、主催した人たちが、韓国の挺身隊問題対策協議会で活動していた人や、早くから慰安婦問題に関心を持ち、韓国挺身隊問題対策協議会の初代代表の尹貞玉教授とも親しい女性学者だったということは、その方々が、私の立場が和田教授に近い、つまり慰安婦問題解決のために、それなりに苦心してきた人物と理解してくれたゆえのことといえます。
7)2012年春、日本が謝罪・補償の案を持ちかけたのに対して、青瓦台(大統領公邸)関係者が支援団体の反対を予想して、慰安婦の当事者はもちろん支援団体に打診さえせずに拒否したという記事を見て、私はこのままだと慰安婦問題は永遠に解決できないと考えました。そこで、韓国に向けての本を書き始め、既に書いてあった日本語の文章も翻訳して収録しました。それが1年後、2013年に発刊された『帝国の慰安婦』です。
この頃私は、サバティカルを迎えて東京にいましたが、この時、長年交流して来た数人の学者たちと、慰安婦問題解決のための議論を数回行いました。そして帰国直前に東京大学で、またもや接点を探るためのセミナーを開いたりしました。
告訴の直後に書いたように(参考45-50)、『帝国の慰安婦』における私の関心は既存の「常識」を見直して、それに基づいて「異なる解決法」があるかどうか考えることでした。その悩みを共有することを通して、慰安婦問題をめぐる韓国人の関心と理解がより深まり、より多くの人々が納得できる解決策を模索し、元慰安婦の方々を一日でも早く楽にしてあげることでした。
そして、この本での具体的な提案は、単に「元慰安婦の方々の様々な証言が、慰安婦問題とその解決のための議論から排除されている。当事者を含む日韓協議体を作り、日本と話し合おう」と言うものでした。
裁判長、
慰安婦問題を知るようになってから、この問題における私の関心と行動と執筆は全て、元慰安婦の方々のためのものでした。既存の常識への異議申し立ては、学者としての当然のことであると同時に、韓国に居ながら日本について教える日本学専門家としての義務と考えていたためでもありました。何よりも、事態を正確に知ってこそ、生産的な対話の始まりと正しい批判が可能だということが、日韓関係に関する初めての本を出した時から、私の一貫した考えでした。『帝国の慰安婦』もまた、そうした考えから書かれた本です。
2.「元慰安婦の方々を非難する日本の右翼を代弁する」という主張に対して――日本の評価
ところで原告側弁護人と検察は、私の本に、日本の責任を免罪する意図があると非難します。私の本が日本の右翼を代弁し、太平洋戦争を美化したとする虚言に加えて、慰安婦問題の解決に「害悪」になる本とまで言いました。『帝国の慰安婦』を、学生たちを動員して分析させた「ナヌムの家」の顧問弁護士は、もう10年前の本『和解のために』を持ち出し、青少年に有害な図書だとして、政府に対して10年前の「優秀教養図書」指定を取り消すよう働きかけました。
しかし支援団体が刑事告訴するまでは、『帝国の慰安婦』もまた、期待以上の好評を得ています(参考資料5-12、新聞書評など)。
日本の責任を免除しようとしていると原告側から非難されましたが、重要なのは日本で私の本がどのように受け入れられているかでしょう。結論を先に言いますと、私の本を高く評価してくれた方々は、原告側が主張するような、(日本の)責任を否定する右翼ではなく、日本の責任を誰より深く認識してきた、いわゆる「良心的」な知識人と市民です。
そのことは、まず2014年秋に日本語版が出版された時、一番先に書評を載せたメディアが、この問題に長い間、最も高い関心を払ってきた朝日新聞だということからわかります。朝日よりもっとリベラルと認められている東京新聞、そしてリベラル中道と言われる毎日新聞も書評、コラムなどを通じて肯定的に言及した事実が、そのことを証明してくれています。
そのような記事が私の本をどのように評価したのか、原告側の嘘を明らかにするため、審査評、学者と作家の書評を一部読ませて頂きます。
軍に代表される公権力によって拉致され性的奉仕を強制された多くの被害者の声に耳を傾けようとする姿勢のかげには、単純な戦時下の人権侵害とする見方よりも、植民地主義、帝国主義にまで視野を広げて問題をとらえる鋭さが隠れている。それは戦時下の人権侵害的犯罪というとらえ方よりも厳しい問いを含んでいると言わなければならない。朴裕河は過去を美化し肯定しようとする歴史修正主義者の視点とは正反対のまなざしを慰安婦被害者に注いでいるのだ。(中沢ケイ「帝国の慰安婦が問いかけるもの」、WEBRONZA 2016年1月18日・作家、法政大学教授、2014)
女性を「手段化」「モノ化」「道具化」する構造への強い批判とともに、その中で人間として生きている 人々への共感を表す。これがこの本の叙述の中核である。(田中明彦、東京大学名誉教授、アジア太平洋賞審査評、2015年11月11日付毎日新聞)(参考資料71,72)
本書の 評価すべき点は、「帝国」すなわち植民地支配の罪を全面に出したところにある と思ってます。(上野千鶴子、東京大学名誉教授、2016、「『慰安婦問題』にどう向き合うか―朴裕河氏の論著とその評価を素材に」から)
マクロ な規定性を見据えながらもミクロ的な人々の生きざまを見ていくことこそが、そこに介在 するメゾレベルの状況をつぶさに 見ていくことが植民地支配を考える視点なのではないか、そうしないと植民地支配の暴力性は本当に は見えてこないという現在の植民地研究の一つの流れを朴裕河氏はくんで いる、と私は考える。(蘭信三、上智大学教授、2016、「『慰安婦問題』にどう向き合うか―朴裕河氏の論著とその評価を素材に」から)
かつて 欧米に追随し、強者としてアジアを支配した日本は、他者を支配する西洋起源の思想を越え、国際社会を平和共存へ導く 新たな価値観を示せるか 。韓国の理解を得て挑みたいものである 。(「風知草 帝国の慰安婦再読」2015年7月27日、毎日新聞)
以上が『帝国の慰安婦』に対する日本での論評の一部です。
にもかかわらず検察と原告弁護人は、いや彼らに論旨を提供した人々は、韓国が日本の事情をあまり知らないことを利用して、事態を正反対に歪曲して伝えてきました。
彼らの言う通り、一部の保守が自分たちの主張に私の本を利用した場合もありましたが、微々たるものです。いずれの保守系新聞もこの本の書評を載せてはいませんし、賞を与えるなどというところもありませんでした。
それなのに、この本は、二つの賞の受賞が意識されたたかのように、受賞の直後に起訴されました。そしてそれを引き受けて日本の代表的知識人たちが起訴反対声明を出すと、早くも『和解のために』の日本語版が出た後の2007年頃から私を非難してきた在日朝鮮人研究者や、日本人を含む支援者側の研究者や活動家たちが私の本を歪曲しつつ激しい非難を始めました。
するとこれを見かねた日本の知識人たちが、以下のように発言してくれました。
「『帝国の慰安婦』は、民族とジェンダーが錯綜する植民地支配という大きな枠組みで、国家責任を問う道を開いた」(加納実紀代、敬和学園大学教授、2016、「『慰安婦問題』にどう向き合うか―朴裕河氏の論著とその評価を素材に」から)
「こうした構造にこそ、植民地支配と戦争の大きな罪、そして女性の悲哀があったと私は思う。私は朴裕河氏が「同
志的関係」という言葉にこめた意味をそう解釈した」(若宮啓文、元朝日新聞主筆、2016、「『慰安婦問題』にどう向き合うか―朴裕河氏の論著とその評価を素材に」から)
「「日本の兔罪を意図するものではないことは、先入観を抜きに全体を読みさえすれば、誤解が生じるはずはない 。それうぃ「日本の兔罪」に道を開く妥協的は書物だと理解する 一部の 読みは、明らかに「誤読」であり、同書を「悪用」することだ」
こうした側面の強調は、「植民地支配」のより深い理解に道を拓きはしても、「日本の兔罪」を導き出すようなものでは ない」(西成彦、立命館大学教授、 「『慰安婦問題』にどう向き合うか―朴裕河氏の論著とその評価を素材に」から)
などです。こうした評価が、『帝国の慰安婦』の日本への批判をきちんと受け止めてのものであることは言うまでもありません。まさに、その部分こそが私の本が日本で評価された理由と私は考えます。
そして慰安婦問題解決の過程において、私の本がどのように位置づけられるべきかを論文に書いてくれた学者もいます(参考資料69,108)。また、これら以外にも同じような視点で『帝国の慰安婦』を支持する文章を集めた本が来年春に出版されると聞いています。
私の本は元慰安婦の方を「名誉毀損する本ではない」とする、日本の知識人たちの起訴反対声明に、河野談話を発表した河野洋平・元官房長官、村山談話を発表した村山富市・元首相、そして日本の「良心的」知識人を代表するノーベル賞作家の大江健三郎氏も賛同してくれました(参考資料73-1,2)。それは、その方たちが私の本を”正しく”読んでくれたからです。
告訴直後、まだ本が日本語に翻訳される前に自国を批判してきた日本の代表的思想家、柄谷行人さんが私に関するメッセージを仮処分の法廷に送ってくれたことも(参考資料140)、私のこれまでの仕事をよく理解し、認めてくれたゆえのことと思います。
それなのに原告側弁護人と検察は、私が日本の責任を否定して兔罪しようしていると主張します。もちろん彼らが、本事件の論点と関係がないにもかかわらずそうした主張を繰り返す目的は、朴裕河は日本からお金をもらって元慰安婦の方々を懐柔するような人物といった認識を拡散させたように、私に対する世間の評判を悪くして、私に元慰安婦の方々を名誉毀損するような「故意」がある人物と見せるためです。
3.慰安婦の名誉を毀損する本であるという主張に対して――韓国の評価
裁判長、しかし私の本が決して元慰安婦の方々を名誉毀損する本ではありえないことは、本を書くまでの経過と、そして2013年、発刊直後の韓国社会の反応、先に申し上げた2014年のシンポジウムについての韓国マスコミの反応だけでも十分に理解して下さると思います。
そして告発後も、すべてを把握できないほど多い、市民、知識人からの嘆願書、声明、書評、フェイスブックでの発言、有力雑誌の特集や記事、そして真実を伝えようとした記者たちの書評と記事が証明してくれています(参考資料4-34,36-44,66-2,73-1,2,75,76-1-10,79-85,91-95,124-139,142-155.)
訴訟の問題を見抜いた市民たちが集まり、支持と応援のためのグループを作り、フェイスブックに「帝国の慰安婦、法廷から広場へ」というページを開設して私をめぐる誤解を解くために努力してくれました。このページに、現在まで2000人近い人々が呼応してくれています。また昨日、私のための嘆願書が、ある若い評論家によって新たに作成され、賛同者の署名を募っている最中です。数は決して多くありませんが、私はそのような方々がいるからこそ、この国を去りたいとは考えずに、耐えてきました。
裁判長、
私のための嘆願や、メディアに記事を書いてくれた方々が主にテキストを読み分析し、書くことを仕事とする韓国文学研究者、評論家、作家であるということに注目して下さい。
多くの人々が読んでくれることを願って一般書として書きましたが、実は私の本は内容も文体も単純ではありません。したがって重要なことは、事実か否か以前に、本で私が何を言っているかを正確に把握することです。私たちはそれを読解力と言います。その読解力で韓国でも指折り数えられるほど優れた方々が、私の本を正確に読んで下さり、支持してくれました。
原告側弁護人と検察は私に名誉毀損の「意図」があるかのように疑って本を歪曲しましたが、私の本が彼らの言うような本であったなら、発刊直後にそのまま無視されたか、メディアが彼らより先に非難したはずです。
告訴後はもちろん、告訴前に出た批判に対しても、私はもうそのほとんどに答えています。(イ・ジェスン、「若い学者」たち、鄭栄桓、「帝国の弁護人」著者に対する反論。参考資料62-1-4,102-105.106,110、リンク)。支援団体だけではなく学者さえもどのような嘘をついたのか、多読家としても著名なある作家と私が反論した資料を読んで下さい(参考資料110,132)。まだメモ程度の文もありますが、彼らがどのように曲解しているのかお分かりになると思います。
4. 異なる声の抑圧――告発理由
ところで、原告側代理人はなぜ発刊後10ヶ月もの間沈黙していて、突然告訴をしたのでしょうか?
その直接の理由は、二つあります。一つは慰安婦の方の声を世の中に伝えるために有志とともに開いた2014年春のシンポジウムです。そして、告訴を前倒ししたのは、本を出した後、私がナヌムの家に暮らしている方をはじめとした慰安婦の方々の中で最も親しくしていた方が亡くなったからだと思います。実際に告訴状には、『和解のために』と、シンポジウムについて言及しながら、朴裕河の今後の活動を阻止しなくてはいけないと書いてありました。(参考資料)
彼らは私が慰安婦の方々と会うのを阻止したかったのです。彼らが本の仮処分のみならず、慰安婦の方々への接近禁止の仮処分まで申し立てた理由はそこにあります。そのように慰安婦の方々を独占したにもかかわらず、彼らは私の本に生前の慰安婦の方々の声が存在せず、空しい本だと主張します。
しかし、私が本を書く期間に慰安婦の方に会わなかったのは、慰安婦の方の証言が、時間が経つにつれて初期の頃と変わることがあったため、以前に出された証言集などが現在の証言よりも事態の把握に役立つと考えたからです。また、日韓関係が日に日に険悪になり、慰安婦の方々がこの世を去っていく中、一日でも早く本を世に送り出し、再び議論しなければ慰安婦問題は解決されないと思ったからでもあります。もちろん、それ以前に、昔会った方々との対話は私の中にしっかり残っていました。
本を出してから、慰安婦の方々に会い始めたのは、謝罪と補償について慰安婦の方がどのような考えを持っているのか直接聞いてみたかったからです。しかし、連絡先を簡単に知ることは不可能であり、挺身隊対策協議会の水曜デモに出てくる方々たちは一般人の接近が徹底的に遮断されていました。そのような制限があったため、会うことができたのは結局数人だけですが、会った方々は、私自身が驚くほど、本に書いた支援団体への批判が、他でもない慰安婦の方々の考えでもあったとことを教えてくれました。
一人の慰安婦の方は私にこのようにおっしゃいました。
「日本が本当にやる気があれば、慰安婦たちに直接謝罪して、慰安婦たちに直接お金をくれないと。なぜ、挺対協を通して」進めるのかと言いながら、「立法とかいうけど、なんのことだ…そんなものは必要ない。慰安婦たちにこう、直接、私たち、住所もあるし、電話番号もあるでしょう。それを教えてあげて」、「この方法で準備したから受け取りたい慰安婦の方たちは受け取ってください」とすれば、「受け取らない人がいたとしてこれで終了ですといえば、みんなもらうでしょう。ぜひ、そうなるようにしてください」とおっしゃいました。(参考資料65、ウ・ヨンジェさんの映像)
また別の方は、アジア女性基金についても知っているか、日本のどんな謝罪と補償を望むのか、法的責任について知っているかを尋ねると、「法的とかそういうのは、私達はわからない、それよりもまずは補償してくれれば」いいとおっしゃいました。(ハ・ジョムヨンさん、2014年シンポジウム映像、参考資料166)
要するに、20年以上支援団体が「被害者=慰安婦の方の考え」だとしながら主張してきた、さらに検察が本事件の争点とは何の関係もないのに私が否定したと批判してきた、日本の「法的責任」について、まったく認知していない方が少なくなかったということです。「朴裕河が日本から20億ウォンをもらってくれると言った」との偽証をしたユ・ヒナムさんでさえ、本当は私に、挺対協を批判しながら、補償さえしてくれればいいのにとおっしゃいました。
それで私はそのような声を世に送り出すことにしたのです。先に話した、2014年4月末に開いた「慰安婦問題 第三の声」というタイトルのシンポジウムでのことです。(参考資料35、映像資料追加)
日本から和田春樹教授、釜山在住の支援団体長、そして私が報告をしたこのシンポジウムは、実は私が費用を負担したものでした。
もちろん、わたしにはお金がありあまっているわけではありません。しかし、必要性を感じたので、個人的には大きな負担でしたが、葬られた慰安婦の方々の声が世の中に伝われば、その声を聞いた人たちが再び議論を始めてくれるだろうと考えたからです。そして期待以上に、初めて公的な場に出た「異なる」声に、日韓両国のメディアは大きく注目してくれました。(記事)
しかし、この時の映像を見るとわかりますが、ここに出てきた慰安婦の方々は全て顔をモザイク処理し、声も変えています。それはもちろん、その方たちが、自分が誰なのか知られるのを恐れたためです。
どうしてそのようなことが起きなければならなかったのでしょう?なぜ、彼女達は自分の考えを、日本への抗議デモに出てくる他の方のように堂々と顔を出して話せなかったのでしょう?
もちろん私たちはその理由を知っています。そのような発言が支援団体によって禁止されていたからです。慰安婦の方々の恐怖は、正確に言えば、禁じられていたことを破った時に不利益を被ることに対してのものであるのは言うまでもないでしょう。
裁判長、
6ヶ月間にわたる通話記録ですので、長いですが、参考資料として提出したペ・チュニさんの録音記録を読んでいただきたくお願いします(参考資料77)。私と電話で話す時、ペさんが何度も、スタッフが隠れて聞いていないかを確認し、気にしている様子も確認できるはずです。
私がこのような話をするのは、私に慰安婦の方を批判しようとする故意のようなものがある理由がないと申し上げたいからですが、後でお話しするように、慰安婦の方もまた、この問題に関して自由には発言できないという事実を知ることこそが、この告訴事態に対する正しい判断を可能にするものと考えるからです。
支援団体関係者が外部流出を止めようとしたのは、謝罪と補償についての慰安婦の方たちの考えだけではありません。支援団体が長い間メディアと国民に向けて話してきたもの、すでに一つのイメージとして定着した「軍人に強制的に連れて行かれた少女」というイメージに亀裂が生じる証言こそが、彼らが私を告訴までしながら阻止しようとした内容です(挺対協も告訴を検討したと聞きました)。
前の公判ですでにご覧になったように、ペ・チュニさんは、動員状況と慰安所での生活と朝鮮人慰安婦について、「強制連行はなかったと思う。慰安婦は軍人を世話する者だった。かっぽう着を着て、軍人のための千人針をもらった。日本を許したいが、それを話すことはできない」とおっしゃいました。(参考資料4他)
そして、早くに両親を亡くして祖母と暮らしていたが、職業紹介所に行ったと言いました(参考資料77)。そして、「日本政府は絶対にそのようなことをやっていない」、「日本人が捕まえて行ったというようなことはない」(参考資料77、90ページ)とまでおっしゃったのです。あまりにも確信に満ちた発言だったので、かえって私の方が、他にいろいろなケースがあるのでは?と話したほどです。
慰安婦動員に詐欺的な手法が多く使われたということは、周知の事実です。しかし、だましたのは日本軍ではない、業者とさらに職業紹介所でもあったということが提出した証言資料に出ています。それで当時の植民地警察も問題視して、女性がだまされて売られることがないよう取り締まったのです。(証拠資料3-1)
さらに、彼らの言う「生存中の慰安婦」の方々が暮らすナヌムの家の、別の方の口述録を見ると、これは原告側が提出した資料ですが、いわゆる「軍人が強制連行」したのは一人もいません。イ・オクソンさんは見ず知らずの朝鮮人による拉致、キム・グンジャさんは養父による人身売買、キム・スンオクさんは父親が勧めた人身売買、カン・イルチュルさんは義兄による「報国隊」の名の下で行ったケース、パク・オクソンさんは自ら行きだまされたケースです(証拠資料50ほか)。カン・イルチュルさんが「報国隊」に行ったと話したのは、カンさんをめぐる動員が募集当時からすでに「愛国」の枠組みの中でのものだったことを教えてくれます。
裁判長、私が『帝国の慰安婦』を通じて試したのは、そのような方々、自分の体験をあるがままに話すことができなかった、あるいは話したけれども忘れられた声を、ただ復元し、世の中の人々が聞くことができる空間へ送り出すことでした。
もちろん、そのような声だけが本当の真実だと主張するためではありません。慰安婦の方々をめぐる問題なのに、慰安婦問題が、当事者の一部を排除して進められる状況を見ながら、意図的か否かにかかわらず、沈黙してきた方の声も含めて一度は聞かなくてはならないと思ったのです。そして、当事者間の考えが違うなら、周囲の人ももう一度考えてみよう、ただそれだけでした。先のシンポジウムでもそのような提案を具体的にしました。
そして、私の気持がどういうものだったのか、ペ・チュニさんは正確に分かってくれました。私は結局その方を世の中に堂々と招いてあげることができませんでしたが、そんな私に「先生の気持は分かっているよ」(資料77、55ページ)「世話になってばかりだ」(同資料68ページ)と話してくださったのです。そして、その言葉に私は慰められながらも、深い申し訳なさに陥るのです。(参考資料113-118、リンク)
しかし、それ以後、私はもうそのような活動を続けることはできませんでした。私と最も緊密な対話を交わし、シンポジウムにも映像で声を届けてくださったペ・チュニさんが、シンポジウム後1ヶ月あまりで亡くなり、私もまたそれからわずか1週間後に訴えられたからです。
5.検察・原告側の誤読
裁判長、
『帝国の慰安婦』が虚偽ではないという事実を証明するための資料はすでに十分過ぎるほど提出したかと思います。しかし、重要な点を少しだけ付け加えます。まず、検察が問題にしている「矜持」と「同志的関係」について、もう一度簡単に説明します。
1)「矜持」の対象
まず、意図的あるいは無意識的な誤読についてです。
検察は私の本が慰安婦の「自負的愛国心」を語っていると言います。しかし、私は本にそのように書いたことはありません。『帝国の慰安婦』で「矜持」、「自負」という言葉は全て、「愛国」自体というより、どんな役割であっても自分が必要とされる場で感じる、自分の存在価値についての自負心という意味で使っています。例えば、私はこのように書いています。
それは不条理な国家の策略だったことは明確だが、外国で悲惨で暗い生活をしていた彼女たちにとって、その役割は自分に対する矜持となり、生きていく力になったであろう。そのような社会的認定は苦しい毎日を忘れ、生きていく上でも必要だったことだろう。「シンガポール近くには6000余りのからゆきさんがいて、1年に1000ドルを稼ぎ、その金を日本人が借りて商売」をしたという話は、海外のからゆきさんが日本国家の国民として堂々と生きていたことが教えてくれる。
からゆきさんの場合ですが、この文で重要なのは矜持という感情自体であり、その内容ではありません。私ははっきりと、矜持を持たせるのは、その「役割」だと書き、「社会的認定」と説明し直しています。そして、「国民」として堂々と生きることができたと書きました。要するに、貧困と娘を売るような家父長制と、あるいは「売春婦」として社会から排除され差別されていた位置を離れ、「国民」の一人として同等に扱われることによる感情自体が、私が言うところの「矜持」なのです。やっていることがなんであれ、「自分の存在を肯定する感情」、私はそれを矜持と言ったのです。矜持の対象は愛国心ではなく自分自身です。
他の文章でも、「彼女たちが”皇国臣民ノ誓詞”を覚え、特別な日には”国防婦人会”の服を着て、着物の上に帯を締めて参加したのは、あくまでも”国家が勝手に押し付けた役割」だと明確に強調し、続けてそのような行為が持つ誰かを慰労する役割について「彼女たちが置かれた過酷な生活に耐えしのぶ力になり得たということは十分に想像できる」と書いたように、「矜持」はあくまでも自分の存在に対する矜持でしかないのです。
自分の存在に対する意味付けが、人間が生きていくために必要不可欠なことだというのは、あえて言うまでもないでしょう。極端なことを言えば、その内容はなんだっていいのです。
告訴者と代理人と検察がこの部分を慰安婦が「愛国自体に矜持を持った」と解釈するのは、文脈を正確に把握できていない、誤読です。
たとえ愛国心自体に対する矜持と判断したとしても、それは構造的に強制された愛国に過ぎず、検察が主張する自発的/自負的愛国とは異なるものだということも、すでに申し上げました。
2)「同志的関係」の概念の意図
検察は私の本が日本軍との違い、日本人慰安婦との違いを消去したとしながら、「同志的関係」という言葉が慰安婦の名誉を傷つけたと言います。しかし、例えば、
表面的には「同志」的関係だったとしても、「朝鮮人のくせに包帯を上手に巻くことができるのか?」と(軍医が)考えていることからも、差別感情がベースになっていた。しかし、そのような隠された差別感情を知るためにも「朝鮮人慰安婦」という存在の多面性はむしろ直視されなくてはいけない。明確に見ることだけが、責任を負うべき責任主体と被害者の関係性を明確にしてくれるからだ。
と書いたことにも、私の意図を読み取ることができると思います。
さらに、「何よりも、”同志”的関係を記憶し、その記憶だけに固執した彼等を無条件に糾弾し拒否するのではなく、正しく応答し対話するためにも事実をあるがままに見なくてはいけない。慰安婦の苦痛を理解できない彼等をきちんと批判するためにも、彼らの内面に存在した差別意識を指摘するためにも、”同志的関係”はまず認める必要があった」と、「同志的関係」という言葉をあえて使う理由についても明らかにしました。
言いかえれば、検察が言うように、朝鮮と日本を同じように扱い、日本の責任を免罪しようとしたのではなく、むしろ目に映らない差異を見るために「帝国日本の構成員」という範疇-同質性を見ようとしたのであり、そのような論旨が日本の謝罪意識を引き出すことができるのを期待したのです。
まさに、日本に向かって書いた部分で「彼女たちは生命の危険の中で時には運命の「同族」(古山高麗雄『白い田圃』、14ページ)として日本の戦争をともに遂行する者でもあった」と書きながら、続けて「そのような意味で彼女たちに送られるべき言葉は、時に彼女たちに暴力を行使し過酷に扱ったことに対する謝罪の表現でなければいけない。軍人の暴力は、表面的には「内鮮一体」であっても、差別構造を温存させた日本の植民地政策がもたらしたものだった(162ページ)」と強調したのです。
6.支援団体・検察・学者の欺瞞と忘却
裁判長、
ここでは彼らが「虚偽」だと主張する三つの論点についてもう少し付け加えます。
1)売春/強制 日本人慰安婦の差異化
私は慰安所のことを「管理売春」であり、「強要された売春」であると言いました。そして、この部分については検察と原告側代理人ももはや反論していません。
ところが、挺身隊問題対策協議会の代表だった尹貞玉教授も、ハンギョレに連載された有名なルポ記事で、「売春を強要された」と言っています。(1990年1月4日付ハンギョレ新聞、韓国挺身隊問題対策協議会研究報告書『日本軍慰安婦新聞記事資料集』、2004、45,46ページ追加)
そして、この資料を含むこの報告書は、「京城地法日本軍慰安婦関連判決文」というタイトルで1930年代後半の裁判資料をまとめていますが、ここには戸籍謄本や印鑑証明等を偽造して連れて行った「私文書偽造行為詐欺」、「満洲にお嫁に行くとだまして酌婦契約」した「詐欺」、「人事紹介業者に長女の娼婦斡旋を依頼」した「詐欺」、「内縁の妻を酌婦に受け渡し、その利益を得」(41ページ)ようとした「営利誘拐詐欺」、「営利誘拐私文書偽造詐欺」等が列挙されています。
この資料と報告書のまえがきにある「朝鮮社会の貧困化とそれにともなう女性の深刻な人身売買を見ることができる」「相当数の女性が満洲に売られたという記事が出て」いるということは、支援団体が早くから慰安所の形態が管理売春であり、必ずしも軍人による強制連行ではなかったという事実を知っていたことを示すものです。2004年、もう12年も前のことです。
それでも支援団体と関連研究者達は長い間、メディアや国民にはこのような事実を隠し、「強制連行」と「総督府命令を受けた銃剣を携えた巡査」だけを強調してきたのです。その結果がまさに、今年の初めに300万以上が見たという『帰郷』での強制連行の場面です。そして検察の起訴はそのように作られた「国民の常識」を一度も疑わなかった結果だと言わざるを得ません。
また、2009年に発刊された国務総理傘下日帝強占下強制動員被害真相究明委員会が発行した『インドネシア動員女性名簿に関する真相調査』には、ソン・ボクソプという朝鮮人軍属の手帖を基に「光州で従軍慰安婦61人の名簿が確認され、日本帝国主義が韓国人慰安婦をインドネシアスマトラ島にも連行し売春を強要した事実が明らかになった」との新聞記事が収録されています。(1992/1/16、光州毎日)この記事にはまた、慰安婦の中に「3人の既婚女性が含まれていたとソンさんが証言」したと書かれています。
つまり、現在の私たちの記憶は、慰安婦問題発生初期の記憶の忘却とともに作られたものなのです。
どの程度意図されたものだったかはわかりませんが、原告側の代理人と検察は自分たちの無知あるいは欺瞞を隠して、日本人慰安婦は「自発的売春婦」であり、朝鮮人慰安婦は日本軍や総督府関係者によって「強制的に連行された少女」ということばかりを強調します。そして、私の本がそのような考えを否定するとして、私を厳罰に処せよと求めているのです。
しかし、日本人女性の中にも慰安所とは知らずにだまされて行ったケースが少なくなかったというのも最近刊行された日本人研究書でも明らかになりました。(『日本人慰安婦-愛国心と人身売買と』、22‐23ページほか)
また、日本の研究書だけでなく、韓国の報告書も「慰安婦や遊興業等への動員過程で誘拐誘引、就業詐欺、人身売買等、合法不法の各種手法が盛行していた」という指摘をしながら、「日本女性すら日本内務省、外務省が提示した原則が守られていなかった」と指摘しています。(『インドネシア動員女性名簿に関する真相調査』、71ページ、追加資料)
つまり、「日本人慰安婦は自発的売春婦」との検察の断定は何の根拠もありません。
原告代理人は、また、千田夏光の『続従軍慰安婦』を提示しながら、同様に朝鮮人慰安婦は何も知らない少女だったと強調しましたが、同じ本に「29歳の朝鮮人娼婦」(118ページ)も登場していることは言及しません。日本軍は朝鮮人慰安婦を卑下し「朝鮮ピー」と呼びましたが、日本人慰安婦も、卑下する言葉である「ピー」と呼ばれたという事実も、他でもない同じ本に出てきます。(韓国語翻訳書148ページ)
前述のナヌムの家の慰安婦の方々のケースのように、いわゆる強制連行とは異なる状況があっても、原告側はこれについて説明しながら、「イ・オクソンさんは拉致、キム・グンジャさんは軍服を着た人に連行、キム・スンオクさんはだまされて、カン・イルチュルさんは家で軍人と巡査によって強制的に連れて行かれた」とだけ書いています。(追加資料)。つまり、義兄が送ったという事実は隠ぺいし、パク・オクソンさんについてもただ「お金を稼げると思って行った」とだけ記述するだけで、どのように行ったのかについては言及していません。
原告側の代理人たちは、国民に向けて行ってきた長い間の欺瞞を、裁判でも行ったのです。『帝国の慰安婦』仮処分および損害賠償1審の法廷は、このような資料を詳細に見てはいなかったはずです。
2)制服を着た業者、朝鮮の「娘子軍」
裁判長、
前述の公判で軍服を着た業者についての資料を提出しました。その資料について追加説明します。
慰安婦の募集は時期によって形態が少しずつ変わったようです。30年代には主に業者の自主的な募集だったのに対して、日中戦争以降には戦争への国民総動員時代を迎えて「愛国」の枠組みでの動員の度合いが強くなったように見えます。
以前提出した証拠資料45号の中にある植民地時代の朝鮮在住日本人の回想には「金原始彦」という軍属が満洲で「皇軍慰安婦として引率活躍、要員を募集のために、偶々厚昌邑内に帰省」しているとし、「一人でも多くの娘子軍を集め、戦力増強に寄与しなくては、と覇気満々」(証拠資料45)だったと記述しています。
「娘子軍」とは、女性の戦力化を称賛してつけられた名前です。この言葉が業者によって使われていたことは、つまり韓国人の大多数が想像するような「強制連行」とは異なる形で慰安婦の募集が行われた可能性を示すものです。
また、当時軍属には軍服に似た制服が支給されましたが、普段でも制服を着ていた業者を、少女が「軍人」と錯覚した可能性は排除できません。そして彼らの態度によっては「軍人が強制的に連れて行った」とする証言はいくらでもありうると考えます。もちろん、先の公判で申し上げたように、実際の軍人による強制連行の可能性も、私は本の中で否定していません。
強制連行でなくとも、少女と女性の慰安所生活は十分に悲惨です。
なのに、長い歳月、支援団体は募集状況に関して国民とメディア、そして国際社会に向けて強制連行とのみ主張してきて、初期の間違った認識を修正しようとしませんでした。私の本はただそのことを伝え、「再び議論」することを願ってのものでしかありません。
3)軍属としての慰安婦
4回公判で説明したように、指定慰安所にいた慰安婦は「軍属」として待遇されました。そのような状況がわかる資料はこれ以外にも存在します。それだけでも、慰安婦が愛国の枠組みにあったとした私の記述が「虚偽」でないことは明白です。
しかも、私だけではなく、このような状況についてすでに知っていた研究者がいたことを、わたしは最近知りました。
例えば、「慰安婦を看護労働に従事させることは頻繁にあったこと」とし、彼女達が「文書に記載」された理由を「看護婦の仕事をしながら正式に名簿に記録して軍属待遇することが妥当だとの第7方面軍首脳部判断の結果」とし、「留守名簿に記録したということは」「援護と関連した各種処置も受けることができる」とし、「日本帝国の国民として保護を受けることができるという点もある」と、政府支援研究報告書は(『インドネシア動員女性名簿に関する真相調査』、2009)言っています。「植民地女性を相変わらず日本帝国の一単位として認識し、現地にいた日本人女性を組み入れたのと同じように、朝鮮人女性を組み入れたと見られる」というのです。先の公判で提出したように、実際に日本の国会で慰安婦を援護(支援)対象にするための論議が行われたということは、彼らの主張が正しいことを示しています。(証拠資料44)
また、ある日本の軍人が書いた本は、中国に慰安婦が8万人いたと聞いたとして、「県知事の呉錫卿氏が坐りその右に私がおり10名の女性がり囲んでいるもので、女性は着物を着ているが全部朝鮮人」(長嶺秀雄『戦場』、94ページ)と一枚の写真を説明しつつ、フィリピンの「セブ市にいた慰安婦約100名は、特殊看護婦の名で、軍の野戦病院と行動を共にしており、わが第1師団に配属されていました」とし、米軍に包囲された時も「某部隊が、陣内を右往左往している時、この看護婦部隊は毅然として動揺しませんでした(98ページ)」と書いています。
第4回公判で提出した、自分は軍属だったと言ったムン・オクジュさんの手記には慰安婦達が好きな人を「すーちゃん」と言っていたとし、ムンさんが「私たちは大概すーちゃんが一人ずついた」(証拠資料42、韓国語翻訳書87ページ)という記述があります。これも、まさにこうした関係の中で可能だったことなのです。今日この席に出られたイ・ヨンスさんもやはり、好きな人がいたと、私に話されたことがあります。(追加資料)
にもかかわらず、こうした状況を知らないまま、原告側と検察、そして一部の学者は、私の本を「例外の一般化」として、非難し続けてきたのです。
4)小説の使用について
ソウル大の金允植教授が慰安婦に関する韓国の小説に言及し、小説を「証言」とみなしたことを先の公判ですでに話しました。ところが、政府による教科書検定は違憲だと提訴した、いわゆる教科書裁判で有名な家永三郎教授も著書『太平洋戦争』で、私が使用した田村泰次郎の単行本『蝗』や『人間の条件』に触れながら、「高い資料価値が認められる」と書いています(追加資料)。なのに小説を一部使用したという理由で、私の本は「虚偽」だと言ってはばからない検察の発言は、文学に対する無知、そして慎重さに欠ける言葉がさせたものと言わざるを得ません。
7. 帰ってこられなかった慰安婦のために
裁判長、
先に申し上げたように、私もまたかなり早くから慰安婦問題に関心を持ってきました。しかし『帝国の慰安婦』で、具体的に名前を挙げて記述したのはたったひとりです。血を吐くような遺書を書き、インターネットに載せたシム・ミジャさんです。それもその方の慰安婦体験ではなく支援団体批判でしたし、誰も彼女の声を聞こうとしなかったという文脈で言及しました。
したがって、万が一私の本が慰安婦の方を非難した本であったとしても、私の本を読んで具体的に誰かを思い浮かべる人は誰もいないことでしょう。なぜなら、慰安婦体験はひとつではない、ということが私の本の主な論旨のひとつだったからです。
そのうえ多くの方が偽名を使っておられるので、たとえどんな方かを特定しようとしても、可能な構造ではありません。
裁判長、
慰安婦の戦場生活と帰還、あるいは未帰還について書いた第1章の最後に、私はこのように書きました。
「おそらく今私たちが耳を傾けなければならないのは、誰よりも彼女たちの声ではないだろうか。戦場の最前線で日本軍と最後までともにし、命を失った彼女たち―言葉のない彼女たちの声。
日本が謝罪しなければならない対象も、あるいは誰よりも先に彼女たちであるべきなのかもしれない。名前も言葉も失ったまま、性と命を「国家のために」捧げなければならなかった朝鮮の女性たち、「帝国の慰安婦」たちに。(韓国語版『帝国の慰安婦』 104ページ)
私が本を書きながらも頭から離れなかったのは、誰よりも戦場で死んでいった慰安婦たちのことです。当時も記録されず、死んでも他の軍属のように遺族が支援金を受けとることもなかった、そのような慰安婦たちです。差別を受けることを恐れて帰ってこなかった慰安婦です。
それなのにどうして私の本が、生きて帰ってきた生存する慰安婦の方を特定した本になるというのでしょう。私がこの本で考えてみたのは、日本人女性を含む、国家の無謀な支配欲と戦争によって犠牲になったすべての個人のことでした。
8. 「慰安婦の苦痛」は誰が引き起こしたのか
1)当事者が排除された代理告発
裁判長、
ところが、告訴と起訴は不当だというわたしに、原告側代理人と検察は言います。慰安婦の方がつらく感じたのだ、「慰安婦の方」が「苦痛」を感じる限り告発と起訴は当然だ、と。一部の学者さえそのように言います。最近も原告側代理人は私が「もっともらしい話術」で「慰安婦の方の胸に五寸釘」を打ちこんだと話しました。
しかし、慰安婦の方に「五寸釘」を打ちこんだのは一体誰でしょうか。私の本を歪曲して伝え、慰安婦の方に苦痛の思いをさせ、怒りを引き起こしたのは果たして誰でしょう。
私は告発直後にふたりの慰安婦の方と電話で話しました。ひとりはナヌムの家にいた方で、原告として名前が挙がっていた方です。
先に申し上げたように私はナヌムの家の一部の慰安婦の方々と親密に交流し、その中のひとりであるペ・チュニさんとは半年にわたって電話もたびたびしました。会った回数よりも電話のほうが多かったのは、ナヌムの家が私を警戒していたからです。そのためペさんもやはり、会うことに慎重でした。
ところが最も親しかったペさんは、告発の一週間前に亡くなってしまいました。そこで私は嵐のようだった告訴の衝撃が少し通り過ぎてから、ナヌムの家に住むユ・ヒナムさんに電話をかけました。この方もやはり、私と対話をしてきた方で、私が主催したシンポジウムに出る予定だった方だからです。
いったいどういうことなのかをうかがったところ、ユさんはおっしゃいました。
「(私は目が)見えないでしょう、それで(職員が)来て読んでくれたけど、強制連行ではなくて何…ただ行っただとか…まあ、読んでくれたのに、聞いたけど忘れてしまったよ」「なぜそのようなことを本に書いたの」と。(参考資料156)
この方は目が不自由で、私の顔さえはっきり見えないとおっしゃっていた方です。そしてこの言葉から、ユさん自身が読んだのではなく、慰安婦の方々を集めて職員が読んだということがわかります。また、ナヌムの家の安信権所長は今年1月の日本での講演で、慰安婦の方々は高齢で本を読めないから、一部分を抜粋して繰り返し聞かせていたと言いました。つまり慰安婦の方は全体を読んだのではなく、支援団体によって前後の文脈が切り離された、抜粋の文章だけを「聞いた」のです。
聞く行為が本にあっては間接的な行為だというのは言う必要もないでしょう。詳しく読んでも読者の数だけの読解が可能なのが一冊の本です。私のために苦しまれたというナヌムの家の慰安婦の方々の苦痛は、私が引き起こしたのではなく、ナヌムの家の顧問弁護士主導の下で行われた漢陽大法科大学院の学生たちの雑な読解と、それをそのまま伝えたナヌムの家の関係者です。
そこで私がユさんにそのような意図で書いた本ではないと言うと、「意図はそうだけれど…」と言葉を濁しました。ユさんは、私が悪い意図をもって書くような人間ではないとご存知だったからだと思います。
そして3日後、今度は一人暮らしのある方から電話がかかってきました。この方はユ・ヒナムさんから聞いたと怒っていて、そのような本ではないと説明しようとすると、「5人のソウル大教授があなたの本は悪いと言ったよ!」と繰り返し、聞こうとされませんでした。(参考資料157)
裁判長、
私に対する告訴において、慰安婦の方々は当事者ではありません。
すでにおわかりのように、本を読んだのはもちろん、告訴書類の作成、論理構成、私を告訴したすべての主体は周辺の人々です。告訴状に押されている慰安婦の方々の印鑑、同じ形の印鑑をご覧になってください(リンク)。私は、慰安婦の方々の中、2014年6月告訴以前に私の本について知っていた方はいなかったと思います。ペ・チュニさんでさえ、亡くなるまで私に告訴のことなど話していません。
私との親密な交流を知らなかったからでしょうが、ナヌムの家の所長は、ペさんも生きていれば告訴に加わっただろうと言いました。しかし、私との通話記録をご覧になれば、そのようなことなどありえないことがお分かりになると思います。
そのうえ、慰安婦の方々は検察が進めた調停課程をご存知ではありませんでした。私に日本語版の絶版という要求を含む調停案が来たとき、他のことはともかくそれは私が決められることではないと伝えて理解を求めるため、刑事告訴で原告として名前が挙がっていたふたりの方に電話をかけました。
告訴後1年も過ぎた秋の時点だったのに、そのうちのひとりユ・ヒナムさんは親しみを込めて受けてくれました。私の話を聞いて、調停問題のことは安信権所長に話しなさいとおっしゃいました。もうひとりのイ・ヨンスさんは、原告として自分の名前が挙がっていることさえ知ってはいませんでした。
ナヌムの家の安信権所長は、最近提出した嘆願書でも相変わらず嘘やいい加減な記事で私を非難しましたが、慰安婦の方々との通話内容や映像を確認すれば、なぜ彼が嘘までついて私を非難するのかがわかるでしょう。
遅きに失しましたが、告発前後に何があったのか、ようやく書き始めた私の文を御覧ください(『歴史との向き合い方』 )今も出回っている「20億懐柔説」がユ・ヒナムさんの偽証だというのも、ペさんとの通話記録を見ればわかります。そして安信権所長が繰り返し非難してきた、事前の許可なく訪ねてきたとしたNHK問題もやはり、彼の嘘であるとわかるでしょう。必要ならば、安所長と交わした携帯メッセージを提出できます。ペさんは日本人との対話を待っていた方で、記者たちは解決のために努力した人々です。
2)血を吐く声
裁判長、本裁判と関係ないような話まで長々として申し訳ありません。しかし、「法」とは正義と共同善を追求することだと理解しています。私がこのような話をするのは私自身のためでもありますが、それ以上に慰安婦の方々のためのことです。相変らず慰安婦の方々の一部は、世の中に届かない声を持っていますが、依然として世の中に送りだすことができない状況です。ペ・チュニさんとの対話から、それがひしひしとわかりました。
ペさんは、自分の経験が世の中に通用するものとは違うということを口にできず、私と対話するときも誰かが盗み聴いているのではないかと気にしていました。
同時に、支援団体の運動やケアの方法に批判的ながらも、自分の考えを思うままに話すことができませんでした。そして彼女たちの言葉を「半分は嘘」(参考資料77、16ページ)とし、慰安婦の方々の講演料が支援団体の建物に使われることに不満ながらも言えませんでした。私に会えないようにするために、体の状態が良くないのに病院からナヌムの家に無理やり移され、血を吐くように彼らに対する不満を吐露しました。亡くなる1か月前のことです。
「人は助けて命は救っておくべきじゃないか」「どんな人だって、命を救おうとすべきじゃないか」と。
その背景にどんなことがあったのか、通話記録を確認していただければありがたいです。メディアや検察がすべきことは、まさにそんなことではないでしょうか。
そうしてペさんは「敵は100万、私はひとり」と思いながら、孤独な生活の末に亡くなったのです。
実際、似たような言葉で支援団体を非難した方がかつておられました。その方の声を偶然聞いたのが、私が『和解のために』で慰安婦論を書くことになったきっかけのひとつです。2004年のことです。しかしそれから12年が過ぎても、状況は何も変わっていません。
韓国の社会は慰安婦に関心が高いです。しかし、私たちは彼女たちの心からの声を果たして聞いたでしょうか。間に合わなくなる前に、生存している方だけでも、本当の声を聞いてあげられる社会になればと思います。
裁判長、
原告側代理人は、最近提出した書類で「朴裕河の解決策がどんな説得力を持つことができるのか疑問」と言いました。
まさにこの言葉に、この告発と起訴の本質が込められていると考えます。
原告側は、すでに告訴状に明確に表れているように、ただ「異なる声」の拡散を防ごうとしました。以後のやり取りでも、彼らがこだわっているのはひたすらこの部分です。日本の「法的責任」を繰り返し主張した理由もそこにあります。
先に申し上げたように、私が会った慰安婦の方のほとんどは、なぜ解決が遅れているのかを知ってはいませんでした。ただただ、日本が何もせずにいるからだとのみ考えていました。もちろんそれは、関係者が彼女たちに情報を伝えず、当事者の多くを排除したまま自分たちがすべてを主管したからです。
私はそのようなやり方を批判しただけで、彼らの活動のすべてを批判したわけではありません。なのに私を、彼らは国家の力を借りて抑圧し、20年以上情報を共有した結果として支援団体と同じように考えるようになったメディアや国民を動員して、私に石を投げさせました。
3) 攻撃を引き起こす意識
裁判長、
彼らの攻撃は、いろいろな構造が複雑に絡み合わされたものです。
そのうちひとつだけ申し上げるなら、検事や代理人の攻撃、慰安婦は自負心を感じてはいけないと抑圧する考えは、女性差別、売春差別的な考えが生み出したのです。
それは、原告代理人が「被害者の声」として彼の書面で繰り返し記述する表現から明確にわかります。彼は絶えず日本人慰安婦に対して「娼婦」「体を売った」「達磨屋」等々の単語を引用・使用しています。そうして「自発的な売春婦」の日本人慰安婦を、強制的に、あるいはだまされて連れて行かれた朝鮮人慰安婦と私が同一視した、と非難しているのです。
しかし彼のこうした言葉こそ、日本人慰安婦たちが名誉毀損と訴えることができる発言ではないでしょうか。彼の単語の使い方には明確に売春婦に対する差別があり、名誉毀損の条件という「社会的評価を低下させる」認識が存在しているからです。
いわゆる「女工」や「売春婦」たちは、いたしかたなく生き続けた日々の苦痛の中で、1銭、2銭とためて故郷に送りました。そのお金で兄は上級学校に行き、仕事をすることができたのに、妹や姉の恋愛に干渉し、時には暴力や殺人さえいとわなかった心理こそが、長らく韓国社会で慰安婦の「異なる」声を殺してきたのです。同じ考えを内面化した女性たちもまた、韓国社会には少なくありません。
これまで私を罪人扱いし攻撃してきた原告代理人と検事、そして彼らに論旨を提供してきた活動家や一部の学者もやはり、そのような認識の持ち主です。慰安婦を抑圧し、自分の存在に何の意味も感じられないように差別し疎外させ、自殺に追い詰めたりした考えの主犯なのです。
このように私を抑圧する理由はただひとつ、そのような存在たちが自分を居心地悪くさせるからです。
裁判長、
自分たちの告発と起訴によって、また何の確認もなしに報道された記事によって、私が今も日本から金を受け取って慰安婦を懐柔しようとした売国奴であり、スカーフで首をしめて殺したくなる人物としてまで指さされているのに、私に対する非難を止めろという人が彼らの中からひとりも出てこないのはまさにそのためです。
告訴に達するもうひとつの背景には、慰安婦問題をめぐる日韓知識人の考え方の違いがあります。詳しくは申し上げませんが、参考資料とホームページに載せた告発までの経過を御覧ください。(参考資料46)
しかし、知識人間の考え方の違いが、法廷で争われるべきことでしょうか。しかも彼ら自身は現れることのない法廷で、検事と弁護士が代理してやるべきことでしょうか。
4) 攻撃の目的
ところで、彼らがこのように一貫して「自発的にいった人と被強制連行者」の差異を強調する理由はどこにあるのでしょう。どうやって行こうがおしなべて悲惨な状況であったことを、彼ら自身が誰よりもよく知っているはずなのに、差異を主張して私を非難する理由はどこにあるのでしょうか。それは、「強制連行」としなければ、彼らが初期に誤って要求してきた「法的責任」を引き続き問えないからです。自分たちの認識に誤りがあったことが明らかになるのを隠すためです。
裁判長、
支援団体は、国民やメディアが与えた市民権力、学界やメディア権力、そして国連や世界女性と市民連帯に至るまで、大きな力を持っています。支援団体の代表のひとりは、有数の学会の元会長であり、有名なマスメディアの元主筆の奥様であり、ウ・ヨンジェさんが言及した「ソウル大教授」でもあります。そして彼らの後ろには、長い歳月の運動を通して作られた固いつながりだけでなく、長官や国会議員を排出した人脈があります。さらに政府や企業、国民が集めてくれた資金があり、何より仕事をする「人」があります。
しかし、私はもっぱらひとりで、批判者たちが集団になって次々と出してくるすべての攻撃文を分析して反論を出さなければなりませんでした。その作業以上に苦しかったのは、その中に含まれる歪曲や敵愾心、根拠のない嘲笑でした。
彼らはひたすら、自分たちの考えを守るため、それまで国民に向かって行った数多くの矛盾をただ隠すため、運動の邪魔になるという理由で、それまで守ってきた権力と名誉が傷つくことなく維持できるようにするために、私を売国奴、親日派と追い立て排斥してきました。 変ることなく大衆の誤解や過度の非難を、知らぬふりをしました。
さらに、ただこの裁判で勝つために、何の根拠もなく私の本が慰安婦を「歪曲」するために資料を「意図的に」「巧妙に」「徹底して」「繰り返し使用」したとし、私に「悪辣」「残忍」「利己的」「悪意的」との単語まではばからないのです。このような態度や表現が典型的な魔女狩りの手法だということは、すでによくご存じでしょう。
裁判長、
これまで多くの資料と説明で、私の本が虚偽でないと主張してきましたが、本当はこの問題は本の問題でさえありません。
私が訴えられたのは、慰安婦の方々と私が親しく交流すること、それによりナヌムの家の問題が世の中に知られることを恐れたナヌムの家の安信権所長と、彼に同調したナヌムの家の顧問弁護士、そして慰安婦問題についてよく知らないまま、教授が指示した通りにいい加減な読解をもとに本を100か所以上めった切りにするレポートを作成した漢陽大法科大学院生の、反知性的な行為であり、謀略であり、陰湿な攻撃です。
裁判長、
「異なる」声に対する暴力的な抑圧と、それによって引き起こされた言葉に言い表せない苦しみの経験はもう私だけで充分です。
代理人は私を非難し、私を放置すれば「第ニ、第三の朴裕河」が出てくるだろうと言いました。
同じように申し上げたいです。私が言う意味での朴裕河を、いわれなき苦しみを経験する第二、第三の朴裕河を、もうこれ以上は生み出さないでください。
彼らは「厳しく処罰されずうやむやに終わっては」ならないと裁判長を脅迫までしました。彼らが私を処罰して守りたいものが何か、もう理解してくださったと信じています。
裁判長、
彼らの攻撃と告発によって私の学者生活二十数年の名誉が一瞬にしてめちゃめちゃにされ、この2年半もの間苦しみの中を生きてきました。
私は彼らの嘘と歪曲が犯罪的レベルのものと考えましたが、仮処分と損害賠償裁判所はそのような彼らの扇動を検証しませんでした。その結果として韓国の法廷を、世界の笑いものにしました。
ごく少数の人だけが私の本を正しく受け入れてくれ、苦しみながらも多くの人々に助けられてなんとか耐えてきました。告発事態でこうむったわたしの名誉毀損と心の傷は、たとえこの裁判で私が勝訴しても完全に消えることはないでしょう。
「社会的価値が低下」することが名誉毀損の定義だと聞きました。
どうか明晰な判断を下していただき私の名誉を回復させ、大韓民国に正義が生きていることを見せてくださるよう、切にお願い申し上げます。
2016年12月20日
韓国検察、「帝国の慰安婦」著者に懲役3年求刑 [朝日新聞]
[裁判関連] 刑事訴訟 公判記4
11月8日に4回目の公判があった。今回は私と弁護人が提出した書証(主張の根拠を表す資料)を説明する番だった。しかし時間が充分ではなく、5月に提出した43の証拠資料についての説明しかできなかった。ひとつの文書の中でいくつかの資料を示した場合もひとつにまとめたため、実際にはさらに多い。結局参考資料として提出した150あまりの文書については個別に説明できなかった。ペ・チュニさんと交わした会話の映像と起こしたものも参考資料として提出した。
私の本が虚偽ではないことを主張するには協力や自発性自体を主張しなければならなかったため、今回の公判は特に気が重かった。私の本はそうしたことを強調するためのものではなかったからだ。法廷でのやりとりは本の趣旨を狭める行為だった。もちろんそれは私が始めたことではない。
私は、朝鮮人慰安婦問題をめぐる状況を理解しやすいように、資料を時代順に準備した。
日本人慰安婦の資料を最初に持ってきたのはそのためである。そして30年代の人身売買をめぐる状況、40年代の総力戦体制の中で「愛国」の構造が作られていく状況に関する資料をおいた。同時代の軍人や慰安所管理人など周辺の人たち、そして周辺人を尋問した米軍の資料。そして戦後(解放後)の資料と「問題」化された90年代以降の資料をおき、最後に学者たちの意見を追加した。
時間が不十分で裁判所で言えなかったことも、簡単ながら括弧の中に「補足」と記して追加しておいた。
弁護人:貧しい女性が売春業に従事したという事実がクマラスワミ報告書、ICJ勧告書にも出てくる。クマラスワミ報告書には村長が工場の働き口を約束し、また家が貧しくて受け入れたという話が出てくるし、ICJ勧告書でも慰安婦のほとんどは「貧しい小作農家出身」だとしている。また、千田夏光の本では日本軍慰安婦問題が呈する植民地支配問題、家父長制の問題を正確に見ることができないと原告側の告訴補充書に書かれているが、このような問題を指摘したのはまさに被告人だ。その意味では告訴補充書の内容と被告人の『帝国の慰安婦』の内容に大差はない。近代公娼制のもとで形づくられた女性の人身売買メカニズムと農村経済の疲弊から始まった貧困な社会が「慰安婦」動員の背景になったのだ。
それなのになぜ「慰安婦は自発的に行った」と被告人が話したと主張できるのか?検事の論旨ならば慰安婦と「売春」を連係させて言及したクマラスワミはもちろん、政府委員会報告書の作成者、原告側代理人さえこの場に立たなければならない。
検事:『帝国の慰安婦』にはそのように書かれている。
弁護人:起訴内容12番にある「強姦的売春、売春的強姦」の意味は「慰安」とは、売春と強姦の両方が含まれるということだ。クマラスワミ報告書にも「対価として金を受け取ったり、金の代わりに伝票を受けとったりした。戦争が突然終わって自分や家族の食いぶちを稼ぐという希望も意味がなくなってしまった」という慰安婦の証言が引用されている。マクドゥーガル報告書には「性的奴隷には強制売春のほとんどすべての形が含まれる」と書かれている。そして強制売春についても「名誉と尊厳を深く傷つける行為」だと認めた。「戦争法に違反した強制売春、強制強姦」などの表現が出てくる。
また、検察が証拠資料として提出した政府刊行証言集『聞こえますか? 12人の少女の話』にも収益に関する部分が明確に出てくる。ICJ報告書には最初から料金表まで出ている。
裁判官:整理すると弁護人の主張は、『帝国の慰安婦』に出てくる売春、強姦の混用表現がこの本だけではなく、クマラスワミ、マクドゥーガルなどさまざまな国際報告書にも出てくるというものだ。
検事:この本には「慰安婦を否定する人々は慰安婦を売春とだけ考え、私たちは強姦とだけ考えた。しかしそのふたつの要素の両方が含まれていた」という文章が記されている。慰安は売春と強姦のふたつの要素を含んでいるということだ。「慰安」にどんな売春的要素が含まれていたというのか。
弁護人:日本軍は慰安婦を管理売春の形で運営した。その指摘が誤ったものだという話か?
検事:日本軍が体系的な料金・労働時間を策定して慰安婦制度を初めから徹底的に計画・管理していた。弁護人が言った報告書の趣旨は、むしろそれだけ体系的に管理して反人道的な罪を犯したという趣旨に理解される。報告書は売春として認知したという趣旨のものではない。
裁判官:いずれにせよマクドゥーガル報告書にも強制売春という表現が出てくるのではないのか?
検事:慰安婦になったのは自発的なのでなく本人意思に反して、詐欺や誘引という方法によるものだった。これが中心にある。ところがこの本はその事実を否定している。この本で売春も慰安のふたつの要素の中のひとつと書いたのは、慰安は売春であり自発性に基づいたものだという意味だ。これが問題だということだ。
弁護人:被告人が慰安婦の性的奴隷性を否定したということか?しかし被告人は本にこのように書いている。「もちろん慰安婦は自分の体の主ではなかったという点で性的奴隷であることに間違いはない。植民地になった国の民として、日本国民の動員や募集を構造的に拒否できなかった。精神的な自由や権利を奪われたという点では明らかに奴隷だった。彼女たちが総体的な被害者だったことは間違いない」。被告人は性的奴隷性を否定していない。
検事:慰安婦は自発的に行ったのではない。本人の意思に反して行ったものだ。ところで被告人が言う性的奴隷というのは慰安所での生活を指すものだ。私が言う性的奴隷とは本質的に違う。むりやり連れてこられたという話がこの本のどこにあるか?296ページを見てみよう。「自発的売春婦という記憶を否定」。それは私たちが熱心に否定してきたということではないのか?
弁護人:「根本的に売春という枠組みの中にあったとのことを知っていたのだ」という部分も起訴対象になったが、この部分はクマラスワミ報告に対して言及しただけだ。女性たちが騙されて性的奴隷になったということだ。
性的奴隷性を主張したいのなら検察の主張と結局違わない。
起訴された30番を見てみよう。「朝鮮人慰安婦とは、このようにして朝鮮や中国の女性たちが日本の公娼制度に組み入れられたものだ」。この部分も他の学者の言葉を引用した部分なのに起訴された。韓国政府傘下の委員会報告書や発刊書でも、公娼制に組み入れられたという形で、同じ趣旨で説明している。
検事:ならば慰安婦制度は合法か?違う、違法だ。それなのに今このように同じように扱っていたから、名誉を傷つけたと主張している。
裁判官:当時、日本帝国下で公娼は合法だったとわかっている。慰安婦の場合はどうなのか?
検事:当時の国際法上違法だ。(裁判官:では日本の法律上は?)
多くの学者が、日本で未成年者の売春は法律で禁じており、慰安婦には未成年者が多かったため違法だと考えている。
裁判官:慰安婦が違法な制度ということは被告も検事も認めている部分だ。検察は、慰安婦は合法制度ではないのにその制度に慰安婦を組み入れたとの主張だ。
弁護人:合法か違法かがなぜ問題になるのか理解できない。本には「自発的な売春婦というイメージを私たちが否定してきたことは、やはりそのような欲望の記憶と無関係ではない」と書いてある。しかしクマラワスミ報告書を見ると、(1)すでに売春婦であり自発的に仕事をしようと思う女性や少女、(2)食堂や軍人のために料理や洗濯をして高い報酬がもらえる働き口を提供するという術策に騙されて来た女性たち、(3)大規模な強制的・暴力的女性拉致、このように多くのいきさつがあったと書かれている。
慰安婦のイメージを否定してきたという文章はいろいろに解釈できる。何よりこの部分は明らかな引用だ。「彼ら(日本の右翼)が主張する自発的な売春婦」というイメージ。そして私たちが自発的売春婦というイメージを否定してきたことははっきりした事実であるとも解釈することができる。このようにさまざまに解釈できる文章をひたすら「被告人が自発的売春婦だと主張した」ということこそ恣意的なものだ。このような形ならば、クマラスワミ、マクドゥーガル、告訴補充書、さらには各種委員会が発刊した冊子、慰安婦のかたの証言書、これらすべてから部分的に抜粋してあなたの趣旨は売春強調ではないかと言いながら名誉毀損の疑いをかけることができる。
検事:これが引用だという証拠があるのか? 脚注もない。引用したのならば、どこから引用したのか書かなければならない。そしてこの本にはそのように書かれていないが、他の引用には括弧の中に文献名とページが書いている。検察の1人がこの本に問題があると言っているのではない。この本が出た後、多くの歴史学者や研究者が額を突き合わせて討論し出版された本があるが読んだのか?
朴裕河:この部分はまとめのところだ。つまり前に話した内容を振り返ったもので、以前の部分に出てくる「自発性の構造」という節の内容を反芻している。言ってみればその部分の内容を持ってきた部分だったため引用符を打った。文献引用は前の部分にある。
名誉毀損になるならば対象が特定されるべきだが、検察は声を上げた人の数が少なく特定されると言い、女性家族省にある資料に生存している慰安婦の方の名前が出ているとも言った。しかし、その中には偽名を使った方もいらっしゃる。支援団体が出した証言集も同じだ。つまり特定などされない。
韓国挺身隊問題対策協議会が一昨年だったかにソウル市の支援を受けて作った慰安婦問題関連の大学生イベントのポスターには「20万人の朝鮮の少女が連れていかれて、2万人あまりが虐殺され、二百数十人だけが帰ってきた」と書かれている。私は慰安婦の経験をした朝鮮人全体を対象に本を書いた。中でも特に感情移入したのは、戦地で亡くなった方々だった。生き残って声を上げた人だけが被害者であるわけではなく、支援団体の主張によれば20万人にもなるのに、本に書いた話が特定の誰かであるとどうして言えるのか。
昨年日本で『日本人「慰安婦」』という本が出た。サブタイトルは「愛国心と人身売買と」だ。編者は「戦争と女性への暴力」リサーチアクションセンターという、慰安婦問題解決のために永らく努力してきた支援団体だ。日本人慰安婦問題はこれまでとりあげられなかったが、遅ればせながら問題化され始めた。
重要なのは、サブタイトルにあるように慰安婦をめぐって「人身売買と愛国」の枠組みが中心だったという事実が認識され始めたという点だ。表紙には「『売春婦』なら被害者ではないのか?」とも書かれている。まさにこれが私の問題意識でもあった。検察は「売春婦」という言葉に非難を込めて言う。私の本でその単語は引用であるだけだが、何より検察が言うその意味での「売春婦」という言葉は使わなかった。
強制性に関しても、「公的では」なかったと書いた趣旨は、日本軍は慰安所を作って管理もしたが、拉致や術策まで使って連れてこさせたのは日本の公式方針ではなかったという意味だ。
現場に到着した時、幼すぎる子は業者に送り返させたという証言が存在している。よそに就職させたという資料もある。その場合、業者を処罰しなかったのが問題だと言う学者もいるが、業者に制裁を加えなかったと記されているわけでもなく、慰安婦の実質的雇い主は金を与えて買ってきた業者だったのだから、制裁にも限界がありえただろう。植民地や本土の誘拐現場を取り締まるのとは異なる状況と考えなければならない。
そして私はそのような黙認も含めて責任を問うた。私が強調したのは「日本軍による物理的強制連行」が決して慰安婦動員の中心となったのではないということだった。
検事:21才以下は中国などでの移動を許可しなかった。しかしそのような取り締まりは日本本土だけで適用され、植民地では違った。多くの学者がこの本を批判した。
朴裕河:通牒文が植民地で発見されていないからといって、存在しなかったという証拠はない。実際に植民地警察も誘拐などを取り締まっていた。そのような資料は強制性を主張する日本の学者も見ていない可能性が高い。私は25年前に慰安婦の方に会い、10年前に慰安婦問題について本を書いた。検事は短時間で猛勉強されたようだが、知らないことが相変らず多い。それなのに既存の研究や支援団体の話だけを信じるのはなぜなのか? 多くの学者がこの本を批判したと言うが、批判者のうちに慰安婦問題の研究者は少ない。つまり実際の資料に接した人たちではない。私のために証人になると言ってくれている歴史学者もいないわけではない。検察と、両方とも証人を採択しないことにしたのでお願いしなかっただけだ。
検事:被告人は「自発的な売春婦」の引用符が引用の印だと言ったが、その部分の引用符はシングルクォートだ。被告人は他の引用にはダブルクォートを使っていた。だから引用ではなく強調だ。
裁判官:シングルクォートは引用する時も強調する時も使う。検察は引用ではないと言い、被告は引用だという。見解の違いがあるのでこれは判断に任せる問題だろう。
弁護人:では証拠資料に対して説明する。まず証拠第1号、『マリヤの賛歌』。日本人慰安婦が書いた手記だ。日本人も人身売買の枠組みの中にあったことがわかるように提出した。「2,500円貸してもらい、それで神楽坂の借金を返して700円を父にあげて台湾に渡った」と書いてある。
もうひとつの資料は同じ本から抜粋したものだが、日本人女性も一日に何人もの軍人を相手にしたという事実がわかる。被告人が「慰安婦の苦痛は日本人の娼妓と異ならない」と書いた部分についての補足説明資料だ。「1人の女に10人も15人もたかるありさまは、まるで獣と獣との戦いでした」と書いてある。
検事:証拠第1号は日本人慰安婦についての内容であり、この事件の起訴内容とは関係ない。『マリヤの賛歌』が発刊されたのは1971年だ。91年8月の金学順さんの陳述後について書かれたのが『帝国の慰安婦』だ。起訴内容とは無関係だ。
判事:「日本人の娼妓」という起訴箇所に関係する部分であり、差し支えない。
弁護人:証拠2『赤い瓦の家』。日本軍慰安婦になった韓国人女性の話だ。植民地を船で離れる時、日本人女性が2人いたと記している。朝鮮半島に住んでいだ日本人女性も慰安婦になっていたことがわかるように提出した。植民地といっても「日本帝国」の国民になっている以上、軍人が強制的にひっぱていくことができる構造ではなかった。
検事:日本の売春婦は性病感染者が少なくなかった。だから朝鮮人女性がたくさん連れて行かれた。日本の娼妓の一部は金を稼ぐために自発的に慰安婦になった。
(補足:日本人女性でも貧しい家の少女が朝鮮に売られてくることもあった。彼女たちも慰安婦になった。そのような存在が見過ごされている。朝鮮人の少女ももちろん多かったが、結婚して子どもがいる女性もいた。植民地は純潔でなければならないという強迫観念が作った考えだ。当時、朝鮮社会は性病が蔓延して深刻な問題にもなった)
朝鮮人慰安婦と日本人慰安婦は待遇に差があり、直接差別されたりもしたが、家父長制下の貧しい女性だったため動員された構造は同じだった。
裁判官:被告人は避けられない状況でなければ発言しないように。弁論は原則的に弁護人がしなければならない。
弁護人:証拠第3号1、2、3は慰安婦動員が主に人身売買によって成りたち、後半には14才以上40才までの400万人が国家のための勤労奉仕隊などさまざまな名前で総動員されたことがわかる資料だ。この時、遊郭の娼妓まで愛国青年団に加入させられるなど、愛国を強要された。
職業紹介所が騙して送り出した情況、そんな職業紹介所を警察が取り締まった状況、許可を規制しようとする状況などがわかる。植民地の日本人女性も一緒にしたし、「病院船」で仕事をしなければならなかった状況も出てくる。
3-3は、当時の人々が「満州」を夢の地と考えて移住しようとしたことがわかる資料だ。そのような枠組みの中で業者が人身売買などによって女性を集めて連れていった。もちろん依頼を受けた場合もあるが、受ける前から動いていた人々もいる。
当時も詐欺などによる人身売買は処罰された。被告人は戦争を起こして植民地の貧しい女性たちが戦地に動員されたことが植民地化の結果だと考え、そのような情況も構造的強制性だとした。業者への処罰が必要だとしたのは、当時も詐欺による人身売買は違法であり処罰されたからだ。軍の介入自体は充分に述べた。
第4号はペ・チュニさんの映像だ。エプロン(割烹着)をつけて軍人のために千人針を縫ってもらいなどしたことを話し、慰安婦は「軍人を世話する存在」とも言った。
第5号の『聞こえますか?』にも、同じように物理的拉致の主体が日本軍ではなく誘拐犯だという事実が多く記されている。両親のためにこっそり慰安婦になったり、紹介業者を通じてなったりしたケースも多い。紹介所が洗濯婦だと嘘をついた場合もある。
検事:人身売買で来ても黙認した場合が多かった。
裁判官:日本軍が人身売買であるとわかっていて黙認したのか、それとも知らなかったがとにかく慰安婦が必要だったから引き受けたのか?
弁護人:『帝国の慰安婦』には、日本軍は黙認していたしその責任を負わなければならないと記されている。
裁判官:結局、憲兵が来て直接捕まえて行ったのではないから物理的強制性はなく、黙認したことについては責任があると主張したと考えればいいのか?(被告人を見る)
朴裕河:そうだ。しかし、部隊ごとにその処遇には違いがあり、さまざまなケースがあったと考える。軍が管理したというのは、業者を通じて部隊に来た時に業者が契約書を両親から受け取ったのかを確認するのが原則であったという話だ。騙されたと泣く場合は他の所に就職させたり、幼すぎれば送り返したりした場合もあるが、だからといってすべての部隊がそのようなケースで送り返したはいえない。公式的な規律では業者に契約書を確認させた事実があることをいえるだけだ。
裁判官:20万人の慰安婦がいる。8万なのか20万なのかわからないが、その場合は原則通りにしなかったケースだが、原則が守られなかったケースの方が多いのか確認されているのか?
朴裕河:それは確認しえない。
弁護人:『奪われた青春、戻ってこない魂』という証言集には「3~40代に見える男が来て、お腹いっぱいなれるし良い靴もくれる所を教えてあげるからついて来いと言った」と書いてある。行ってみると旅館に農民の娘が14~15人いたという。何のためにどこに連れて行かれるのかもわからずに。錠前がかかっていて逃げられもせず。現場に到着するとカーキ色の軍服を来てゲートルを巻いた3人の日本軍人が待っており、中国の上海駅に行ったなどの話がある。経済的に厳しい農民の娘を対象に慰安婦が集められていたことがわかる。
検事:この話はむしろ強制的に慰安婦が集められ、軍人が募集過程に加担していたと考えなければならない。強制動員、強制連行の主体は日本軍だ。それが歴史的事実だ。しかしこの事件図書には強制動員、連行の主体が決して日本軍でないと叙述されている。
弁護人:物理的主体が日本軍だということか?
検事:物理的、構造的主体すべて日本軍だ。
裁判官:起訴内容を見ると、日本軍や国家が強制連行を指示したと考える証拠はないという立場だ。業者がどのように連れてこようが、これを黙認したことに対する責任はあっても…日本国が強制連行と言って連れてきたという証拠がないというのだから。
弁護人:第7号の1-3。以下は『強制的に連行された日本軍慰安婦』という韓国挺身隊問題対策協議会が作った証言集だ。慰安婦が国防婦人会に加入して協力を強要された状況が出てくる。たすきをかけて帽子をかぶり兵士を見送ったり訓練を受けたりした。皇国臣民の誓詞を覚えなければならず、君が代を歌い防空演習や看護活動もした。「中に入って階級の高い人に会った。朝鮮に行きたいと言った。看護婦が足りないから行くかと聞かれた。看護婦は3階で寝た」。性労働以外の戦争協力を強要されたという話で、強要された愛国、強要された協力についての証言資料だ。
検事:この証言集に朝鮮に送ったと出てくる。しかしその前に新しい朝鮮人女性が補充されてきたという内容がある。
動員では日本人が連れていった場合も多い。9-3には銃剣を突きつけて聞き取れない日本語を叫びむりやりトラックに乗せられ連れていかれたと出てくる。これは直接的にむりやり連行されたということだ。(呂福実のケース)
弁護人:被告人は本に「軍人や憲兵に連れて行かれた場合もある」と明示した。ただしその場合は個人的逸脱と考えなければならないとしただけだ。
朴裕河:現在の学界の理解では、占領地では強制連行もありえるが植民地ではそのような理由がないというのが中心だ。学界や関係者ならばみな知っている話が一般人に知られていなかっただけだ。私がした話は、日本軍が募集と管理はしたが手段や方法を選ばず連れてこいとは言わなかったという意味だ。もちろん軍人が強制的に連れていったケースを完全に排除はできないが、その場合は個人的逸脱としなければならない。植民地といっても表面的には国民のひとりであり、強制的に連行するのは違法だからだ。軍人だと話す場合は証言の中ではむしろ少数で、その場合も軍服を着た業者だった可能性が高いと考える。
(補足-もちろん本当に軍人が一緒に来ることもあるがその場合、むしろ形式的にはより志願の形が目立つような情況が『女の兵器』に見られる。それがまさに植民地統治の方式だ)
裁判官:業者が軍服を着ていたかもしれない。個人の逸脱であることもある。業者が軍服を着ていたという資料はあるか?
朴裕河:業者が軍服を着ていたとみられる資料がある。今後提出する。
(補足:7-4では慰問団に参加した女性の証言が出てくる。それによると慰問団には日本人女性もいた。この証言も朝鮮半島での強制連行が常識的にはありえなかったという証拠だ。
8号証は料金表などの慰安所の規則だ。負傷兵の世話をし、洗濯をし、戦場に見送った話が出てきて、入院した慰安婦を軍人が見舞いに来た話もある。9-1では慰安婦生活の後軍需工場を営んだ女性の話も出てくるが、慰安所での行為を利敵行為と思い、そこでの経験は話さなかったという。9-2には、朝鮮から出て行った日本人女性の話があり、9-3、4にも慰安所での、これまでの常識とは異なる状況が記されている)
弁護人:10号証「強制連行された朝鮮人軍慰安婦ら4」には「国のために行った」という証言が出ている。だから補償しなければならないと。「朝鮮が貧しくて出稼ぎに」行かなければならなかったという話も出てくる。
検事:「国のために」という言葉は日本帝国のために、という意味ではない。当時は(朝鮮人にとって)国なんてなかったのだから。
弁護人:11号証と同様の証言集5冊だ。慰安所の状況を知ることができる。
検事:証言集はむしろ分かりやすくまとめられている。これまでの研究によると軍慰安所はその形態によって軍直営営慰安所、軍専用の慰安所、一般の慰安所のうち軍も利用する慰安所三つに分けられる。軍直営の慰安所、形式上は民間業者が経営しているが軍が管理・統制を担う慰安所、第三は軍が指定した慰安所だ。この吉見義明教授の定義は非常に適切だ。形式上は民間業者が経営しているが、軍が管理・統制する軍人軍属専用の慰安所だった。
(補足:12号『海南島に連行された朝鮮人の性奴隷に対する真相調査』は韓国政府傘下の委員会が作ったもので、日本軍にいた朝鮮人の証言が収録されている。朝鮮人慰安婦が軍人たちより年上だったため「お姉さん」と呼んでいたという話が出てくる。ほとんどが日本人女性だったことや日本人女性の方が朝鮮人女性より若かったなどといった話も出てくる。このような話はごく一部だろうが、かといって無視すべき理由はない。場所や時期によって数多くのいろいろなケースがあったと考えねばならない。
13号証は『日本軍慰安所の管理人の日記』という本だ。慰安所経営に慰安婦の「酌婦許可書」、「就業許可書」、「廃業許可書」が必要で、その書類を軍に提出しなければならなかったということが分かる。慰安所の業者らは共に組合を作ったり、慰安婦に代わって朝鮮に送金したりもした。
慰安婦には移動の自由があり「女性青年隊」として応急処置法を学ぶなど、協力を強要した話も出てくる。)
弁護人:14号証は日本軍にいた朝鮮人が書いた本だ。慰安所に関する内容で翻訳した部分を見ると、慰安所の名前が「愛国奉仕館」だった。日本軍が慰安所の役割を軍人の戦闘力向上を促すものと捉え「愛国」いう名前をつけた、という証拠だ。
15号証は日本植民地時代の作家崔明翊が書いた「張三李四」という短編だ。小説だが、朝鮮人の業者が自主的に日本軍を追って慰安所を運営していたことがわかる。「従軍」したのはむしろ業者の方だった。
検事:「愛国」は起訴内容の一つだ。慰安婦とは愛国心のある同志的関係だった、国のために喜んで行った、たすきをかけた。このように書かれているが、これはすべて朝鮮人についてではなく日本人慰安婦の内面を書いたものだ。この本では何の根拠もなく日本人慰安婦が朝鮮人慰安婦と同じレベルで描かれている。慰安婦たちは自身をつまらない存在だと認識していたが、国家のために奉仕するという自負心を持つようになったという話だ。この本では何の根拠もないが日本人も韓国人も慰安婦は同等で同志的関係だったとしている。
弁護人:本のその部分が日本人慰安婦についての記述であったことは被告人自身が本に明示している。しかしそれ以前の部分で、朝鮮人慰安婦が洗濯し看護したという証言を引用しており、「朝鮮人慰安婦も基本的な待遇は同じであったとしなければならない。そうでなければ敗戦前後の慰安婦が負傷兵の看護をして洗濯、縫い物をしていた背景を理解することができない。朝鮮人慰安婦たちもサユリなどと呼ばれた。『日本人』の代わりになる仕事…」この部分は朝鮮人慰安婦に与えられた役割が日本の慰安婦と同じであったということを表している。しかし同時に「『偽りの愛国』と『慰安』に没頭することが彼女たちにできたたった一つの選択だった」と書いたのだ。
構造的には日本人慰安婦と同じ境遇に置かれていたが、日本人慰安婦とは違ったことについてもはっきりと話している。
(補足:16号は、国防婦人会についての本だ。慰安婦たちがなぜ割烹着を着てたすきをかけて、「愛国」的な行動をしなければならなかったのかを知ることができる資料だ。いわゆる娼妓たちも「我々も日本の女」、「国のために」と、このような動員に積極的に参加するよう仕向けたのは社会の売春に対する差別だった。朝鮮人慰安婦もその枠組みに組み込まれたのだ。
17号は、同時代の慰安婦募集広告だ。紹介所が18歳から30歳の女性を募集したことが見て取れる。新聞にこのような広告が出たということは慰安婦という存在が公的な存在だったということを物語っている。しかし、仕事内容を明示しておらず、このような点が詐欺的な募集を可能にしたのだろう)
弁護人:証18号は慰安所の入り口写真だが、「身も心も捧げる日本女性のサービス」と入口に書いてある。別の写真には、慰安所の名前が「故郷」、「愛国食堂」とある。これは慰安所に課された役割が身体的、精神的な慰めであったことを語っている。故郷に対する郷愁を紛らわすために。
検事:朝鮮人慰安婦は、同志的関係ではなかったのに同志的関係であったと虚偽の事実を表現したとして起訴したのだ。
弁護人:被告人は朝鮮人慰安婦を自発的な同志関係とはしなかった。19号証は当時、日本軍人が慰安婦は「軍属」だったと書いた資料だ。
検事:それは慰安婦に関する日本軍の認識ではないか。起訴内容とは関連がない。
弁護人:20号証だ。『女の兵器』という朝鮮人慰安婦の手記だ。集められ強姦されて泣くことになるが、後に国防婦人会に加入してうれしかったとし、愛国奉仕団の一員となった自分は一般娼妓とは異なる存在と自分のことを認識してえいる。そんなふうに変わっていったケースもある。どうにかして生きていくためであったろう。
(補足:この資料はおそらく書き手が男性ではないかと思われ、出すべきかどうか躊躇したが、村にやってきて「愛国」を掲げて募集する様子と、少女が変わっていく様子が書かれていることにおいて排除できないと考えて使った。もちろん、すべての口述や評伝に聞き手や書き手の視点が入るのは言うまでもなく、重要なのは資料との距離のとり方である)
21号証は日本人慰安婦のケースだが、多くの兵士を相手にしたことによる苦痛が書かれている。
22号証は日本軍の軍医が書いた「漢口慰安所」。ケイコ(朝鮮人慰安婦)を司令官が表彰したという内容もある。軍人が業者の搾取から慰安婦を保護しようとした内容も見られる。この本に出てくる慰安所の名前も「平和館」だ。慰安婦が上官の奥さん扱いを受けた話も出ている。
前述した、詐欺にあって慰安所へ来た後、他の所で働かさせてもらうことになった話はこの資料に出ている。
23号は今年6月に毎日新聞に掲載された資料の原本と翻訳だ。米軍捕虜を尋問した資料で、朝鮮人が証言した部分だ。捕虜たちに日本の植民地統治全般に対する考えを聞いた資料だが、慰安婦について語った内容が出ている。彼らは「韓国売春女性は全員志願者であったか、または親によって売春業者に売られてきた女性たちだった。日本人による強制的徴発があったなら男らが激しく抵抗したはず」と話したと書かれている。
検事:この報告書には軍属と書かれてある。(補足:Civilianとしか書かれていない)民間人イ・バクド、ぺク・スンギュ、カン・キナムといった感じで。慰安所を経営した業者と推定される。そのためこのように言うしかなかったものとみられる。なぜなら慰安所に集めてくることに協力した者は処罰対象になるためだ。当然、志願者と言うほかない。自分が強制的に連れてきたのではなく、自ら来たことにしようとこんなに証言をしたのだ。したがってこの証言は信憑性が低く、慰安婦の自発性を裏付ける供述と見ることはできない。
弁護人:検事の推測だけでこの資料に信憑性がないとは言えない。
裁判官:捕虜たちが述べた内容に信憑性があるかどうか。これは注視しなければならない。
弁護人:24号証は1970年8月14日付のソウル新聞の記事だ。「花柳界の女性を動員していた日本帝国は、次第に人数が不足すると一般の娘まで召集した」との記述がある。
25号は千田夏光のインタビューの内容だ。「一種の売春婦だった」としながら「彼女たち自身が国のためだと信じていた」と話している。「従軍慰安婦」という本にも同じ認識が書かれている。
検事:『従軍慰安婦』という本には、日本人慰安婦には「祖国のために」「軍人のために」という意識があり、自分の行為を愛国心という装飾物で飾った。しかし朝鮮人慰安婦は強制連行され働いていた女性たちだ。朝鮮人慰安婦と日本人慰安婦は異なる。なのにこの『帝国の慰安婦』では日本人と朝鮮人を同等に見ており、同志的関係にあったとしている。
裁判官:強制連行とは、構造的な強制性だという話がなかったときのことではないのか。物理的な強制性のことだから。
弁護人:強制であったとしても業者によるものか、軍によるものかを区別しなければならない。(同意する)
27号は韓国政府報告書だ。韓国外交省の挺身隊問題実務対策チームが1992年7月に発表したものだ。
ここでも軍が慰安所を直接経営していたというよりは、経営は売春業者に任せ、軍は委託管理などを行っていたという認識になっている。募集方法も1938年までは都市地域の女工から募集、飲食店従業員などを人身売買の手法で募集しており、38年から40年までは貧困農民の娘から募ったと書かれている。
慰安婦には収入があり業者と収入を分配していたことなど、管理売春形態であったことが政府にも分かっていた。
検事:この報告書は、日本軍が目的や軍隊のために売春をし、軍隊が直接全面的に介入し徹底的に管理できるようにしていたことを物語っている。慰安所は軍隊に従属した集団だった。売春業という単語だけで韓国政府も売春業と認識していたことを立証のための証拠として提示しているが、韓国政府は慰安婦を売春業と認識してはいない。報告書には、日本軍の視点から見た場合、慰安所は軍隊による強姦予防や性病予防のため、そのために売春業に軍隊が介入し徹底的に管理できるようにしたという内容がある。此の頃は慰安婦研究の出発点であり、そのためタイトルも中間報告書になっている。韓国政府は慰安婦を売春と認識したことはない。
弁護人:当時、韓国政府は慰安婦を管理売春と認識していた。それに基づいて河野談話も作成された。
28号証4は軍の指示文である。この部分は「精神的な慰め」について書かれている。「現在特殊慰安所は慰安婦の数が少なく、ただ情欲を満たすためのものにすぎない。そのためもっと慰安婦の数を増やして精神的な慰安も与えられるよう指導するように」と。身体的な性欲だけでなく精神的な慰めも与えられるようにすることが慰安婦の役割だったという、慰安婦が強要された役割であった証拠資料として提出する。
検事:むしろ計画的に慰安婦は運営されていたということが分かる。資料29号から33号(「従軍慰安婦関係資料集成」)はアジア女性基金が発行した資料だ。
(補足:この資料には契約書、営業許可書、就職許可書が含まれる。許可制にしたのは、未成年を雇用したり詐欺などで連れて来られたりすることがないようにするためだった。
軍人が暴行することもたくさんあったが憲兵による取り締まるもあった。言うならば、暴行はあったが公的に認められていたことはないという話だ。遊郭を慰安所に指定していた様子も出てくる。軍属に制服を着用させていた様子も確認できる。軍属扱いを受けた業者にも軍服が支給されたため慰安婦が軍人と勘違いした可能性もある。慰安婦は最初は同郷の人が集められた。その方が精神的な慰めにはより都合がよいと期待したのだ。慰安団のうちに日本人が90人いたという話も出ている)
弁護人:次は慰安婦問題解決案研究としての『女性家族省の用役報告書』。日帝強占下強制動員被害真相究明委員会が出した報告書だ。研究責任者は、ミンディー・カトラー(アジア政策研究所)だ。カトラー氏は米国下院の決議を引き出すことに貢献した人だが、慰安婦の募集は人身売買を通して行われたものと見ている。
検事:人身売買での売買主体は対象者ではなく「対象者を強制的または騙して連れてきた者と、その者から対象者を買う者」だ。対象者が自発的に自分の体を売るということは決してない。
弁護人:これは単純な強制連行ではなく親に売られた等の形であったことを証明する資料だ。
検事:では、親は慰安婦になると知っていて子供を売ったのだろうか。人身売買の対象としてもそのひとがどのような仕事をするのか知った上で売ったというのか?
弁護人:『帝国の慰安婦』によれば、騙されて連れてこられた場合も自ら行った場合もあるという。
36号証は2015年にアメリカの日本(歴史)学者たちが発表した声明書だ。2015年、元慰安婦たちの側に立って作られた報告書だ。性的暴力と人身売買のない世界を作るため、アジアの平和と友好を深めるためには、過去の過ちを清算しなければならないと言う。それでも慰安婦問題は人身売買と認識している。
検事:慰安婦は軍隊による組織的管理が行われたという点で、そして日本の植民地や占領地で貧しく弱い女性たちを搾取したという点で問題だ。女性の移送と慰安所の管理に日本軍が関与していたことを証明する資料が多数発見された。被害者らの証言にも重要な証拠が含まれている。証言に違いがみられることもあるが全体として控訴力のある公文書で立証されている。証拠も存在せず、証言は一貫性のないように見えるが、全体的な証言は明らかに一つのことを指している。
弁護人:被告人はその部分について意見が変わらない。慰安婦と公娼制度に関する学者の研究も多い。一部を読み上げる。「廃業届には廃業申告書を提出しなければならないが、申告書にはオーナー業者が連名捺印をするようになっていた。業者らが自らの利益に反して娼妓の自発的廃業を認めるはずがない」「軍人の性欲処理と性病予防のために公娼を設置した」…等。
検事:証拠38号から41号は起訴内容と何の関係があるのか。慰安婦と公娼制との関係とはどんな関係があるのか?
弁護人:慰安婦は公娼制度に編入されたとここに記載されている。だから名誉毀損ではないという証拠の提出だ。
検事:慰安婦を集めた場所は日本内地だ。軍ではどうしても直接手を出せないことであったため思いついたのが慰安所だ。軍属となっているが正式な軍所属ではなく、内部で「御用商人」のような存在を利用した。
弁護人:引用した部分は、必要性があり引用しただけだ。同志的関係という枠組みの中で商品扱いを受けたと明らかに述べられており、文字通りオランダ人、中国人慰安婦などの戦争相手国の女性たちと比較する目的で使用しているだけだ。
検事:参考資料として出された聯合ニュースの資料を読んでみたい。挺対協の提案が2015年4月23日掲載された。軍慰安婦問題解決市民団体と金福童が23日、東京で提示した案だ…(省略)被告人は責任を認めたというが法的責任ではない。いったい何の責任を認めたというのか。
弁護人:そんなことをなぜここで問題視しなければならないのか。だが、挺対協も法的責任に関するハードルを下げたと表現している。法的責任を要求事項にはっきりと含めなかったのだ。
裁判官:日本に法的責任があるか否かというのは、本裁判の争点とは関係がない。
朴裕河:簡単に補充する。
1)日本人慰安婦と朝鮮人慰安婦を私が同じ扱いをしたとしているが、違いについても書いた。日本人慰安婦は将校を相手することが多く相手が将校の場合、将校の人数は少ないため環境や立場がより楽だった。ただ朝鮮人慰安婦も将校の相手をした場合がなくはなかった。
朝鮮人慰安婦の中で日本人のように行動した者がいたのはむしろ二重の差別があるためだ。日本人娼婦さえ、一般女性と「同じ日本人女性」の扱いを受けるべく、国防婦人会に積極的に参加し軍人を見送ったりしながら士気を高めるていた。
2)朝鮮半島でも日本人女性たちが慰安婦になった。慰安団にも混ざっていた。朝鮮半島で日本人女性が慰安婦になるのに朝鮮人女性だけを別に強制連行するとは常識的に考えられない。当時、突然連行されたのは主に反体制思想犯だった。占領地と植民地の違いを考慮しなければならない。
検事は、安秉直教授が「慰安団」募集は強制だったと話したとしたが、その中に日本人女性も多かったという事実を見過ごした結果の認識と考える。彼女たちも一日に数十人の相手をすることもあり、程度の差はあるだろうが女性として動員され受けた苦痛の質は同じだ。
3)軍服の支給についての指摘では、慰安所に出入りするときのみと検事は言ったが、業者が慰安婦を集めに朝鮮半島へ来たときも軍服を着ていたと考えられる資料がある。追加提出する。
4)慰安所に行くことを知りながら娘を故意に売った親がいるだろうかと言っていたが、そのような親も少なくなかった。ただし養女である場合も多かった。貧しさから制度の犠牲になったケースが多いと思われる。
『中国に連れて行かれた慰安婦2』の一部を読んでみたい。
「その時十何歳だっただろうね。ああ、十六歳になった頃だと思うよ。飲み屋にも、2年くらいいたからね。祖母、祖父の判子までもらってこいといわれたよ。祖母、祖父まで印鑑を押してくれるはずがないでしょう。そこでね、父は私の話なら信じてくれていたので父の手をひっぱって川べりへ出て事情を話したんだ。『父さん、セクシ(商売女)を買いに来た人がいたの。いくらくれると言うんだけど、私、遠いところにお金を稼ぎに行く』『おい、何言ってるんだ。?私はお前がいてくれることだけを楽しみに生きているのだから。だめだ』『だめなことなんてないよ。お父さんが良い暮らしをするのを見てから死にたい。父さんにはただお金を満足に使って、ただ食べたいものを食べてもらいたい。私ひとりくらいいないものと思って、父さん、私を紹介してちょうだい。ほかに方法がない。水商売のところに2年もいたのだから。、私、もう村にいたくないよ』『どうしてもそうなら、紹介してあげるよ』『そうよ。母さん、父さんの名前を書いて判子を押して』『お婆さんお爺さんの判子も全部押すのだそうよ。どうしよう?父さん』『それじゃあ私が書こう』父が書いて、祖母と祖父の判子を押して、あとから皆の同意をもらった。それを持って博川へ行ったの。到着してから様子を見ては、父さんは『(ほかの人ではない)あなたに娘を売ったのだから、別のところにまた売ちゃだめですよ』そのような約束を(買い手と)したんだ」。
こうしたケースは少なくない。家族のために自分を犠牲にした人たち。
裁判官:重要な資料のようだ。どうして提出しなかった?提出しなさい。
朴裕河:検事の叱責を聞いて、提出の必要性を改めて悟ったためだ。似たような資料は多い。
5)許可申請書は業者側の書類だと検事は言うが、「酌婦」(当時は慰安婦を「酌婦」とも呼んだ)としての本人の許可願も必要だった。また、千田夏光を引用したことを検事は否定的に言うが、千田を本の冒頭に引用したのは「愛国」の枠組みでこの問題を見た者が、私の知る限りセンダしかいなかったためだ。私も10年前、同じ認識を持ち本にも書いたが、その時は本を読んでおらず、後になって知ったため、先立つ認識への礼として引用した。
6)検事は慰安婦が軍属であっても性奴隷だ、と言う。ところが日本の国会での議論について書いた文書を見ると、日本の従軍慰安婦が戦闘者として認識されていたことが分かる。手榴弾を運んだり、洗濯したりしたことについてだ。補償策を作らねばならないという議論があった。後に提出する。
7)18号の連合軍資料は信憑性がないと言っているが、その発言の前後は、日帝の過酷さについて話している。だからその部分だけを検事が願ったニュアンスではなかったという理由で、信憑性がないとする理由はない。しかも、三人の証言者のうち一人の個人調書があるが、その人は炭鉱夫だった。検事が推測する「責任を回避するために嘘をつく業者」ではない。全体的に日本の過酷さを強調しているのに慰安婦関連事項だけを異なる姿勢で話しているとか考えるべき根拠はない。後に提出する。
8)アメリカの歴史学者たちも慰安婦問題に関して私と似たような認識を表した。2015年5月のことだ。私が削除版<帝国の慰安婦>に声明を入れた理由でもある。長い間、慰安婦問題に対してもっとも良心的に報道してきた朝日新聞が2014年8月に奴隷狩りをしたという吉田清治の証言を検証し、虚偽という結論を下した。しかし、韓国ではこのニュースはその趣旨が報道されなかった。
9)「同志的関係」についてもう一度説明しよう。まずは形態的な意味だ。韓国が日本帝国に占領されたため、「日本人」として動員したという意味だ。そんな話をしたのは慰安婦について少女たちをむりやり連れて行き軍人たちが強姦したという認識だけが広く普及されてきたからだ。植民地統治下での国民動員の一種とみるべきだ。そうした時、実際どれほど自らすすんでの行為だったかの判断は極めて難しい問題だ。
そうした状況の中で軍人と慰安婦が社会の最下層の者同士や、故郷を遠く離れた者同士などが、心を通わすこともあった。形態的枠組みは民族的関係だが、実際の関係は男女関係や階級的な関係だ。民族関係としての同志的関係ではないかと恐れ、否定する理由はない。
そのような状況を知ることの出来る資料をもう一つ読んでみたい。『ビルマ戦線、日本軍慰安婦文玉珠』という本だ。亡くなった方だ。
「私は軍人たちの機嫌を損なわないように、楽しんでもらえるようにできるだけ努めた。兵士たちの家族やふるさとの話を聞き、一緒に日本の歌を歌った」「所帯持ちの兵隊たちもかわいそうだった。いつも妻や子供のことを思い出しているようだった。泣きながらこんな歌を歌う人もいた。戦地の軍人たちの思いとわたしたちの思いとは同じだった。ここにきたからには、妻も子も命も捨てて天皇陛下のために働かなければならない、と。わたしはその人たちの心持がわかるから、、一生懸命に慰めて、それをまぎらしてあげるような話をしたものだった」
文さんは好きだった軍人もいたが、戦争が終わると彼は日本に行こうと言われ自分は朝鮮に行かなければならないと言ったところ、その軍人は「それなら自分が朝鮮にいこう。ヨシコが日本人になってもいいし、自分が朝鮮人になってもいい」と言ったと話した。また「一週間に一度ヤマダイチロウがくるのが生きがいになって、わたしは慰安婦の生活に耐えられるようになった」と。
「その刀は、天皇陛下からもらったものじゃないか。敵に向かって抜くべきものを、はるばるこんな遠くまであんたたちを慰安にきている私に向かって、朝鮮ピ―、朝鮮ピーといってばかにして。わたしたち朝鮮人は日本人じゃないか。」
「世の中というものは、ひっくり返ることがあるのだ。ある日突然立場が逆転すると、こんなふうに人間の関係も変わってしまう。それがわたしには悲しかった。それまで『日本は世界でいちばん強いのだ。日本人はいちばん上等ななのだ』といっていた軍人たちが、国が負けたら小さくなってしまっている。情けなかろうとまた泣けてきた。
その時のわたしは、まだ日本人の心をもっていたのかもしれない」
「私はタテ八四〇〇部隊の軍属だった」
裁判官:その2冊の本を証拠として提出するように。次は被告人尋問を2~3時間行う。資料は次の期日まで受け付ける。最終弁論は3週間ほど後、最終弁論をして結審したらどうだろうか。11月29日午後2時に変えてはどうだろうか。3週間後の12月20日火曜日に結審公判をすることにしよう。
(6)「20億ウォン懐柔説」について
(慰安婦、もう一つの考え「敵は100万、味方は自分ただひとり」から続く)
12月18日の電話内容を纏めながら省略した部分がある。ナヌムの家のハルモニたちがアメリカで訴訟を準備中で、その裁判で日本に請求する金額が20億ウォンになるだろうというところだ。ぺさんはこの20億ウォンの話を、この日だけで2回、その後も何回か言及していた。内容としてはほとんど、それは途方もない金額という認識だった。当然のことだが、慰安婦の方々の価値観や考えは一つではない。
しかし、20年以上、韓国社会の中でその事実は認識されなかった。周辺にいた人たちにとってはその一人一人が異なる「個人」であったはずだが、多くの韓国人たちにとって「慰安婦ハルモニ(おばあさん)」とは単に「日帝に苦しめられた被害者」以外の姿として存在する機会はなかった。
思えば、1995年に日本がアジア女性基金を設立し贖罪を試み(このとき日本が集めた国民募金に付けた名前は「償い金」だった)、以後、受け取った人が60人以上になるという事実がこれまで全く知られてこなかったことも、「慰安婦ハルモニ」はとことん「慰安婦ハルモニ」としてしか存在し得ないようにしたはずだ。慰安婦ハルモニたちの感情と考えが決して同じではないという、あまりにも当然なことが可視化されたのは、せいぜい日韓合意以降、未だ1年と経っていない。しかも、日韓合意の直後に、合意を受け入れる、と表明した方の声は、すぐに取り消された。
また、2000年代に沈美子さんという方が怒りを込めて挺対協を批判したことも、その痕跡はネット上にかずかに存在をとどめるのみで、広く受け止められることはなかった。そのように一人の慰安婦の声が埋もれてしまった90年代半ば以降の10年間、支援運動の声は国内外に広く届くことになる。ぺさんをして、初対面だった私に向けて日本を許したいとの気持ちを漏らさせたのは、おそらくそうした歳月だろう。ぺさんはこの時すでに90歳だった。
そして、その一言は、その後続くことになる長い長い対話の冒頭だったけれど、もしかすると、それ以降の話の核心だったのかもしれない、と私は今になって思う。日本を許したいという話は、法的責任はもちろんのこと、補償すらいらないということだった。さらに、ぺさんは慰安婦問題が問題視されたことすら納得できないとまで話していた。
もっとも、それはぺさんがハルビンの遊郭にいたゆえの、最前線で軍人たちと共に移動することを余儀なくされた慰安婦たちの体験を知らなかったゆえの言葉ではなかったかと思う。しかし、慰安婦問題についてそういうふうに考えている方がいるということを、長いこと関心を持ち続けてきた私ですら知らなかったのだから、自責の念を禁じ得ない。
20億に関するぺさんの話まで書くことになったのは、第三回公判記に書いたように、検事が、ユ・ヒナムさんの偽証を、判事やメディアに向けて私のことを日本のスパイでもあるかのように疑わせる資料として言及しつつ提出したからだ。元は仮処分裁判の時に話されたというが、たまたまその時出席しなかったこともあって長い間まともに反論することもしないまま放置してきた。その理由は、自分の解明が、慰安婦の方々の信用を削がせ、さらに韓国の信用を落とすことを憂慮したからである。
ユ・ヒナムさんが刑事裁判が始まる頃に法廷でふたたび話したとき多くのメディアが私に確認をとらないまま報じるようなことがあった。さっそく解明を出したが私の反論も載せてくれたところはごくわずかでしかない。最も確信犯的に反復報道をしたネットメディア「ソウルの声」は、直接抗議したにもかかわらず、この記事を修正も削除もしなかった。そして、その記事を引用しながら、私のことを「親日売国女」「八つ裂きにすべき女」「汚らしい女」などと非難する人たちは、今でも後を絶たない。
◇
2013・12・18
(夕方・7:28)
まぁ、お金は、政府が月々130万ウォンずつ支給してくれるのよ。返さないといけないわけでもない。死ぬまで支給されるけれど、そんなこと全部無視して、金大中さんがお金をくれたのも無視して(注:アジア女性基金に対抗して政府が4300万ウォンほどの一時支援金を支払った)、全部無視して、いつまでも、、、
ユ・ヒナムも、今回(私のところに)来ては、裁判が始まるから、日本のお金を20億ウォン必要と言え、20億要求しろと。
(私も前回お聞きしました。昔5千万ウォンだったから、今もらうなら5億はもらわないといけないと、仰ってました。)
いや、20億だよ。4ヶ月前位に会議したのよ。私が体調悪い時。病院から帰って体調良くないときに来て、なんて言ったかっていうと、「あんたも20億必要と言えと。」。私は理由がわからんから、何を20億というのか、って聞いたら、「裁判する時一人当たり20億くれろと答えろ」と言ってたんだよ、アイゴ、、
(4ヶ月前というと、2013年7・8月頃の事であり、私がまだナヌムの家に行く前のことである)
(私もその書類は見ました。初めてナヌムノ家を訪ねたとき、キム局長だったかな、、、事務局長、その人が私に書類を見せてくれました。ハルモニのお話を聞くと、その書類のようですね。私への説明では、現状のままでは解決できないから、裁判をやり直すのだけれど、裁判内容は、日本に勝とうというものではなく、合意を引き出す裁判だ、調停をする裁判だと言って、そうすることにしたと、言ってました。その書類にはハルモニたち10人くらいの名前にはんこが押されてました。)
あぁ、体調を崩して病院から帰って見回ってたら、自分たちだけで会議してたのよ。会議して終わって出て来て、金さんも私に「20億、、」っていうからびっくりして、それが、その20億ということかなって。
(キム局長も20億と言ったんですか?)
まぁ、そうだね。最後に、帰るとき私たちの部屋に入って来て、「ハルモニ、金貰うときに20億と、ハルモニもそう言わないとならないから、私が名前書いとくからね」って言って。私は訳がわからなくて、「何が20億じゃ?」って聞いて話を聞くと、ユ・ヒナムの話だって。ユ・ヒナムが20億くれといって、裁判起こすって。全員が要求しないとならないから、名前を全部書いておいたみたい。後から聞いた話だと。
(一人当たり20億ですか?全員で20億じゃなくて?)
いやいや一人。だから私が、、(判読不明)と思って。
アイゴ、20億だなんて。2億でもなく。あの人たち、どうして20億がほしいと言えるのだろうと思ってだまってた。
(それは不可能なのでは、、、もしかしてキム局長やアン所長が言った金額ではないのですか?ハルモニたちが考えてる金額?)
いや、あのユ・ヒナムだよ。
(あぁ、それは不可能。。私、日本側の人たちとも会って話すこともあるけれど、それは難しいと思います。)
そうだよね。荒唐無稽なことを言っとる。
(ユヒナムが)見回ってた時、私のところに来て、「何を言われても20億といってね」って、こんなこと言ってた。「20億が人のうちの名前だとでも?で、理由は?」って言ったら、もう帰っちゃっていない。会議に出た人たち全員帰ったので後から聞いたら、ユ・ヒナムがその意見を出したみたい。
(そうですかあ。。そういうことだと解決は不可能と思います)
ユ・ヒナムは、もともと考えることが大きいじゃない。ほんとうに、とんでもない考えをする人だよ。
ぺさんとの会話が最後に録音された日付は、次の年の5月18日である。初めて電話で話した時も何度も20億ウォンのことに言及されたが、亡くなる一ヶ月前の5月3日にもこの話をしている。この時はまだ、苦痛は訴えても話は普通にできる位お元気だった。そして、私に多くの話を遺言のようにされた。知っておくように、メモしておくように、記憶しておくように、との言葉とともに。
2016・5・3
いや、まぁこの話は知っておけってことなのよ。慰安婦も、日本人たちを、日本を想っている人たちもいる。(なのに)最初から最後まで、商売、、、ユ・ヒナムのように一人当たり20億ウォンずつもらう、そんな人たちがいるからね。
私も金は嫌いじゃないし、誰かさんの言うように、お金くれれば断りはしない。だけど、お金にそんな欲求を持っちゃって、、、
(以下省略)
◇
ぺさんが体調が悪い中こうした話をされた理由を私はいまになって分かるような気がする。「いや、まぁこの話は知っておきなさいって」とか、「(裕河だけが)知っておきなさい」と、何度もおっしゃったものだ。そうした話が公けになった場合ぺさんに及ぼす影響を恐れて、私はペさんの生存中は約束を守った。
しかし、ぺさんが恐れたのは、ご自分の考えが世間に出ること自体ではなかった。むしろ、いつかは知られることを望んでいた。慰安婦としていた遊郭が実際に存在したことを確認してほしいと、そして自分が偽物ではないと(日本への非難を控えていることでそう言われたらしい)証明してほしいとおっしゃりながらメモしなさいと話していたのだから。
20億の話をあえてされたのは、必ずしもユ・ヒナムさんのことを非難するためではなかったように思う。その話はむしろ、誰もが勝手に想像し知悉しているかのように思い込んでいる「慰安婦ハルモニ」が、実は決して一様ではないことを、世の中に訴えたかったゆえのことではなかったろうか。
「日本人たちを、日本を想っている人もいる」との述懐がそれを語っている。ぺさんは間違いなく、ご自分の考えを私だけでなく世間に伝えたがっていた。おそらく、日本にも。
ぺさんは、ナヌムの家に住み始めて以来の20数年の間、多くの日本人に出会っているのだろう。しかし、そうした本音を聞いた日本人はいるだろうか。遅きに失したが、こういう形ででもぺさんの話を伝えておきたい。
もちろん、それとてしょせん多くの中のひとりの考えに過ぎない。しかし、仮にたった一人だったとしたらよけいに、その「声」は大切に記憶すべきと思うのである。同時に、ぺさんが直接伝えられるように環境を整えることをしてあげられなかった私自身の無力さについても、私はこれからも考え続けなければならない。
[裁判関連] 刑事訴訟 公判記3
過去2回の公判は『帝国の慰安婦』自体の検証であった。言うなれば、本だけを前にして、名誉棄損と指摘された34項目を順番に指し示しながら、検事と弁護人双方が各自の主張を繰り広げる場だった。すでに書いた通り、検事が本についての主張を行うときに根拠としてきた資料の大部分は、学者または支援団体など関係者の話だった。そして、告発がなされた以降の資料が多かった。
だが、検察が提出した資料の中には、国連報告書をはじめとする過去の資料もあった。その大部分は民事裁判に提出された資料だった。そして、それらの資料を援用しながら、仮処分裁判でも損害賠償裁判でも「世界と日本はこう言っているのに、朴裕河だけが慰安婦問題をめぐって戯言を述べている」という原告サイドの主張を受け入れていた。無論私は、一人の学者として私から見た慰安婦問題をめぐる認識を発表したまでだ。その認識が正しいかどうかは、当然、アカデミズムを含む世間で検討されるべき事項だ。だが不幸にも、私の著書についての検証はそうではなく法廷に一任されてしまい、この日は、それらの資料の主張が、検事によって再び代弁された日となった。
10月11日。 3回目の公判では、そんな「犯罪の証拠資料」と共に、検察の主張に反論するための、私の主張の根拠となる「証拠資料」の検証が行われる予定だった。だが、検察の主張とこちらの反論に時間がかかり過ぎたため、こちらの証拠資料についての説明は次回公判に持ち越された。
検事の資料は60件余りで、大きくは告訴状と告訴状補充書、告訴人の意見書、私の著書に検討を加えた法科大学院生のレポートなど、周辺人物の考えを汲んだ述べた資料だ。
そして、ナヌムの家に住む元慰安婦の方5人の口述、慰安婦のおばあさんの口述記録集『トゥリナヨ(聞こえますか)』、証言ドキュメンタリー映像、『55人のオキナグサの少女達』というタイトルの慰安婦の体験資料、日本軍「慰安婦」被害者e-歴史館の資料などの元慰安婦の口述、ナヌムの家に居住されていた慰安婦の1人だったユ・ヒナムさんの捜査官陳述調書が、原告サイドの資料として提出された。さらに、尋問調書、捜査報告書、犯罪経歴等の照会回答書など、私にかかわる検察の資料が、言うなれば、当事者の資料だった。
周辺資料のうち、検察が独自に提出した資料は「捜査報告」という名前で提出された、一般人のブログ上の著書についての感想だけだった。(文学評論家・孫鐘業氏のフェイスブックの文章が添付されている文書。彼は私をアイヒマンになぞらえて非難した人物だ)。
より公的な文書では、慰安婦問題解決のために韓国外交部が積極的に動かないのは違憲と判断した憲法裁判所の判決文、河野談話、 クマラスワミ報告書(1996年 )、マクドゥーガル報告書、アムネスティ・インターナショナル報告書、国際法律家委員会(ICJ)、国際労働機構(ILO)など国際機構による慰安婦問題関連の資料集、アメリカ連邦下院決議文など、慰安婦問題解決運動の結果出されてきた、過去20年あまりの、第三者の認識を示す資料、そして告発がなされた以降に私の著書に下された判断である、仮処分決定書と損害賠償判決文があった。これに、「帝国の慰安婦を語る」というタイトルの若手歴史研究者の座談会資料、在日女性研究者金富子氏の論文、私に対する批判書『帝国の弁護人、朴裕河に問う』に掲載されたいくつかの文章(学者の李在承、金昌禄、金富子、李娜榮氏。評論家のキム・ヨソプ氏 、歴史評論家のキム・スジ氏など。さらに日本人の前田朗氏の文)が追加されていた。
私は今でも、彼らが自分自身の文章が資料として裁判所に提出されていることを知っているかどうか知らない。もっとも、民事裁判のときから出されていたので、知らないはずはないだろう。いずれにしても、私への告発と処罰要求に力を添えたのは、これらの資料だった。
その他は全て、告発以降に出された私を非難する新聞のコラムや記事などだった。
新聞記事の中に、「慰安婦の強制動員を確認」したというものがあり、マッカーサー作成の機密文書にそうした内容が含まれていたという記事があった。ところが、その原文が同じく資料として出されていた国際法律家委員会の勧告文に入っていた。ところがその内容は、狭い意味の強制動員とはむしろ違った状況である。おそらく検事は、数多くの報告書を資料として出していながら中身まですべてチェックできなかったのだろう。当然といえば当然のことで、そうした資料は検事が探してきたものではなくすべて原告の周辺にいる学者や運動家たちが提供したものだからである。さきの仮処分と民事裁判関係者も、同じくそうした資料を内容まで読んではいなかったに違いない。
以下に、この日の公判での検察の主張、そして私と弁護人の答弁を書いておく。双方とも、パワーポイントやOHPを用いて進行したため、私と弁護人は証人席に一緒に座って、検事が提示する資料を見ながら発言した。裁判官はこの裁判に十分な時間をかけようという態度で臨んでおり、今回の公判では、私も十分発言できるよう配慮してくれた。
この日の公判も朝10時に開始され、昼食時間をはさんで夜7時近くまで続けられた。だから、やはり今回の公判記も、やりとりの全記録ではない。メモできたことのみ、さらに、メモから内容を十分推測・記憶できたことだけ書いてみた。
<午前>
検事:過去の損害賠償請求に関する民事判決は、朴裕河氏の主張を「事実の摘示」と判断している。したがって、朴氏の主張は意見の表明ではなく、「事実の摘示」とみるべきだ。慰安婦の方を売春婦と書いたことに、非難しようとする「故意」があったことを立証したい。被告は日本の責任を免罪したいがため、日韓併合が法的に有効だったとまで述べている。自分の解決方法を貫くため(慰安婦は売春婦であると非難しようとする故意を込めて)この本を書いた。
裁判官:今日の公判に入る前に、いくつか確認を行う。
1)検察の意見書によると、被告は「慰安婦の本質は売春」だと述べた。そして、「故意」(意図)があって売春を強調したという。だとすれば、「売春」を「事実」と認めているのか?であれば、「売春」の事実について、双方の意見の違いはないことが前提となる。そして、だとすれば、本の前後の部分―脈絡をよく調べてみなければならない。
2)「同志的関係」についても脈絡を調べる必要があり、検察は同志的関係にはなかったという事実を論証で明らかにすべきである。言うなれば、売春が事実でなく、同志的関係であった根拠がないといえる証拠を提示すべきである。
3)強制性の否定について、検察は被告が日本の責任を否定しようとしたというが、この裁判では日本に責任があるかどうかについては扱わない。
答弁:日本の責任をなかったことにするための「故意」という主張は、思想の検証だ。本書は、日本による物理的な強制性はなかったとしても、日本に責任があるという主張を展開した本だ。これまでに支援団体などが物理的な強制性、つまり、狭い意味の強制性だけを主張したことよって日本の反発が起きたため、被告は広い意味の強制性を主張し、それについても責任があるとしている。被告が日本に”法的責任を負わせることは難しい”としたことをめぐって、日本に”責任はない”と述べたと主張しているが、むしろ、その反対だ。しかも、日本の責任に関する議論は、裁判官もおっしゃった通り、名誉棄損とは関係のない話だ。
検事:パク・ソンア漢陽大教授が学生とこの本について検討を加えたレポートについて、被告は「学生のレポート」だとしているが、学生の感想は一般人がこの本についてどう感じているかをよく表している。つまり、名誉棄損となる。
答弁:パク・ソンア教授はナヌムの家の顧問弁護士でもある。彼女がナヌムの家の依頼を受け、学生たちに分析させた内容が客観的であり得るだろうか。彼らは「一般人的感覚ではなく、初めからこの本について否定的な態度で検討を加えたとみるべきだ。その上、支援団体が流布した知識以外は、慰安婦問題について知らない学生たちだ。全く同じ本について、慣れない認識の提起に戸惑いながらも肯定的に受け入れ、「元慰安婦の方の痛み」をより深く知ることができたとした一般人も少なくない。刊行直後の新聞等の書評やインタビュー記事はほとんど好意的なものであったし、メディアの反応こそ「一般人」の代表的な反応とみるべきだ。
例えば、リベラルインターネットメディアのオーマイニュースは、この本が「軍隊が女性を性的に搾取する構造」を「普遍的な女性問題として提起」した本であるとし、「帝国の最も恐ろしい点は、被害者を加害者に仕立て上げたところ」だと受け止めている。
検事:(ここでは主に原告サイドが民事裁判で提出した告訴状の内容を発言)この本は自分の解決方法を貫くため、慰安婦について虚偽を書いた本だ。ところが、国際社会も慰安婦制度は性奴隷制度であったと言っている。一方、被告は日本の責任をの免罪するのため、一部の事実をもって全体の事実であるかのように述べている。植民地化していたのに合邦と述べており、『正義とは何か』のマイケル・サンデル教授の主張に照らし合わせてみても、被告は共通善と正義に背いている。他の学者も被告を批判している。ホロコーストを否認した外国の作家は処罰されたのだ。
答弁:被告はこの本で具体的な解決方法を主張してはおらず、法的解決にこだわらず、当事者も含めた協議体を作って議論しなおそうと述べたまでだ。そして、日本語版には植民地支配に関する反省を述べる国会決議をすればよいと書いた。結論が初めからあったわけではなく、証言集や各種の資料、そして慰安婦問題についての研究と運動に検討を加えた結果の言葉だ。国際社会の結論にも疑問を持っている。一部のみをもって主張を行ったというが、前回答えた通り、私が使った証言は必ずしも少なくもなく、少ないとしても、それは記録者の期待に添う口述が多くなる。
運動が長引いているのに解決が遠い状況がもどかしく、9年前に本を書いたが、支援団体等の関係者は無視した。ここ数年来、日韓関係が行き詰まり、国民間の誤解と葛藤状態が深刻になる一方だった。そこで何が問題だったのか改めて考えてみた本だ。
この本のサブタイトルは「植民地支配と記憶の闘争」だ。日韓併合とは不平等な宗主国と植民地の関係と考えるゆえのタイトルだ 。問題の深刻さを他の事案事柄になぞらえて訴えるのは良いが、ホロコーストと慰安婦問題はまったく異なる問題だ。ホロコーストは民族抹殺を意図したものだが、帝国は植民地人を資源として利用するものである。
この本は慰安婦ではなく支援団体を批判した本だ。そしてそれこそが、訴えられた原因だ。実際に、100か所以上にわたる指摘部分の半数近くが挺対協を批判した部分だった。仮処分申請裁判で、原告が指摘した部分のうち、3分の1だけが裁判部で受け入れられたことも、そうしたことをあらわしている。支援団体は物理的な強制連行と考られていた時期の解決方法だけに20年以上拘泥してきていたので、他の方法はないだろうかと問題提起したまでだ。彼らは問題提起を訴えたのだ。
検事:被告は慰安婦が日本軍と同志的な関係にあったため、日本人の軍人と同等の待遇を受けるべきだと述べている。被告のいう補償とはそういうものだ。
答弁:慰安婦が日本軍と同等の待遇を受けるべきだと述べたわけではない。戦場に動員されながら、男性であれば法的保障によって補償されるのに、女性にはそれがなかった。慰安婦も、徴兵と同じ範疇の被害と考える必要があるはずだというのが被告の主張だ。補償については、日本兵ではなく、朝鮮人日本兵と比較した。朝鮮人日本兵にすら法的保障はあったが、それは彼らが男性だったからだった。日本の敗戦のため朝鮮人日本兵はすぐに補償を受けとることはできなかったが、日韓条約以降、少額ながら補償されており、2006年以降にもう一度補償金が渡された。(死亡者の場合、2000万ウォン)
元慰安婦の方の中には「国のために行けと言われたのだから私たちも補償をもらうべきだ」と発言した方もいる。被告のいう同志的関係とはそのような脈絡での話だ。
裁判官:弁護人側は集団名誉棄損に該当しないという論旨について補完を行われたい。
<午後>
答弁:検事は被告の主張に反論するため、マクドゥーガル報告書を提出しているが、マクドゥーガル報告書は慰安婦問題を「強制強要された売春」との言及があり、そのうえで日本は補償の責任を有すると述べている。特記すべきは、この報告書が業者にも言及しており、民間人の関係者も処罰を受けるべきだと書いてある点だ。
検事:マクドゥーガル報告書は法的責任を認めているが、被告は日本の法的責任を認めない。それがこの図書で被告が強制連行ではないと主張している理由だ。
答弁:マクドゥーガルは日本軍が直接に誘拐し、売春を強制したと考えている。被告は、朝鮮半島の場合誘拐もしくは拉致を行った主体のほとんどは業者だということを述べたのであり、強制連行の主体は日本軍だとする少数証言まで否定したわけではない。クマラスワミ報告書などの国連報告書も、慰安所が売春施設であったと述べている。占領地で軍が直接、拉致強姦を行ったことがあったとしても、植民地の女性に起こったことはそうした状況とは異る。報告書も占領地と植民地を区別している。オランダ人慰安婦の場合は占領地の例だ。
検事:ユ・ヒナムさんの陳述書によれば、朴裕河氏が日本政府から20億ウォンをもらってあげると述べたという。
答弁:被告が20億ウォンをもらって来るとか告訴を取り下げれば20億ウォンあげると言ったとかいう悪意に満ちた虚偽が報道され、被告の名誉はとてつもなく傷つけられている。検察がこういう資料まで使わなければ言及せずに済んだことなのに、すでに故人となった方について言及せざるを得なくなってとても残念だ。ユ・ヒナムさんは民事裁判でも同様の話をし、ナヌムの家の所長もその話を広めたが、それは偽証だ。
被告が20億ウォン発言を初めて耳にしたのは、本を出した後で知り合った元慰安婦ぺ・チュニさんとの会話の中であり、その金額を言ったのはユ・ヒナムさん自身だ。アメリカにおいて日本政府と企業を相手取った訴訟の一人当たりの請求金額として提示された金額だと聞いているが、その話を聞いた被告は日本が補償するとしても、そんな金額にはならないと思うと、その会話で述べている。ぺ・チュニさんもまた、ユさんの話を批判するような話を何度もされた。該当する会話が入った記録は、全て提出することにする。
検事:被告は韓国語版と日本語版の内容を変えて書いている。例えば、韓国語版では日本が謝罪をしなかったと書き、日本に向かっては謝罪したと書いた。
答弁:その話は在日研究者の鄭栄桓氏が自分の著書に書いた話だ。だがそれは、韓国人のほとんどが原文を確認できないことに乗じた嘘だ。鄭栄桓氏の指摘が実は意図的な「誤読もしくは嘘」(蔣正一)だという事実を、作家の蔣正一氏が、日本語ができる人の助けを借りて確認し、指摘した文章がある(https://parkyuha.org/archives/3727)。検事の指摘もまた、根拠のない中傷に過ぎない。
検事:被告は韓国語版の発刊後に行われたインタビューで「悪口を言われる覚悟で書いた本」だと発言している。この言葉は、被告自身が慰安婦を売春婦と称した事実について悪口を言われるだろうと考えて書いたものだ。つまり、被告に慰安婦の名誉を棄損しようという「故意」があったことを物語っている。
答弁:その言葉は被告の発言ではなく、インタビューのタイトルだ。インタビューのタイトルはインタビューされる側が決めるものではない。記者がそう解釈したまでであり、その記事も、この本が慰安婦の名誉を棄損しているため悪口を言われる覚悟をしたという内容ではない。
被告が著書の序文に「少し恐れの気持ちもある 」と書いたのは、元慰安婦の方に対するものではなく、支援団体への批判に対する支援団体の反発、そして長い間支援団体の認識のみを共有してきたメディアと一般人の反発に対する恐れだった。
検事:(私が提出したぺ・チュニさんの映像を画面に掲げ、話を起こした文を読み進めたあと、ぺ・チュニさんが挺身隊に入ったという記事を示しつつ)被告は自発的に行った人もいると述べているが、ぺ・チュニさんの場合は挺身隊に行った人だ。
答弁:ぺ・チュニさんは自分で職業紹介所に行ったと話されていた。死後に出された記者の記事と、生前、直接話しておられたご本人の言葉のうち、どちらを信頼すべきだろうか?これについては録音記録で確認してほしい 。
検事:金富子教授の論文によれば、慰安婦は未成年者が大部分だというが、被告はその事実を否定している。
答弁:被告は「未成年者が少ない」とはしていない。映画『鬼郷』に出てくるような14、5歳の少女、大使館の前の少女像に代表される「10代前半の幼い少女」が慰安婦の中心ではなかったと述べたまでだ。
検事:若手歴史学者の指摘によると、小説を使用するなど、問題が多い。
答弁:その座談会こそ、問題が多い。例えば「解放70年」に触れながら韓国の自省を促す 部分をもってきて、元慰安婦の方を批判したと誤認し、非難するなど、基礎的な間違いと曲解がほとんどだ。これについては反論を書いたので、ご参考願いたい(https://parkyuha.org/archives/3759)。
歴史研究者たちは小説はフィクションだとしか考えなかったようだが、前に述べた通り、小説というものは、長い間口にも出せなかった「真実」を込めた告白のメディアでもあった。慰安婦が「数千回もの性交」をしなければならなかったと書いたのも、軍人として慰安婦をそばで見ていた日本人の手による小説だった。検事は日本人の小説なら日本中心主義だろうと無条件に断定するが、それは人によって異なる。被告があえて日本人の小説を使用したのは、慰安婦の証言は嘘だとして否定し続けてきた一部の日本人に向かって、同じ空間にいた日本人がこう書いていると示すためでもあった。
検事:河野洋平・元官房長官が被告のための声明に参加しているということだが、韓国語版を読んでいないからだろう。日本は謝罪したと日本語版に書かれた部分が気に入ってのことに違いない。河野談話は強制性を認めた談話だ。
答弁:被告は著書で河野談話についても再解釈を試みている。河野元官房長官が、被告の著書についてよく知らないまま被告を起訴したこと対する反対声明に参加することなどあり得ない。河野元官房長官は同じ自民党だが、安倍首相の発言を批判するような人物だ。
検事:被告は笑顔で写っている慰安婦の写真を使用している。この写真が朝鮮人であるという証拠はない。
答弁:被告がこの写真を使用した理由は笑顔を強調するためではなく、そのような表情を撮影した記者の胸中が写真に添えられた説明に表れていたためだ。記者は慰安婦の笑顔に「望郷の念を振り払うため」と読み取っていた。被告は韓日の人々の相互理解に努める人物だ。記者のそうした目や気持ちも伝えたくそのキャプションを添えて使った。当時の日本人も悪魔のような日本人ばかりではなかったことを示すために。さらに、写真を取った記者が朝鮮人と書いている。